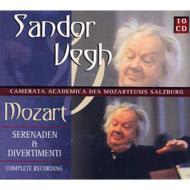
三連休の最終日。先週の週末はお仕事で、昨日・一昨日も外出しておりましたので、久しぶりに家でゴロゴロしております。秋晴れで、昨日行った岡山では秋祭りたけなわでした(別に岡山以外でもそうなんですがねえ)。
そんなわけで、休日のモーツァルトであります。最近はトンとご無沙汰でしたねえ。それで今回は、ディヴェルティメントです。モーツァルトのディヴェルティメントは、番号がついていたり、なかったり、はたまた楽器編成がちがって、管楽器だけのだったり、けっこう複雑です。ケッヘル番号で理解するのがいいのですが、しばらくご無沙汰だと、忘れてしまいます。だから、ケッヘル番号で言われたとしても、うーん、と迷うことしきりです。曲を聴けばわかるのですが。でも、けっこう似ているので、困ってしまいます。今回のディヴェルティメントも、ニ長調K.251です。この曲は、1776年7月、姉のナンネルの25才の誕生日を祝って作曲されたとされています。また、Ob1,Hr2,Vn2,Va1,Cb1の七重奏の編成で演奏されます。そんなところからか、ナンネル・セプテットと呼ばれることがありますね。曲全体にフランス風の影響があることから、アインシュタインは十年前にナンネルとともに、パリに旅行したときの思い出をこめたものとされています。6楽章からなり、第2・第4楽章がメヌエットになっています。
この曲、小編成のオケで演奏される場合と、文字通りの七重奏曲としての場合があります。どちらも、それぞれのよさがあるんですが、個人的な趣味としては、最初に聴いたのが、ハインツ・ホリガー、ヘルマン・バウマンなどとオルランド四重奏団のレコードだったので、七重奏の方を贔屓にしています。他にも、アカデミー・チェンバー・アンサンブルによる演奏もあるのですが、以前にそのCDは取り上げたことがあるので、少々目先を変えまして、シャーンドル・ヴェーグ指揮のザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカの演奏です。1987年の録音。このCDは、10枚組のセットになって発売されていますが、4000円くらいで出回ってます。私は、かなり前ですが、なんばのタワーさんで、なんでか2000円ほどで売られてたのを見つけ、驚きながら買ったのであります。
このヴェーグの演奏、好き嫌いは別にして、素晴らしい快演であります。ウィーン風の典雅な曲が、再び旺盛な生気を取り戻し、たいそう生き生きとした元気一杯の曲となるのですね。しかし、この演奏は、もう出だしから違いますねえ。第1楽章アレグロ・モルト。ユニゾンによる第一主題からして音が違います。そして、弦の響きが実に心地よい。おしてリズミカルな躍動感がこれまた心地よい。音も強弱も明確で、管楽器との対比も絶妙です。第2楽章メヌエット。ヴェーグの強弱のコントロールがは平坦な曲を立体的にし、曲のよさを実感させてくれます。そして、第3楽章アンダンティーノ。この曲の最も美しい楽章。弦とオーボエが美しく優雅な主題を歌います。最初は七重奏版に比べて分厚すぎる印象を持ったのですが、むしろこちらの方がオーボエが上手く聴けます。もっと長く聴きたいくらいですねえ。第4楽章メヌエット。トリオではメヌエットの主題が三つの変奏を展開しています。ここでも弦楽器の微妙な強弱が効果的です。オーボエもいい。第5楽章ロンド。交響曲の終楽章みたい。ヴェーグのロンドは躍動感満喫。そして最後に行進曲が終楽章を飾ります。これはおまけみたい。最後まで、ヴェーグの強弱のバランスが抜群で、それによって素晴らしい生気溢れる生き生きとしたモーツァルトでした。
しかしこの曲は、第1・3・4・5楽章で、まさに4楽章形式の交響曲でもいいですよねえ。そんなことを思うのは、ヴェーグの演奏からだけなんですよね。ヴェーグの演奏は、交響曲的とも言え、そこんところが他のディヴェルティメント的な演奏とは違うんでしょうねえ。
(CAPRICCIO 10 203 1988年 輸入盤)
そんなわけで、休日のモーツァルトであります。最近はトンとご無沙汰でしたねえ。それで今回は、ディヴェルティメントです。モーツァルトのディヴェルティメントは、番号がついていたり、なかったり、はたまた楽器編成がちがって、管楽器だけのだったり、けっこう複雑です。ケッヘル番号で理解するのがいいのですが、しばらくご無沙汰だと、忘れてしまいます。だから、ケッヘル番号で言われたとしても、うーん、と迷うことしきりです。曲を聴けばわかるのですが。でも、けっこう似ているので、困ってしまいます。今回のディヴェルティメントも、ニ長調K.251です。この曲は、1776年7月、姉のナンネルの25才の誕生日を祝って作曲されたとされています。また、Ob1,Hr2,Vn2,Va1,Cb1の七重奏の編成で演奏されます。そんなところからか、ナンネル・セプテットと呼ばれることがありますね。曲全体にフランス風の影響があることから、アインシュタインは十年前にナンネルとともに、パリに旅行したときの思い出をこめたものとされています。6楽章からなり、第2・第4楽章がメヌエットになっています。
この曲、小編成のオケで演奏される場合と、文字通りの七重奏曲としての場合があります。どちらも、それぞれのよさがあるんですが、個人的な趣味としては、最初に聴いたのが、ハインツ・ホリガー、ヘルマン・バウマンなどとオルランド四重奏団のレコードだったので、七重奏の方を贔屓にしています。他にも、アカデミー・チェンバー・アンサンブルによる演奏もあるのですが、以前にそのCDは取り上げたことがあるので、少々目先を変えまして、シャーンドル・ヴェーグ指揮のザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカの演奏です。1987年の録音。このCDは、10枚組のセットになって発売されていますが、4000円くらいで出回ってます。私は、かなり前ですが、なんばのタワーさんで、なんでか2000円ほどで売られてたのを見つけ、驚きながら買ったのであります。
このヴェーグの演奏、好き嫌いは別にして、素晴らしい快演であります。ウィーン風の典雅な曲が、再び旺盛な生気を取り戻し、たいそう生き生きとした元気一杯の曲となるのですね。しかし、この演奏は、もう出だしから違いますねえ。第1楽章アレグロ・モルト。ユニゾンによる第一主題からして音が違います。そして、弦の響きが実に心地よい。おしてリズミカルな躍動感がこれまた心地よい。音も強弱も明確で、管楽器との対比も絶妙です。第2楽章メヌエット。ヴェーグの強弱のコントロールがは平坦な曲を立体的にし、曲のよさを実感させてくれます。そして、第3楽章アンダンティーノ。この曲の最も美しい楽章。弦とオーボエが美しく優雅な主題を歌います。最初は七重奏版に比べて分厚すぎる印象を持ったのですが、むしろこちらの方がオーボエが上手く聴けます。もっと長く聴きたいくらいですねえ。第4楽章メヌエット。トリオではメヌエットの主題が三つの変奏を展開しています。ここでも弦楽器の微妙な強弱が効果的です。オーボエもいい。第5楽章ロンド。交響曲の終楽章みたい。ヴェーグのロンドは躍動感満喫。そして最後に行進曲が終楽章を飾ります。これはおまけみたい。最後まで、ヴェーグの強弱のバランスが抜群で、それによって素晴らしい生気溢れる生き生きとしたモーツァルトでした。
しかしこの曲は、第1・3・4・5楽章で、まさに4楽章形式の交響曲でもいいですよねえ。そんなことを思うのは、ヴェーグの演奏からだけなんですよね。ヴェーグの演奏は、交響曲的とも言え、そこんところが他のディヴェルティメント的な演奏とは違うんでしょうねえ。
(CAPRICCIO 10 203 1988年 輸入盤)


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます