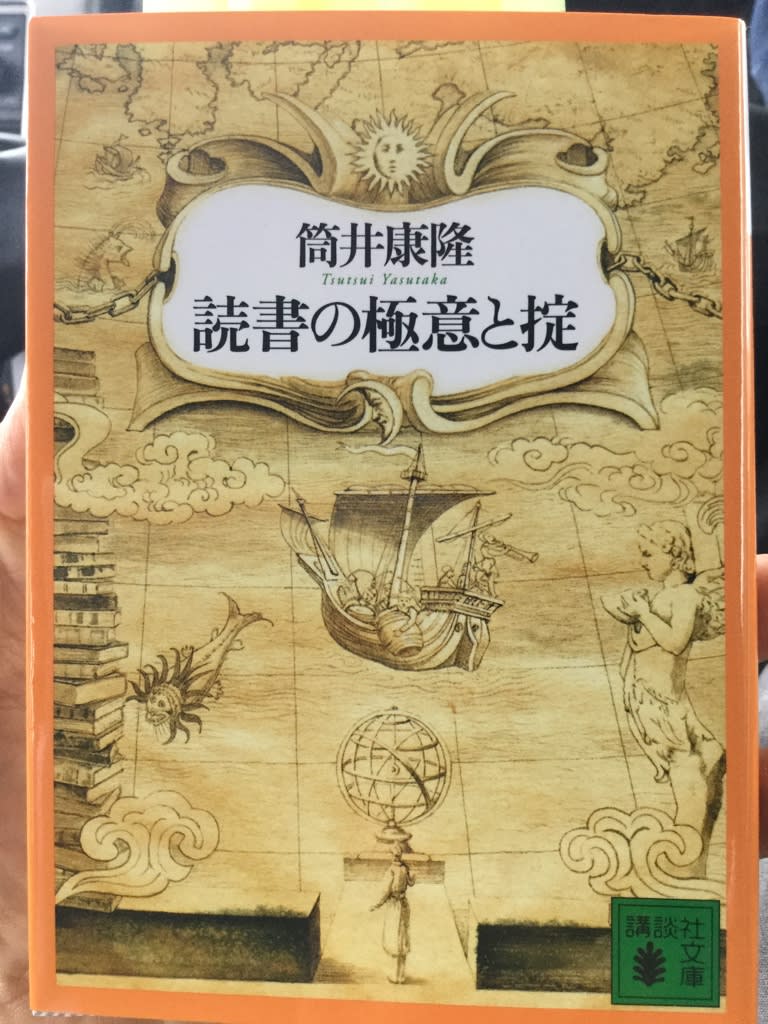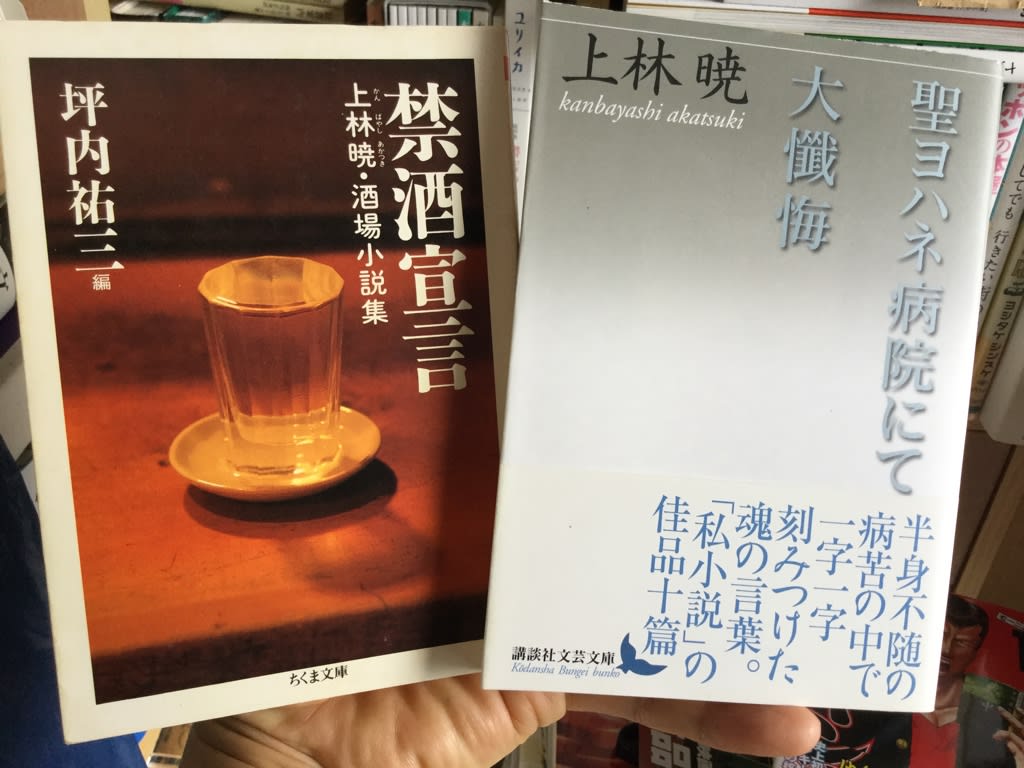『千夜千冊エディション 読書の裏側』
松岡正剛著、KADOKAWA(角川ソフィア文庫)、2022年
現在の日本において、お世辞抜き&掛け値なしに「知の巨人」と呼べる存在である、松岡正剛さんのブックナビゲーションサイト「千夜千冊」。2000年2月23日、中谷宇吉郎『雪』を取り上げた第1夜から始まり、3月はじめ現在で第1817夜まで到達していて、いまなお継続中であります。
取り上げられている書物の幅広さもさることながら、さまざまな他の書物とも結びつけながら展開される精緻な読み込みぶりには、ただただ溜息とともに圧倒されるばかり。読むたびに知的な刺激を受けるとともに、自分の世界がいかに狭いのかを痛感させられております。
その「千夜千冊」を加筆修正した上で、テーマ別にピックアップして構成・編集していく角川ソフィア文庫のシリーズ『千夜千冊エディション』も、2018年の5月にスタートして以降、今年2月までに27冊が刊行され、こちらもなお継続中です。
シリーズ『千夜千冊エディション』の25巻目として刊行されたのが、この『読書の裏側』です。執筆から編集、組版、印刷、出版、そして販売に至るまでの本作りのプロセスや、本の読み方、味わい方などをテーマにした43冊が取り上げられております。やはり書物とその読み方をテーマとした、『千夜千冊エディション』第一弾の『本から本へ』の姉妹篇ともいえましょう。
取り上げられた本の一部を列挙すると・・・渡辺一夫『曲説フランス文学』、林達夫・久野収『思想のドラマトゥルギー』(←ずーっと前に買っておきながら、いまだ読めておりませぬ・・・)、花田清輝『もう一つの修羅』、四方田犬彦『月島物語』、ジャック・ザイプス『おとぎ話が神話になるとき』、吉野孝雄『宮武外骨』(←この本は未読なのですが、宮武外骨はわたしも大好きな怪人&快人編集者であります)、菊池寛『真珠夫人』、須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』(←須賀さんの文庫版全集で読みました)、佐野衛『書店の棚 本の気配』、内澤旬子『センセイの書斎』(←この本はわたしも楽しく読みました)、門谷建蔵『岩波文庫の赤帯を読む』、宮崎哲弥『新書365冊』(←これも実に面白い一冊でした)、斎藤美奈子『本の本』・・・。
『読書の裏側』には至るところで、書物や読書についての松岡さんの持論が熱っぽく語られていて、強く惹きつけられるものがありました。
「引用で綴る、読書と人生の交錯」という副題がついた『本から引き出された本』(マイケル・ディルダ著、早川書房)を取り上げた回はとりわけ、読書の醍醐味を触発してくれるようなシビれる記述に溢れておりました。
まず頷かされたのが、本に没入したり首っぴきになることの功徳を説いたくだりです。
「第一には「そこには世界がある」ということ、第二には親や親戚や友人よりもずっと変化に富んだキャラクターと出会えること、第三に本には人類の英知と努力と逸脱がふんだんに待ってくれているということ、第四にそれらのことが手際よい構成的パッケージになっていること、第五にそれらすべてが自在に選択可能で、かつ類書とつながっている、ということだ。一言でいえば、どんなレパートリーにもどんなシーンにも、どんな人物にも出会えるというトクだ。
(中略)
本を読み出しさえすれば、うっとうしい日々、退屈な夫、くだらない上司、自慢たらたらの友人、ありきたりな部屋、似合わない洋服、貧しい言葉づかいといった、あまりうまくいかない自分の不遇など、まったく嘆く必要がない。ツイッターなど打っているのがもったいない」
本を読むことの功徳と醍醐味を濃縮還元したような、まことに魅力的な読書へのいざない、ではありませぬか。SNSで正義漢を気取り、他者をバッシングすることで溜飲を下げているくらいなら、本の世界に没入したほうがよほど愉しく、充実感もたっぷり得られるというものでしょう。本は類書ともつながっているという指摘も、松岡さんならではであります。
そこからさらに進んで、読書の愉しみを深めていくための秘訣も説かれております。
「もうちょっと本格的に本が好きになるには、「本を読んで理解できるようになりたい」のではなく、「理解するから本が楽しくなる」という逆転感覚をもつことだ。理解できそうもない本を次々に避けているうちに、あの町この町日が暮れて、読書はどんどん遠のいていく」
この一節にも大いに頷かされましたねえ。「理解できそうもない」本には手を出そうともせずに、自分にとって読みやすい本ばかりを読んでいる(「読書好き」などといっておられる人にも、そういったタイプが結構いたりするのですが)というのは、実にもったいないことだと思うのです。一見「理解できそうもない」ような本であっても、じっくりと向き合うことで少しずつ何事かを理解できるようになり、結果として本を読むことをさらに愉しめるようになれるのですから。
その一方で、「何かを学びたい」という動機で本を読むにあたっては、「いったい学習や教育が信ずるに足りているものなのか」と問うことの大切さも語られています。
松岡さんは、「学校で生徒が教わるのは、嘘をつくこと、権威への不名誉な服従、下品な冗談、愚弄と怯懦、臆病者が臆病者をいじめることばかりだ」というバーナード・ショーの言葉や、「教育の主たる目的は、平凡な社会に適応しない人間を作ることである」というノースロップ・フライの言葉(これらの言葉もまことに至言であります)を引きながら、こう述べます。わたしがとりわけシビれた一節であります。
「そうなのだ。何かを学ぶために本を読むなら、自分が平均点から大幅にずれていくことを快感とすべきなのである。きっとピーター・ウィアーの映画《いまを生きる》のラストシーンに泣かされた者ならわかるだろうが、机にしがみつくのではなく、机の上で立ち上がることが、読者の屹立なのである」
「コロナ禍」などと呼ばれている(わたしはあえて「コロナ莫迦騒ぎ」と称しているのですが)この3年あまりの間に目にしたのは、それなりの高等教育を受けてきて、知識や教養をしっかりと身につけているハズの人びとが、「専門家」という「権威」になんの疑問も持たずに服従し、「個」としての判断を放棄し続けたお寒い光景でありました。
それだけになおさら、「権威への不名誉な服従」や「平凡な社会」への適応ではなく、むしろそれらから逸脱し、読者として「屹立」するための読書をこそ指向しなければ・・・と、わたしは強く思いました。
政治的な理由や宗教的な理由、性的な理由、そして社会的な理由によって弾圧され、禁書とされた書物をピックアップした『百禁書』(ニコラス・キャロライズほか著、青山出版社)を取り上げた回でも、実に重い問いかけがなされておりました。
松岡さんは、弾圧の理由の中でも社会的理由による弾圧が最も興味深いと述べ、『アンネの日記』や『時計じかけのオレンジ』(アンソニー・バージェス著)、『フランクリン自伝』などが「良識」ぶった人びとによって非難され、禁じられたり改竄されたりしてきた事実を『百禁書』から拾います。そして、以下のように鋭く指摘するのです。
「検閲と弾圧は書物があるかぎりはなくならない。そう言えるけれども、ほんとうは書く者がいて読む者がいるかぎりはなくならないというのが真相だ。当局による検閲や削除や訂正が断行されるだけではない。出版社や新聞社や編集者によっても、それに良識的読者によってもそれはのべつまくなしにおこなわれている。
ぼくも一、二度、そういう目に遭っているが、良識ぶった出版社や編集者は、どんな内容であれ過激であること、難解であること、非常識であることを嫌う。特殊であること、独りよがりであることを非難する。そこでは「みんなにわかりやすく」「みんな平等に」という美名が独裁的な支配者になっていて、執筆者や著者を凌辱し、平然と汚していく。(中略)わかりにくい、むずかしいという判断こそ、世の中の書物を〝見えない禁書〟に追いこんできたもうひとつのテロルなのである」
われわれは、「わかりにくい」だの「非常識だ」だの「不謹慎だ」だのといった「良識」や「正しさ」を振り回すことによって、結果的に何かの書物を禁書に追いやってしまうようなテロルに加担してしまってはいないだろうか・・・という問いかけを、折にふれてやっていく必要があるではないか、そう思いました。
森銑三や柴田宵曲、内田魯庵、徳富蘇峰、亀井勝一郎などなど、文字どおり「書物の達人」たちを取り上げた『書物の達人』(池谷伊佐夫著、東京書籍)を案内した回にも、実にいい一文がありました。こんな文章です。
「もともと読書とは、先人が読書してきたものを継承して読書することである。もう一度読むこと、それが読書である。一冊の書物は「魔法の絨毯」であり、かつまたそれだけでスモール・ネットワークをもっているのだ。(中略)大半の書物は読み継がれ、いままた読み継がれるのを待っている。
そこにはリレー・リーディングあるいはインター・エディティングがありうる。「継読」こそ読書であり、「共読」「互読」「間読」こそ読書という編集行為なのだ」
一冊の書物を読むことは、先人から連綿と受け継がれてきた「読み」のネットワークの一端につながる行為でもある・・・。一見孤独でちっぽけないとなみに見える読書が、じつは自分ひとりだけにとどまらないタテとヨコの広がりに加わる営為なのだ・・・ということを思えば、とても豊かな気持ちになります。だとすればなおのこと、一冊の書物を「良識」や「正しさ」の名の下に葬り去ることがあってはならないのだと、あらためて思うのです。
ここしばらく、あまり読書に熱を入れていなかったわたし。ですが、松岡さんのおかげで本を読むこと、本と関わることの意味を、あらためて認識することができ、また書物としっかり向き合っていこう、という気持ちが湧いてまいりました。