
『文庫本は何冊積んだら倒れるか ホリイのゆるーく調査』
堀井憲一郎著、本の雑誌社、2019年
森永のチョコボールを1000個以上買って金と銀のエンゼルがいくつずつ出るか調べたり、在京6局のテレビ局のアナウンサーが画面に出ている時間を1週間にわたって調べ上げたり、エロメールによく使われる女性の名前をランキングにしたり・・・。疑問には思っていても誰も本気で調べようとしない(もしくは、そもそも調べようとすら思わない)ようなテーマを取り上げてはとことん調べまくった、『週刊文春』の伝説の連載「ホリイのずんずん調査」で知られるコラムニスト・堀井憲一郎さんが、本にまつわるあれやこれやを調査した一冊であります。
副題どおり、調査の内容はあくまで「ゆるーく」、とりたてて役に立たないものではありますが、それでいて本好きのツボをどこか絶妙にくすぐるようなテーマばかり。堀井さん独特の、これまたゆるーい文体とも相まってやたらに楽しくて、読んでいると1ページに最低2回(多いときには5〜6回)は笑いの発作に襲われました。
書名にもなっている「文庫本は何冊積んだら倒れるか」は、文庫本を出版社別に積み上げていき、倒れる直前の冊数と高さを測るというものです。
岩波うんこ、もとい、岩波文庫を(岩波現代文庫と合わせて)積み上げたら、夏目漱石『坑夫』までは耐えたものの、チョムスキー『統辞構造論』をのっけたら倒れてしまったとか。それで、「漱石とチョムスキーはあまり反りが合わないのかもしれない」と言っちゃったりしていて、思わず爆笑させられました。そりゃこれで「反りが合わない」などと言われた日には、漱石もチョムスキーも立つ瀬がないでしょうけど。
同じ文庫本でありながら、高さに差があるハヤカワ文庫と講談社文庫を並べて、そこに生じる「身長差」の空間に入るスリムな文庫本を調べる、という調査も愉快でした。
文庫本には出版社ごとに微妙な「身長差」があることは知ってはいましたが、そこにスリムな文庫本を「住まわせる」という発想はさすがにありませんでしたねえ。これには思わず脱毛、もとい、脱帽でした。
大きな書店の文庫売り場で、各社の文庫が置いてある棚の幅を歩幅で測る、というのもあります。これによれば、新潮文庫が「17歩」で一番広いスペースを誇っていて、以下講談社文庫、文春文庫および角川文庫と続いて、けっこう多かったのが「5歩」のグループ(集英社文庫や光文社文庫など)だったとか。
まあ、意味がないといってしまえばハイそれまでよ、なのですが(笑)、書店の規模の大小はあっても、どこもおおむね新潮文庫がもっとも多かったりするので、これはちょっと納得でありました。
「小説をめちゃ速読してみる」という項目は、いろんな名作文学の最初の一文と最後の一文だけを読んで小説を味わう、という趣向。たとえば、芥川龍之介の『羅生門』は、
「ある日の暮方の事である。下人の行方は、誰も知らない」
漱石の『坊っちゃん』は、
「親譲りの無鉄砲で、小日向の養源寺にある」
志賀直哉の『城の崎にて』は、
「仙吉は、擱筆することにした」
・・・などといった感じ。まあ、これも他愛ないといっちゃ他愛ないのですが、なんかミョーに楽しかったりいたします。いろいろな名作小説で試してみたら、けっこう面白いかもですな。
名作を音読してみて、読み間違えたところをチェックするという項目も、他愛ないけど面白いお遊びであります。プルーストの『失われた時を求めて』は、集英社文庫版では冒頭からの12行目で詰まり、光文社古典新訳文庫版では23行目でダウン。レイモンド・チャンドラー『かわいい女』の創元推理文庫版(清水俊二訳)では5行目で行き詰まり、ハヤカワ文庫版(村上春樹訳)では11行目で挫折・・・。
確かに堀井さんも書いているように、音読するというのはかなり疲れることではあるでしょうが、名作に親しむという意味ではこれもけっこう、面白い方法かもしれません。・・・人が見ているところでやると怪しまれそうだけど。
そう。本書には、一見敷居の高い名作文学をナナメから楽しむことで、名作が身近に思えるような項目がけっこう多くあったりするのです。ヴィクトル・ユゴー『レ・ミゼラブル』の新潮文庫版全5巻を通読して、主人公であるはずのジャンバルジャンがいかに「出てこない」かを検証した項目も、実に面白く読みました。
それによれば、第1巻の冒頭から1549行、89ページになってようやくジャンバルジャンが登場。それ以降も別の人物が主役となったり、ワーテルローの戦いや修道院などに関する作者ユゴーの〝うだつき〟(脱線)などでジャンバルジャンが出てこない章が多くあり、第3巻に至ってはまったくジャンバルジャンが登場しない(!)んだとか。
ううむ、『レ・ミゼラブル』はこれほどまでに、ジャンバルジャンが「出てこない」お話だったとは。わたしが知っている『レ・ミゼラブル』って、ほんとごくごく一部でしかなかったんだなあ、ということを認識した次第であります。
本書には面白おかしい項目ばかりではなく、文庫本を通して時代の流れが窺えるような項目もあったりいたします。
「新潮文庫15年の作家の違いを眺める」は、2000年と2015年の新潮文庫解説目録を比較して、消えていった海外文学の作家や作品をチェックするというもの。それによれば、2000年にはまだ10作品あったアガサ・クリスティの著作が、2015年版ではすべて消えてしまっていたといいます。また。パスカルの『パンセ』やロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』、テネシー・ウイリアムズ『やけたトタン屋根の猫』、さらには最近ハリソン・フォード主演の映画版が公開されたジャック・ロンドンの『野性の呼び声』も消えてしまったのだとか。けっこう、名作が残っていると思っていた新潮文庫ですら、思っていた以上に名作ものが消えてしまっていたとは。
また、「岩波文庫〔緑〕の欠番を調べてみる」では、岩波文庫の〔緑〕帯(現代日本文学)の中で、2016年の次点で品切れとなっている作家を調べています。ここでも、葛西善蔵や山本有三、岡本かの子、室生犀星、野間宏、草野心平、野上弥生子などなどの面々が、品切れの憂き目にあっていることがわかります。岩波文庫の場合はときおり品切れ本でも重版がかかるので、またいつか復活のチャンスもあるかもしれませんが、それでも岩波文庫ですら、意外な大物の面々が品切れになっていることには、ちょっと驚かされました。
新潮文庫版『ボヴァリー夫人』の1965年版と2015年版を比較して、そこで使われている訳語の違いを追った項目も面白いものでした。「羽根つき」が「バトミントン」になっていたり、「柴を折って」が「たきつけ用に小枝を折って」となっていたりしていて、時代が変われば言葉の使い方も変わっていくということがよーくわかります。
本好きにとっては「あるある」と膝を打ちながら、思わず苦笑してしまうような話題もございます。読もうと思って買っておきながらも、読まないままに積んでおいた本には、「未読の悪魔」が取り憑いて「腐って」いくということをテーマにした項目は、積読本を山のように、どころか山脈のごとく抱えているわたしにとっては、よくわかり過ぎるくらいわかるお話でありました。
また、「人は1年に何冊本を読むのか」という項目では、1年間に何冊の本を読んだかを記録していたら、本を読みたいというよりも「読んだ本の記録数を伸ばしたくて読む」という気持ちが出てきたので、記録することをやめた・・・という、若いときの経験を語っています。その上で、こう記します。
「数字を数えだすと、数字のほうが大事になって、本体はどうでもよくなってしまう。つまり読んだ冊数が大事で、読んだ本はどうでもよくなってしまう」
ああ、数字を気にするようになると、そういう本末転倒なことになりうるよなあ・・・。自分自身にも身に覚えのあることなので、これは気をつけなきゃいけないなあ、と思ったことでありました。
ここのところ、どこを向いても新型コロナがらみのニュースばかりで気が滅入る昨今。たいして役には立たないかもしれないけれど、なんだか楽しい本のお話を、ゆるーいジョークやギャグを散りばめた文章で綴った本書は、無性に愉快な気持ちにさせてくれました。
書物に格調高い教養やら、社会に対するスルドイ問題意識やらを求める「正統派」読書人にはあまり向かないかもしれませんが、遊び心とともに本を愉しみたいという方には、大いにオススメしたい一冊です。




















































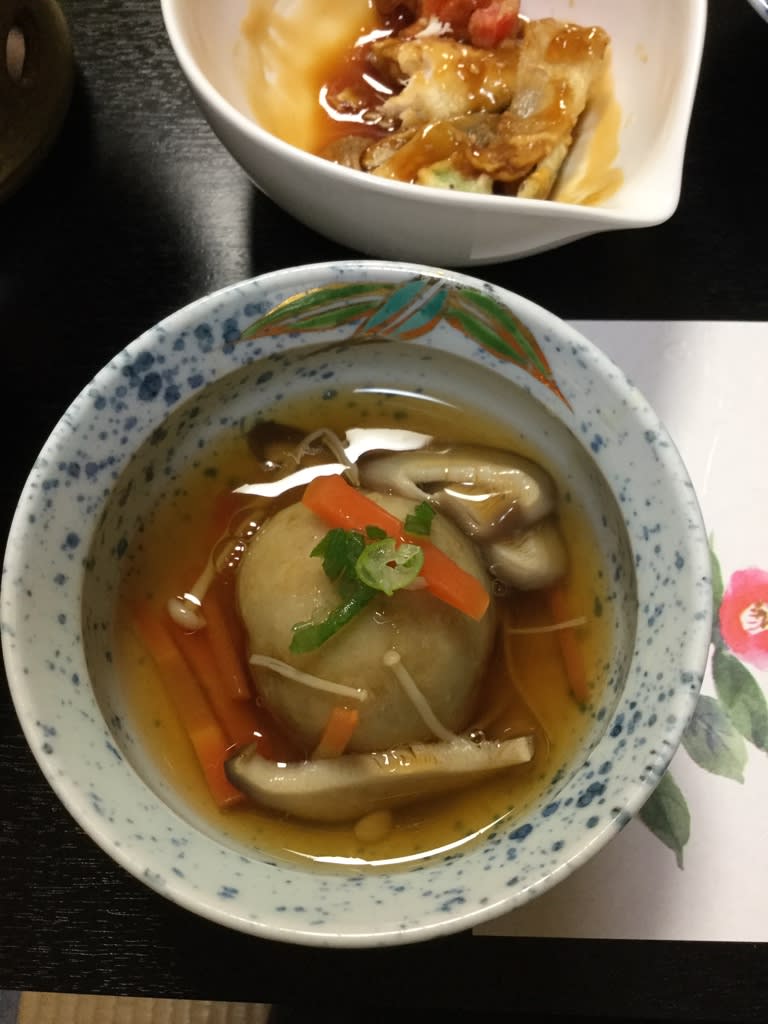




 提灯のあかりと、宿の窓から漏れるあかりで、ほのかに照らし出れた石畳の坂道・・・。実際に目にした光景は、ここに上げた画像よりもはるかに美しく、幻想的なものでした。わたしは浮かされたように、温泉街をぶらぶらと歩きました。
提灯のあかりと、宿の窓から漏れるあかりで、ほのかに照らし出れた石畳の坂道・・・。実際に目にした光景は、ここに上げた画像よりもはるかに美しく、幻想的なものでした。わたしは浮かされたように、温泉街をぶらぶらと歩きました。

