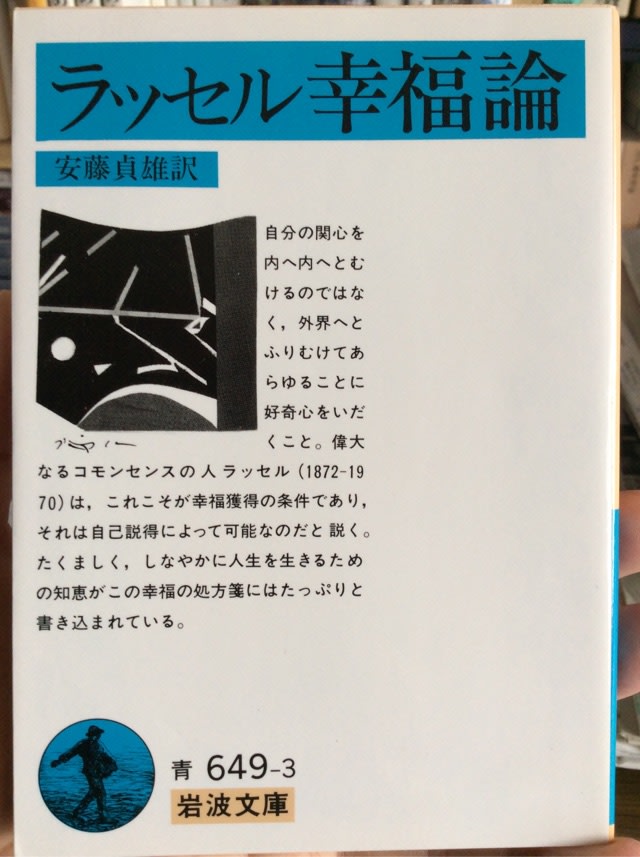
『ラッセル 幸福論』
バートランド・ラッセル著、安藤貞雄訳、岩波書店(岩波文庫)、1991年
「幸福論」と銘打った書物はいろいろとあるのですが、その中でも数学者・哲学者にして平和運動にも尽力したバートランド・ラッセル(1872ー1970)の書いた『幸福論』をオススメしたいのは、この本が「合理的・実用主義的(プラグマティック)な幸福論」(巻末の訳者による解説より)だからであります。
「幸福論」というと、いささか説教くささのある宗教的なものや、もってまわったもの言いの哲学的・文学的なものが多かったりいたします(むろん、それらの中からも有益な知恵を汲み取ることはできるのですが)。ラッセルの『幸福論』は、合理的かつ実用主義的であるがゆえに、誰しもが可能でもある方法と考え方によって、幸福を得ることができるということを説いていきます。その語り口は、哲学書の一種とはいえ非常に明快で、読む人はここから多くのヒントや知恵を得ることができるに違いないでしょう。
前半の第一部「不幸の原因」では、現代人を不幸にしている諸原因を列挙、分析し、それらへの対策が示されていきます。
競争、疲れ、ねたみ、被害妄想、世評に対するおびえ・・・。不幸の原因として挙げられているそれらについてのラッセルの分析を読んでいると、本書の原書が1930年に刊行されたものとは思えなくなるほど、今の日本に生きる人びととの共通性を強く感じます。
ねたみの結果期待される「公平」とは「不運な人たちの快楽を増すよりも、幸運な人たちの快楽を減らすことを旨としている」、ひいては「公的生活をも破壊するものである」と述べられているところ。また、「重大な問題でもささいな問題でも、他人の意見が尊重されすぎている」ことにより「自ら進んで不必要な暴力に屈」して「あらゆる形で幸福をじゃまされることになる」という記述。いずれも、今の日本の少なからぬ人びとが抱えている状況と重ならないでしょうか。
本書の後半、第二部の「幸福をもたらすもの」の中で、ラッセルが幸福獲得の条件として強調して説いているのが、「自分の殻に閉じこもらずに、外の世界に関心と興味を向けること」です。
「幸福な人とは、客観的な生き方をし、自由な愛情と広い興味を持っている人である」と定義するラッセルは、幅広い事柄へ関心と興味を向けることの効用を、随所で熱っぽく語っています。
いくつか引いてみましょう。
「この世界は、あるいは悲劇的、あるいは喜劇的、あるいは英雄的、あるいは奇怪または不思議な事物にみちあふれている。そこで、世界の提供するこの壮大なスペクタクルに興味を持てない人びとは、人生の差し出す特典の一つを失っていることになる。」
「人間、関心を寄せるものが多いほど、ますます幸福になれるチャンスが多くなり、また、ますます運命に左右されることが少なくなる。かりに、一つを失っても、もう一つに頼ることができるからである。」
「幸福の秘訣は、こういうことだ。あなたの興味をできるかぎり幅広くせよ。そして、あなたの興味を惹く人や物に対する反応を敵意あるものではなく、できるかぎり友好的なものにせよ。」
さまざまなことに関心や興味を向けることで、生きることが楽しく豊かなものになるということを、さやかながら実感しているわたくしにとって、ラッセルの説く幸福の秘訣はとても納得と共感を覚えるものでした。
いま、少なからぬ人びとが不安や不信にさいなまれる一方で、自分の身の回りを中心にした内向きで狭い範囲のことばかりにとらわれ過ぎているように思えてならないところがあります。
・・・などと申しているわたくし自身も、ここしばらくはあまりにも瑣末なことに目が向いたり、気持ちを奪われすぎていたりしていたことで関心や興味が狭いものとなり、結果として自らの内面が澱んでしまっていることを、久々に開いた本書を通じて自覚せざるを得ませんでした。
関心や興味が狭いものにとどまってしまうと視野も狭くなり、ちょっとしたことで行き詰ってしまうことが増えるように思います。それよりなにより、幅広い関心や興味、好奇心を持たないと面白くもないですし。
人生への熱意を取り戻し、もっとしなやか、かつ楽しく有意義に生きていくためにも、ラッセルの説く幸福への処方箋が多くの人に読まれてほしいと願います。そしてわたくし自身も、思考と視野が狭くなっているようなときには本書に立ち返り、精神の糧としていきたいとも思います。
最後にもう一つ、少々長くなるのですが引かせていただきます。いま、なんらかの不幸に沈む人たち、そして、今後なんらかの不幸に直面するであろう全ての人に、さらにはわたくし自身にも自戒を込めつつ、この言葉を。
「十分な活力と熱意のある人は、不幸に見舞われるごとに、人生と世界に対する新しい興味を見いだすことによって、あらゆる不幸を乗り越えていくだろう。その興味は、一つの不幸のために致命的になるほど制限されることは決してないのだ。一つの不幸、いや数度の不幸によってさえ敗北してしまうのは、感受性に富むあかしとして賞賛されるべきことではなくて、活力の無さとして遺憾とされるべきことである。」

















