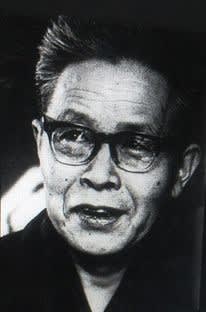雑誌「歴史人」 2022年6月号
沖縄復帰50年---繰り返さないために、いま語り継ぐべきこと
沖縄戦
航空機による特攻は、その数なんと2.500を数えたという。
人間魚雷の回天も沖縄戦に投入された。
さらに人間ロケット桜花も使用された。
こうした特攻攻撃で撃沈された船は、
わずかに駆逐艦9隻。
戦艦や空母などには、かすり傷しか与えることはできなかったが、
アメリカ兵に対する精神的動揺は、相当なものがあったと考えてよいだろう。
連合艦隊の超弩級戦艦大和もこのとき、海上特攻攻撃に使用されている。
片道燃料だけを積んで、徳山湾を出港し沖縄へ向かった。
海岸に乗り上げさせた後、あらんかぎりの砲弾を敵艦隊にお見舞いし、大打撃を与えようとする計画だった。
だが、すでに制空・制海権を完全ににぎられていたため、計画自体が無謀なもので、
九州の坊ノ岬沖で沈没してしまった。
沖縄南部には民間人が10数万人いたといい、
彼らは日本軍の側にいることが安全だと思い、軍に付き従っていた。
というのは、
アメリカ人は鬼畜だという教育を受け、捕まれば拷問されたり凌辱されたりした後、むごい殺され方をすると信じていたからである。
沖縄の女子学生たちは、野戦病院の看護婦として従軍させられていた。
ひめゆり部隊も、そうした学生看護師隊の一つだった。
彼女たちは第三外科壕にいたが、そこにアメリカ軍がガス弾を投げ込んで、数十名の若い命を奪ったのである。
沖縄県民の命は、アメリカ兵だけでなく、日本兵も足手まといになる民間人に自決を強要したり、スパイ容疑をかけて射殺したりということが起こった。
6月22日、牛島中将は司令部で自殺した。「日本兵は命あるかぎり戦い続けよ」と遺言した。
軍人・民間人含めて20万人が犠牲となった。
沖縄県民は、なんと4人に1人が死んでいる。

兵力不足を補うため、県民25.000名を召集した。師範学校や中学校、専門学校の、高等女学校の生徒も徴用した。
1761名の男子は「鉄血勤皇隊」、543名の女子生徒は緊急看護衛生班員となった。
5月3日夜から総攻撃開始、目標とする米軍陣地までたどり着けないまま全滅する部隊が相次いた。
5月5日、午後6時総攻撃中止を命じた。
5月7日、ドイツが連合軍に降伏。
6月13日、海軍大田実少将以下の首脳陣は自決し、組織的抵抗に終止符を打った。
自決の直前、大田少将は海軍省の海軍次官宛てに電報を打った。
それは、今度の戦いで沖縄県民がいかに作戦に協力をしてくれたかを細かに述べるとともに、
「沖縄県民かく戦えり、県民に対し後世特別の御高配を賜らんことを」
と結んであった。
6月18日、ひめゆり部隊の看護女学生27名は、米軍急襲を受け全員即死。
6月19日、牛島軍司令官は指揮権放棄を宣言した。もう各部隊との連絡もつかなかったからである。
6月23日、牛島司令官、長参謀長は洞窟内で自決した。
約7.000名が投降した。
戦没者は18万、うち県民は12万。(軍属2.8万、一般9.4万)と言われる。
米軍死者は1.2万人だった。
・・・・・