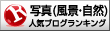みのおの森の小さな物語
(創作ものがたり NO-15作 (1)~(7))
トンネルを抜けると白い雪 (1)
「 トンネルを抜けるとそこは雪国だった・・・ か 」
太田垣 祐樹はボソッとつぶやきながら我に返った。
なぜそんな言葉が口をついて出たのだろう・・・か?
箕面グリーンロードトンネルを抜けて止々呂美(とどろみ)の出口にでると、
真っ暗闇の中に車のライトに照らされた白く輝く銀世界が広がっていた。
トンネルを入るまでは全く雪がなかったので一瞬ビックリしたものの
すぐにまた自分の世界へと入っていった。
三ヶ月ぶりに自宅に帰る・・・
と言っても誰もいない家に帰るのは何とも気が重いものだ。
ほんの40分ほど前まで、祐樹は梅田の新ビジネス街に建つ高層ビルの
一室で、苦手な外人バイヤーとの厳しい商談を終えたばかりだった。
その直後、弁護士から 「離婚が成立しました・・・」 と電話があった。
・・・そうか終わったのか・・・
祐樹は26階のオフィスから眼下に広がる光り輝く大都会の街の明かりを
ぼんやりと眺めていた。
・・・やっぱりここはボクの住む街じゃないな・・・ と一人つぶやいた。
そして急にこの連休は一人静かに過ごしたい・・・ との思いから
同僚との飲み会を断り、いつしか車はかつての自宅へと向かって
いたのだった。
先日、祐樹は会社の上司からニューヨーク支店への転勤内示があったが、
何度も自分の心と対峙し熟考のうえ辞退を申し入れていた。
同僚や後輩はその早い栄転を羨ましい言葉で賛辞しながらも
やっかみ半分のところがあった。
そのやっかみは祐樹が入社してすぐに感じていたことっだった。
「あいつの入社は俺たちと違ってきっとコネだからな・・・
何しろ親父は国会議員だし、上の兄貴は地方議員でいずれ
親父さんの後をつぐんだろうしな。
母親はその道の家元で全国に教室があるとか聞いたし、
下の兄さんは大学病院の精神科医でTVにもよく出ているし、
フランスにいる姉さんはたまに週刊誌にもでてる有名なファッション
デザイナーなんだろう・・・
あいつの一族はまさに<華麗なる一族>といったところだからな・・・
しかし どうもあいつだけはちょっと異色で変わってるよな・・・
エリートコースのニューヨークを断るなんてバカじゃないの・・・?」
同輩や後輩らと飲みに行くと必ず家のことを何かと聞かれるので
祐樹はほとほと嫌気がさしていた。
・・・ボクはボクなのにな・・・
みんなボク自身のことより、家族やその背景のことばかり気になる
ようだな・・・ といつも自嘲気味に笑っていたが心は憂鬱だった。
・・・あんなビジネスの激戦地みたいな所へいったらもう自分が自分で
なくなってします・・・
自分らしく生きたい・・・ 小さな自分の夢を追ってみたい・・・
やっかみ半分の同僚たちの思いと祐樹の思いとは、全く別の次元のもの
だったが、それは会社の誰もが知る由もなかった。
梅田の会社駐車場から出て新御堂筋に入ると、祐樹の
イタリア製最高級スポーツカーはすべるように江坂、千里中央を経て
箕面グリーンロードトンネルに入った。
この車も自分の好みと全く違ったが妻が選んだ車だった。
そこを5分ほどで抜けるとあの梅田の街の喧騒から30分ほどで
全くの別世界に入っていった。 そしてそこには白銀の世界が広がっていた。
・・・これが幸せと言うものなのか・・・ と思えた1年ほど前の日々を
想う・・・
どこかいつも 違う 違う と思いつつも、祐樹は子供のころから
自分の気持ちを抑え、心をごまかしながら両親や兄姉の指示や
言葉に従順に生きてきていた。
30歳をいくつか過ぎ、やっと祐樹は自分の歩んできた今までの道を
省みていた。
祐樹は母親が41歳のときに予定外で生まれた子供だった。
もうすでに上の兄は19歳、次兄は17歳で姉は15歳と年の差があったので、
それが為にそれぞれにみんなが可愛がってくれた。
それは一方で過保護となり、過干渉であったりして自我に目覚めると
随分とそのことに悩んだりしたこともあった。
しかし、元来素直で従順で優しい性格の祐樹は、そんな周りの保護の中で
強く自己表現することもなく、常に争いごとを避けて暮らす習慣が身に
ついていた。
だが一度だけ大きく家族に反発したことがあった。
それは高校生になったころ、両親や兄姉らがこぞって
「お前は弁護士になれ・・・ 医者を目指せ・・・ 」
と次々に干渉され、その必要性を懇々と説かれたことだった。
「人生の競争に勝つためには・・・ 人の上に立たねば・・・
権力、名誉、金、力を持てば人はついてくる・・・幸せもついてくる・・・
自分に合った仕事なんて無い・・・自分を合わせるんだ!
お前の祖先も両親も俺たちもみんなそうやって成功を
つかんできたんだ・・・」
「もういい加減にしてくれ・・・ボクはボクの人生を生きるんだ!」
と はじめてみんなの前で反抗し叫んだときだった。
しかし、次の日からまた何事も無かったかのように祐樹の訴えは無視され、
再び過干渉が始まった。
そして祐樹はいつしか ・・・まあいいか・・・ と
それまでの習慣どおり、みんなの意見に自分を従わせようとしていた。
そしてそれはやがて自分の夢や希望や感情までも抑え、家の重圧に押され
毎日現実的な対応を余儀なくされていた。
塾に通い、習い事に明け暮れ、競争社会には全く合わない自分を知り
ながらも、いつしかそんな嫌いな社会の渦の中に巻き込まれていった。
しかし いざとなると自分は人との争いごとの間に立つ弁護士など
天敵とも思えるぐらい全く向かない職業だと思った。
それに医師の次兄の薦めで医学部を目指そうと思ったものの、
本来血を見ただけで怖くて卒倒しそうになるのに、人の死と向き合う
医師など全く存外で自分には向かないと確信して断念した。
「じゃあ 何になりたいんだ・・・」 と問われるので、祐樹は漠然とだが
「ボクは植物や動物が好きだから・・・山も好きだし・・・絵も・・・」
「そんなもの勉強したって食っていけるわけ無いだろう・・・
まじめに考えろ!」
と怒られていた。
なぜそんな言葉が口をついてでたのか・・・
そこには祐樹に一つ思い出に残る印象があった。
それはまだ祐樹が小学生の頃、家族みんなが仕事で多忙な頃に
家族に代わって周りの取り巻きの人たちが東京のデズニーランドや
大阪のユニバーサルスタジオ、映画や遊園地などにもよく連れて行って
くれた。
しかし、祐樹がもっとも印象に残ったのは、ある日小学校の遠足で行った
箕面の滝への道だった。
近くの山麓に住んでいながらこんな所があるとは全く知らなかった。
箕面川の渓流が岩にぶつかり、白い水しぶきを上げてダイナミックに
流れている・・・
その岩の上に一羽のアオサギがじっと置物のように身動きせず水面を
見つめて狩りをしている姿・・・
美しいコバルトブルー色したカワセミがあっという間に水にもぐり
小魚をくわえて小枝に戻ってきた姿に、祐樹は初めての感動を覚え
興奮した。
山麓に咲く小さなイチリンソウ、ニリンソウなどの野花は、街中では
見られない素朴で清楚な姿をしていて祐樹の心をとりこにした。
野花をみて 「 きれいだな・・・」 と初めて子供心に感動した。
それに野生のサルが群れで木々の上を動き回って木の実を食べている姿は
動物園で見たサルと違って興奮した。
見るもの一つ一つが祐樹の子供心を刺激し琴線に触れるものがあった。
見上げれば美しく紅葉した森が広がっている・・・
祐樹は落葉したそんなもみじの葉を数枚拾い、持ち帰って本にはさみ
押し葉にした。
今でもその押し葉を見るたびに、あの時の感動を思い出すのだ。
祐樹は近くの山麓に住んでいながら今まで家の高台から見る視線は
いつも南側に広がる大阪平野であり、その先に林立する大都会の
近代的ビル群だった。
それが初めて反対側の裏山の箕面の森の中へ行ったとき、祐樹の心を
動かすほどのものがあったのだった。
次兄にその感動を話したとき・・・
「お前の生まれる前にもう亡くなっていたけど、祖父は旧帝大出の
有名な植物学者だったそうだ。
それで親父は子供の頃よく束ねた新聞紙を持たされて爺さんと裏山を
歩いた・・・ とか言ってたな・・・
なんでも箕面の山には日本の羊歯(シダ)類の相当数の種類が
自生しているとかで、その採集の手伝いをさせられたんだろうな・・・
お前はそんな爺さんの遺伝子を引き継いでいるのかも知れんな・・・」
と笑われた。
「もう勝手にしろ!」 と言う家族の声に これ幸い! とばかりに
祐樹は初めて自分の意思で大学を選んだ。
それはみんなが全く想像外の<心理学>を専攻し、大学院では
<農学、園芸・森林療法と自然環境学分野との融合> を研究した。
この6年間は祐樹にとって実に充実した日々を過ごした。
しかし、祐樹は卒業を前にして再び両親や兄姉からの強い過干渉が
始まった。
そしていつの間にか<特別推薦枠>とかで、考えても見なかった
総合商社へすんなりと採用されたのだった。
それは国際社会を舞台に、ビジネスでの激しい競争を繰り広げる
会社だった。
祐樹は相変わらずどこかで 違う・・・ 違う・・・ と思いつつも仕事に
没頭し6年が経っていた。
この間に名門家系の御曹司で末っ子ということもあり、次々と縁談が
持ち込まれ、親の薦めに反対できず何度も見合いをしてみたが、
祐樹の心に触れる女性は一人もいなかった。
ある日、祐樹は会社の重役の誘いで、ある財界のパーテーに招待された。
そしてそこである女性を紹介された。
祐樹は本来最も苦手なそんな所で酔うことなど無いのだが、仕事の
ストレスもあり、勧められるままにしこたま飲んで酔っ払ってしまった。
そしていつしかその女性から介抱される始末になり、気がつけば彼女の
赤い車の横に乗って家まで送ってもらうことになった・・・
そこまでは覚えているのだが・・・?
ふっと気がついて目を覚ますと、祐樹はホテルのベットに裸で寝ていた。
横には見慣れない女性が寝ている・・・
祐樹は あっ! と声をあげそうになった。
後日知ったことだが、この女性は中々結婚しない末息子を心配した
父親が、自分の政治後援会長に相談したら、なんとその会長は自分の
一人娘を連れて来ていたのだとか・・・
しかし、その後の展開と行為は予想外だったらしい。
祐樹は自分の愚かさと女性へのすまなさとで自責の念にかられ、
恐縮の日々を過ごしていた。
そしてそれはやがて祐樹の世界を一変させていった。
(2) へ続く・・・