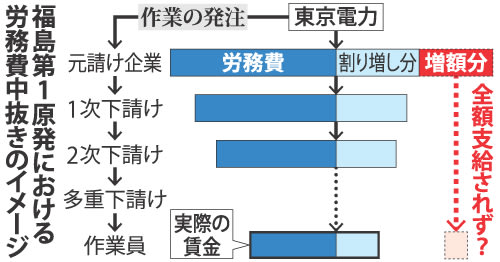毎日新聞 2014年01月06日 11時30分(最終更新 01月06日 12時30分)
【テヘラン田中龍士】イランのサレヒ原子力庁長官は5日、ウラン鉱石を採掘するガチン鉱山に対する国際原子力機関(IAEA)の査察を今月中に受け入れると発表した。核兵器開発疑惑解消のためIAEAと昨年11月に署名した共同声明に基づく査察。昨年12月に重水製造施設の査察を受けており、相次いで声明を履行して透明性を強調する狙いがある。
ガチン鉱山はイラン南部にあり、2004年に採掘を開始。ウラン鉱石を製錬したウラン精鉱(イエローケーキ)は、中部イスファハンの施設で六フッ化ウランに転換し、中部ナタンツの施設で濃縮されてきた。IAEAは主に衛星で監視を続けてきたが、現場査察で実態がより明らかになる可能性がある。
11月に署名した共同声明は、原子力発電所や研究炉の新設情報の提供▽新たなウラン濃縮施設の明確化▽西部アラクの重水製造施設の査察--などを明記。重水製造施設の査察は昨年12月、声明発表から1カ月以内で実施された。
サレヒ氏は5日、「イランは合意事項の実施に全力で取り組んでいる」とアピール。天野之弥・IAEA事務局長報告がイランの姿勢を「前向きだ」と評価した点に触れ、「次回の報告も同様の扱いを受けるだろう」と自信を見せた。昨年末には、改良型遠心分離機「IR2m型」について「1000台導入したが、稼働させていない」と述べており、昨年11月の米欧など主要6カ国との合意を踏まえ、活動を自粛していると強調した。
一方、イラン国会(定数290)では昨年12月下旬、米国が同月初旬に発表した制裁対象拡大に反発し、新たに制裁が強化された際には、濃縮度60%のウラン製造に着手することを政府に求める法案を一部議員が提起した。審議は進んでいないが、賛同議員は今月5日までに200人に達した。合意以外の要求がなされたり、決定事項が守られない場合、強硬に臨む姿勢を示した。
【テヘラン田中龍士】イランのサレヒ原子力庁長官は5日、ウラン鉱石を採掘するガチン鉱山に対する国際原子力機関(IAEA)の査察を今月中に受け入れると発表した。核兵器開発疑惑解消のためIAEAと昨年11月に署名した共同声明に基づく査察。昨年12月に重水製造施設の査察を受けており、相次いで声明を履行して透明性を強調する狙いがある。
ガチン鉱山はイラン南部にあり、2004年に採掘を開始。ウラン鉱石を製錬したウラン精鉱(イエローケーキ)は、中部イスファハンの施設で六フッ化ウランに転換し、中部ナタンツの施設で濃縮されてきた。IAEAは主に衛星で監視を続けてきたが、現場査察で実態がより明らかになる可能性がある。
11月に署名した共同声明は、原子力発電所や研究炉の新設情報の提供▽新たなウラン濃縮施設の明確化▽西部アラクの重水製造施設の査察--などを明記。重水製造施設の査察は昨年12月、声明発表から1カ月以内で実施された。
サレヒ氏は5日、「イランは合意事項の実施に全力で取り組んでいる」とアピール。天野之弥・IAEA事務局長報告がイランの姿勢を「前向きだ」と評価した点に触れ、「次回の報告も同様の扱いを受けるだろう」と自信を見せた。昨年末には、改良型遠心分離機「IR2m型」について「1000台導入したが、稼働させていない」と述べており、昨年11月の米欧など主要6カ国との合意を踏まえ、活動を自粛していると強調した。
一方、イラン国会(定数290)では昨年12月下旬、米国が同月初旬に発表した制裁対象拡大に反発し、新たに制裁が強化された際には、濃縮度60%のウラン製造に着手することを政府に求める法案を一部議員が提起した。審議は進んでいないが、賛同議員は今月5日までに200人に達した。合意以外の要求がなされたり、決定事項が守られない場合、強硬に臨む姿勢を示した。