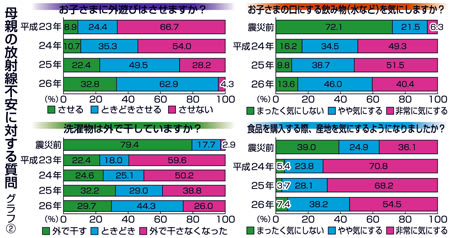今年度原子力防災訓練の会議 NHK
松江市にある島根原発から放射性物質が漏れたという想定で来月行われる鳥取県と島根県の合同訓練について、県内の関係者が話し合う会議がきょう開かれ、初めて実際のスクリーニング会場を使うなどの訓練の概要をまとめ島根県と最終的な調整を行うことになりました。
この会議は、来月18日に鳥取県と島根県が合同で行う原子力防災訓練の内容について話し合うため開かれたもので、県や米子市、境港市の職員など県内の関係機関からおよそ90人が出席しました。
訓練は、島根原発2号機から放射性物質が外部に漏れた想定で行われ、およそ800人が参加することになっています。
きょうの会議では、大山町にあるスクリーニング会場を初めて使うことや、バスや列車、船といった交通機関を使った住民の避難、それに障害者や外国人の避難のため通訳などの支援者を派遣する訓練も行うことを確認しました。
県は今後、島根県と調整し、来月上旬には最終的な訓練の内容をまとめるということです。
県危機管理局の渡辺剛英原子力安全対策監は「鹿児島県の川内原発が国の規制基準に合格するなど、再稼働の流れになっているが、自治体として、万が一に備え、避難方法を確認したい」と話していました。
09月11日 19時58分
松江市にある島根原発から放射性物質が漏れたという想定で来月行われる鳥取県と島根県の合同訓練について、県内の関係者が話し合う会議がきょう開かれ、初めて実際のスクリーニング会場を使うなどの訓練の概要をまとめ島根県と最終的な調整を行うことになりました。
この会議は、来月18日に鳥取県と島根県が合同で行う原子力防災訓練の内容について話し合うため開かれたもので、県や米子市、境港市の職員など県内の関係機関からおよそ90人が出席しました。
訓練は、島根原発2号機から放射性物質が外部に漏れた想定で行われ、およそ800人が参加することになっています。
きょうの会議では、大山町にあるスクリーニング会場を初めて使うことや、バスや列車、船といった交通機関を使った住民の避難、それに障害者や外国人の避難のため通訳などの支援者を派遣する訓練も行うことを確認しました。
県は今後、島根県と調整し、来月上旬には最終的な訓練の内容をまとめるということです。
県危機管理局の渡辺剛英原子力安全対策監は「鹿児島県の川内原発が国の規制基準に合格するなど、再稼働の流れになっているが、自治体として、万が一に備え、避難方法を確認したい」と話していました。
09月11日 19時58分