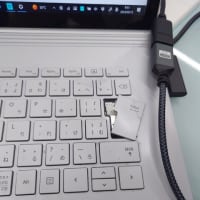昨日の続き。
判決中、「独占適応性」について、以下の各点を指摘して本件の独占適応性を否定している。
ア 油圧ショベルは,様々な作業を行うことができる多様性を有し,その用途に汎用性があるため,建設業において広く用いられているほか,農業や林業にも利用されており,油圧ショベルの需要者には,建設業者,建設機械を取り扱う販売業者及びリース業者のみならず,農業従事者及び林業従事者等も含まれること,
イ 本願商標の色彩と同系色の「橙」色(マンセル値:5YR6.5/14)は,人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火,健康上有害な情報並びに緊急避難を目的として規格化された「JIS安全色」の一つであり,ヘルメッ
ト,レインスーツ,サイトウェア,ガードフェンス等にオレンジ色が使用され,オレンジ色は,工事現場で一般に使用されている色彩であること,
ウ 原告以外の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧ショベルを販売していたこと,
エ オレンジ色は,黄色と赤色の中間色であって,基本色の一つであることから,オレンジ色の色彩名から観念される色の幅は広いものである上,人の視覚によって,マンセル値で特定された本願商標のオレンジ色とマンセル値の異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することには限界があり,加えて,本願商標は,色彩を付する位置を特定した,単一の色彩のみからなる商標であり,色彩を付する位置の部分の形状や輪郭に限定がないため,本願商標の商標登録が認められた場合の商標権の禁止権(商標法37条)の及ぶ範囲は広いものとなること
「ア」は、主に原告の主張①(=ショベルの参入企業は限定的である)に対するカウンター。
需要者の幅が広くなればその分混同可能性は高く評価され得る。
「イ」は、本当に3条1項3号の該当性の話なのだろうか?「JIS安全色の一つ」であるのならば、それを独占的に使用すべく登録することは公序良俗の問題ではないのか?
「ウ」について、まさに昨日言及した点(=「永年の間,他人に使用されることなく,独占的排他的に継続使用した実績を有する場合」に該当するといえるかどうかを基準として判断した」点についての審決の実体的違法性に関する主張)についての答えになっている部分。
”他人に使用されることなく”を「要件化」しているとも受け止められる。ちょっと踏み込み過ぎじゃないか?と思う。
「エ」も、出願の段階で「色彩のみからなる商標を構成する色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組み合わせ方(色彩を組合せた場合の各色の配置や割合等)等についての具体的かつ明確な説明」を記載することが求められている。「色彩の類否」という独特な議論が生まれる余地があるにはあるが、ここまで細かく規定して出願する以上、色彩については類似の幅はかなり制限的に取り扱って良いのではないかと思うがどうなのだろう?
この判決では、禁止権が及ぶ「類似の範囲」には、例えば”同系色のオレンジ色”も含まれ得る、ということを懸念している。本願の場合はさらに部分の形状や輪郭に限定がないから禁止権の範囲が著しく広くなるとしている。
でも、出願人は果たしてそこまでの「禁止権」を欲しているのだろうか?
本件の出願人は、というのと、広く一般的「色彩のみからなる商標」を出願する人は、という2つの意味で疑問。
制度として禁止権の範囲を自ら限定的にすることで権利化可能性を高めることができる仕組みがあっても良さそうに思う。包袋禁反言でもよいけど。
今のままでは、出願しても登録の見込みは極めて低く、使い勝手の良くない制度になってしまう。独占適応性を認め得る範囲にまで絞り込むような補正の方法や商標の特定の方法(特に禁止権の範囲について出願人自らが規定できる方法)が確立されないものか。
判決中、「独占適応性」について、以下の各点を指摘して本件の独占適応性を否定している。
ア 油圧ショベルは,様々な作業を行うことができる多様性を有し,その用途に汎用性があるため,建設業において広く用いられているほか,農業や林業にも利用されており,油圧ショベルの需要者には,建設業者,建設機械を取り扱う販売業者及びリース業者のみならず,農業従事者及び林業従事者等も含まれること,
イ 本願商標の色彩と同系色の「橙」色(マンセル値:5YR6.5/14)は,人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火,健康上有害な情報並びに緊急避難を目的として規格化された「JIS安全色」の一つであり,ヘルメッ
ト,レインスーツ,サイトウェア,ガードフェンス等にオレンジ色が使用され,オレンジ色は,工事現場で一般に使用されている色彩であること,
ウ 原告以外の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧ショベルを販売していたこと,
エ オレンジ色は,黄色と赤色の中間色であって,基本色の一つであることから,オレンジ色の色彩名から観念される色の幅は広いものである上,人の視覚によって,マンセル値で特定された本願商標のオレンジ色とマンセル値の異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することには限界があり,加えて,本願商標は,色彩を付する位置を特定した,単一の色彩のみからなる商標であり,色彩を付する位置の部分の形状や輪郭に限定がないため,本願商標の商標登録が認められた場合の商標権の禁止権(商標法37条)の及ぶ範囲は広いものとなること
「ア」は、主に原告の主張①(=ショベルの参入企業は限定的である)に対するカウンター。
需要者の幅が広くなればその分混同可能性は高く評価され得る。
「イ」は、本当に3条1項3号の該当性の話なのだろうか?「JIS安全色の一つ」であるのならば、それを独占的に使用すべく登録することは公序良俗の問題ではないのか?
「ウ」について、まさに昨日言及した点(=「永年の間,他人に使用されることなく,独占的排他的に継続使用した実績を有する場合」に該当するといえるかどうかを基準として判断した」点についての審決の実体的違法性に関する主張)についての答えになっている部分。
”他人に使用されることなく”を「要件化」しているとも受け止められる。ちょっと踏み込み過ぎじゃないか?と思う。
「エ」も、出願の段階で「色彩のみからなる商標を構成する色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組み合わせ方(色彩を組合せた場合の各色の配置や割合等)等についての具体的かつ明確な説明」を記載することが求められている。「色彩の類否」という独特な議論が生まれる余地があるにはあるが、ここまで細かく規定して出願する以上、色彩については類似の幅はかなり制限的に取り扱って良いのではないかと思うがどうなのだろう?
この判決では、禁止権が及ぶ「類似の範囲」には、例えば”同系色のオレンジ色”も含まれ得る、ということを懸念している。本願の場合はさらに部分の形状や輪郭に限定がないから禁止権の範囲が著しく広くなるとしている。
でも、出願人は果たしてそこまでの「禁止権」を欲しているのだろうか?
本件の出願人は、というのと、広く一般的「色彩のみからなる商標」を出願する人は、という2つの意味で疑問。
制度として禁止権の範囲を自ら限定的にすることで権利化可能性を高めることができる仕組みがあっても良さそうに思う。包袋禁反言でもよいけど。
今のままでは、出願しても登録の見込みは極めて低く、使い勝手の良くない制度になってしまう。独占適応性を認め得る範囲にまで絞り込むような補正の方法や商標の特定の方法(特に禁止権の範囲について出願人自らが規定できる方法)が確立されないものか。