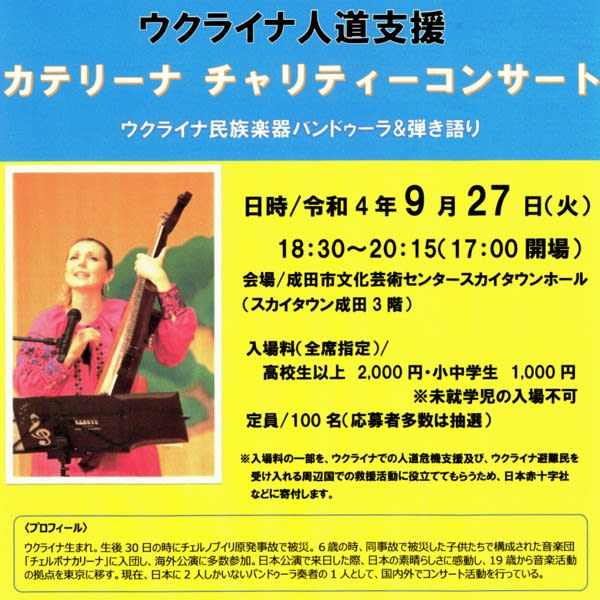「初詣」の帰りに、成田駅前の「スカイタウンギャラリー」で《 市川團十郎 歌舞伎浮世絵展 》を観て来ました。55点の作品は見応えがありました。殆どが九代目「市川團十郎」が描かれたものでした。特に明記していない作品は九代目「市川團十郎」です。
「祐天上人」は師僧「檀通上人」から暗愚のため経文が覚えられず破門され、1649年(慶安2年)に「成田山新勝寺」で参籠修行しました。その時に、夢の中で「不動明王」より剣を喉に差し入れられて明智を授かり、呪術的な能力を持ったとされています。後に「増上寺」の第36世法主となり、目黒区の「祐天寺」を開山しました。
【押隈】は初代・二代目「市川團十郎」が考案しました。 俳優の「隈取」を役が終わってから、布または紙を顔へ押しあてて写しとったもの。ひいき客の注文に応じてとることが多いそうです。実際に行なわれたのは九代目「市川團十郎」からで、それ以前のものは残されていません。尚、十代目「市川海老蔵」は後の十二代目「市川團十郎」になります。
パンフレット / 【明治座新狂言 不動霊験之場】 -「成田山新勝寺」に伝わる「祐天上人」の物語-
【新版 成田山参詣図】 -成田山参詣の市川家一門- 中央は七代目「市川團十郎」とその子の八代目
【奈智瀧祈誓文覚】 -「不動明王」と「文覚上人」の物語- 「市川團十郎」の2役
【歌舞伎十八番】 「暫」(しばらく) / 「矢ノ根」 / 「鎌髭」(かまひげ)
【歌舞伎座新狂言 勧進帳】 -「義経」と「弁慶」の奥州への逃避行の物語- 「市川團十郎」は「弁慶」役
【義経千本桜】 -「義経」と「知盛」、悲しき2人のヒーロー物語- 「市川團十郎」は「平知盛」役
【実録忠臣蔵】 -赤穂事件・歌舞伎版- 「市川團十郎」は「大石内蔵助」役
【高貴演劇遊覧図】 -明治20年の天覧歌舞伎- 演目は「勧進帳」
【押隈】十代目市川團十郎「暫」 / 十代目市川海老蔵「大根左衛門」 / 十二代目市川團十郎「雨の五郎」