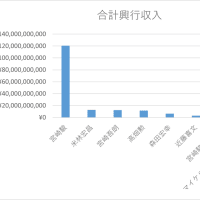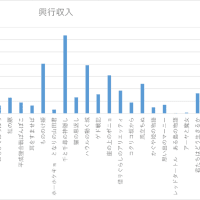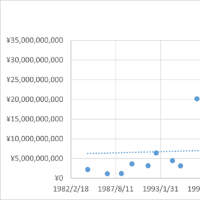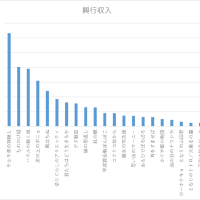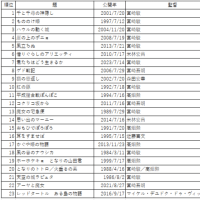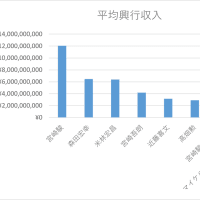僕は義務教育が嫌いだった。
訳の分からないことを、覚えろだとか、考えろとか、全くできない子だった。
でも、芸術と工作とコンピューターが好きだったので、それだけは他のことそっちのけでやり続けた。
でも金がないので、全部自作。
例えば、アパートの一室に新聞紙を敷きつめて、張り合わせ、巨大な折り鶴を作ったり、タミヤのプラバンを切ったり折ったり曲げたりして、ジープ作ったり、自分でゲームを作って遊んでいた。
中学ぐらいになると、三次元グラフィックに興味を持ち始める。
XYZの3次元画像。拡大縮小は画像深度で平面画像座標を割ればよい。
3次元座標を回転させる方程式を、どこからか見つけて、BASICであっても、「おーそーいー。」と思いながら、グリグリ回していた記憶がある。
では3次元座標の回転移動の連立方程式は、私の場合大学2年で習った。
でも、それ以外の英語やら漢字やら歴史地理なんかは、全くできなかった。
今でも掛け算九九は、うろ覚え。
7と9の段は、かなり怪しい。
そんなわけで、工業高校に進み、ものを加工する実習をやり始めた途端、知的好奇心が沸騰した。
旋盤で金属を円形に削る。
金属の種類によって、周回転速度、切れ角、逃げ角、切り込み深さ、様々な要素で仕上がりの部品の美しさが変わる。
しかも同じ金属でも、焼き入れ、焼きなましなどによって、面芯立方、などの組織形状によって性質が変わってくる。
それを知るのが楽しくて、どんどん勉強していった。
いつの間にかテストの平均点が、100点を超えて、首席になっていた。工業高校で先生がサービスして、150点満点にしたせい。
大学で99点が平均になったかな?
自分の身近な人たちを見渡しても、自分が興味を持ったら、時間も労力も惜しまない。
ある人は、200ぐらいある人体の筋肉の名前を、すべて暗記している。
またある人は、中学時代に光学レンズ式プラネタリウムを作っている。
亡くなってしまわれたが、東大理三に進んだ人は、授業の時に、教科書もノートも持っていかない。
弔辞の時、学友が、
「君はある日、私にメモを渡したね。私はそれをテストのヤマと勘違いして、散々な目にあった。後で君に聞いたら、『ああ、それはまだ僕が覚えていない場所だよ。』と答えた。」
つまり、授業で習う内容は、それ以前に全部理解していて、授業には出席と質問するためだけに出ていたと推察される。
盆に故郷に帰ったら、しばらく会ってなかった子供たちがいたので、
「義務教育を受けていると思っているうちは意味ないよ。」
と言ったら、祖母に当たる人が、
「ダメだよ、そんなこと言っちゃ。」
とたしなめた。
勉強させられていると思っているうちは、身につかないんだ。
何か目的があって、それを成し遂げるために、人は学習する。
例えば僕は、小学生の頃、
「一、十、百、千、万、億、兆、京、…那由他、不可思議、無量大数」
を、ソラで言えるように覚えていた。
今は怪しい。
全く小学生では覚える必要のないことだが、僕は単純に、
「数はどこまであるんだろう?」
という好奇心で覚えた。
福島原発事故の際、
「これから何京、何億京Bqの放射能が漏れ出すか分からない!」
と、ツイッターでつぶやいていた人がいたので、
「いやいや、それは万万法で、京の次はガイですから。」
とRTしたが、無視された。
「知ることが楽しい。」
と思えない限り、何も身につかない。
今だって新しい発見、常識が生まれている。
応急処置も、心停止の場合は、心臓マッサージよりも、AERの方が良いとされている。
昔は怪我をしたら、赤チンと脱脂綿だったが、それでは再生細胞組織を殺してしまうので、最小限の消毒で、静脈損傷ならラップを巻いたほうがいい。
日常の常識さえも変わるのだから、生涯学習なのである。
親「勉強しろ!」
子「なんで?」
親「それが子供の仕事だからだ!」
という論法で、子供が勉強するか?
僕だったらしない。というかしなかった。
何かをやり遂げるには、知識という道具が必要。
人間の最大の発明は、文化文明であると思う。
現実を知り、対応する力こそ、教育の本質だと思う。
それが根底にないままで、どんな一流大学を卒業したって、何もできない。
教育はアシスト。それに頼ってちゃいけない。
1年生が3年生のことを知っていても、おかしくない。
中学のある日、全く勉強せずに、数学の全国模試で100点をとってしまった。
クラスのリーダー的な友人に話したら、
「嘘つけ。ありえない。」
いや、現実としてあるんだけど。
学ぶとは何か。
教育とは何かのヒントになれば幸い。
好きこそものの上手なれ。
訳の分からないことを、覚えろだとか、考えろとか、全くできない子だった。
でも、芸術と工作とコンピューターが好きだったので、それだけは他のことそっちのけでやり続けた。
でも金がないので、全部自作。
例えば、アパートの一室に新聞紙を敷きつめて、張り合わせ、巨大な折り鶴を作ったり、タミヤのプラバンを切ったり折ったり曲げたりして、ジープ作ったり、自分でゲームを作って遊んでいた。
中学ぐらいになると、三次元グラフィックに興味を持ち始める。
XYZの3次元画像。拡大縮小は画像深度で平面画像座標を割ればよい。
3次元座標を回転させる方程式を、どこからか見つけて、BASICであっても、「おーそーいー。」と思いながら、グリグリ回していた記憶がある。
では3次元座標の回転移動の連立方程式は、私の場合大学2年で習った。
でも、それ以外の英語やら漢字やら歴史地理なんかは、全くできなかった。
今でも掛け算九九は、うろ覚え。
7と9の段は、かなり怪しい。
そんなわけで、工業高校に進み、ものを加工する実習をやり始めた途端、知的好奇心が沸騰した。
旋盤で金属を円形に削る。
金属の種類によって、周回転速度、切れ角、逃げ角、切り込み深さ、様々な要素で仕上がりの部品の美しさが変わる。
しかも同じ金属でも、焼き入れ、焼きなましなどによって、面芯立方、などの組織形状によって性質が変わってくる。
それを知るのが楽しくて、どんどん勉強していった。
いつの間にかテストの平均点が、100点を超えて、首席になっていた。工業高校で先生がサービスして、150点満点にしたせい。
大学で99点が平均になったかな?
自分の身近な人たちを見渡しても、自分が興味を持ったら、時間も労力も惜しまない。
ある人は、200ぐらいある人体の筋肉の名前を、すべて暗記している。
またある人は、中学時代に光学レンズ式プラネタリウムを作っている。
亡くなってしまわれたが、東大理三に進んだ人は、授業の時に、教科書もノートも持っていかない。
弔辞の時、学友が、
「君はある日、私にメモを渡したね。私はそれをテストのヤマと勘違いして、散々な目にあった。後で君に聞いたら、『ああ、それはまだ僕が覚えていない場所だよ。』と答えた。」
つまり、授業で習う内容は、それ以前に全部理解していて、授業には出席と質問するためだけに出ていたと推察される。
盆に故郷に帰ったら、しばらく会ってなかった子供たちがいたので、
「義務教育を受けていると思っているうちは意味ないよ。」
と言ったら、祖母に当たる人が、
「ダメだよ、そんなこと言っちゃ。」
とたしなめた。
勉強させられていると思っているうちは、身につかないんだ。
何か目的があって、それを成し遂げるために、人は学習する。
例えば僕は、小学生の頃、
「一、十、百、千、万、億、兆、京、…那由他、不可思議、無量大数」
を、ソラで言えるように覚えていた。
今は怪しい。
全く小学生では覚える必要のないことだが、僕は単純に、
「数はどこまであるんだろう?」
という好奇心で覚えた。
福島原発事故の際、
「これから何京、何億京Bqの放射能が漏れ出すか分からない!」
と、ツイッターでつぶやいていた人がいたので、
「いやいや、それは万万法で、京の次はガイですから。」
とRTしたが、無視された。
「知ることが楽しい。」
と思えない限り、何も身につかない。
今だって新しい発見、常識が生まれている。
応急処置も、心停止の場合は、心臓マッサージよりも、AERの方が良いとされている。
昔は怪我をしたら、赤チンと脱脂綿だったが、それでは再生細胞組織を殺してしまうので、最小限の消毒で、静脈損傷ならラップを巻いたほうがいい。
日常の常識さえも変わるのだから、生涯学習なのである。
親「勉強しろ!」
子「なんで?」
親「それが子供の仕事だからだ!」
という論法で、子供が勉強するか?
僕だったらしない。というかしなかった。
何かをやり遂げるには、知識という道具が必要。
人間の最大の発明は、文化文明であると思う。
現実を知り、対応する力こそ、教育の本質だと思う。
それが根底にないままで、どんな一流大学を卒業したって、何もできない。
教育はアシスト。それに頼ってちゃいけない。
1年生が3年生のことを知っていても、おかしくない。
中学のある日、全く勉強せずに、数学の全国模試で100点をとってしまった。
クラスのリーダー的な友人に話したら、
「嘘つけ。ありえない。」
いや、現実としてあるんだけど。
学ぶとは何か。
教育とは何かのヒントになれば幸い。
好きこそものの上手なれ。