ここで暖炉のイメージを絵にしてみる。
何度もイメージは更新させれると思うが、直感で書き留めておくことは、
もの作りの基本と思う。
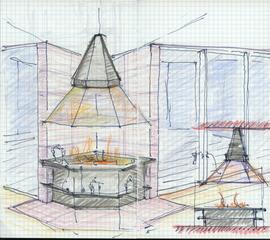
メモ57
鋼とガラスのコラボレーション・・・・?
開放型の暖炉なので、<臭い><音>に関しては、十分<癒し>を
堪能できるだろう!
安全を確保しながら、<見る楽しみ>を満足させるために、耐火ガラスのシェードを
付ける様にした。
後ろの壁部分を熱から十分守るために、鋼の囲いを立ち上げるか・・・?
だんだんストーブ的になってくる。囲炉裏の雰囲気は薄れる。
耐熱的な建材で壁を作る方法は・・・
耐火煉瓦・・・
抗火石・・・
不燃材・・・
燃焼面は床から50センチは上げたい。
椅子に座って見る炎の高さは、床面では低すぎる。
火元の面積がそれほど大きくは取れないので、
効果的な位置を計算する必要がある。
何度もイメージは更新させれると思うが、直感で書き留めておくことは、
もの作りの基本と思う。
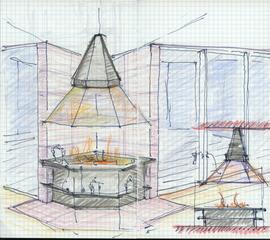
メモ57
鋼とガラスのコラボレーション・・・・?
開放型の暖炉なので、<臭い><音>に関しては、十分<癒し>を
堪能できるだろう!
安全を確保しながら、<見る楽しみ>を満足させるために、耐火ガラスのシェードを
付ける様にした。
後ろの壁部分を熱から十分守るために、鋼の囲いを立ち上げるか・・・?
だんだんストーブ的になってくる。囲炉裏の雰囲気は薄れる。
耐熱的な建材で壁を作る方法は・・・
耐火煉瓦・・・
抗火石・・・
不燃材・・・
燃焼面は床から50センチは上げたい。
椅子に座って見る炎の高さは、床面では低すぎる。
火元の面積がそれほど大きくは取れないので、
効果的な位置を計算する必要がある。
暖炉・・・“炎に求めるものは?・・・”を考えていたら、
想いが<囲炉裏>に発展した。
癒しの根源を<炎>とすれば、そこから受ける情報・・・
<色>
<臭い>
<音>
<暖気>
これらのものが、直接感じられなければならない。
<利便性> <安全性>・・・これらのことを配慮すると、
ストーブのような密閉された空間の中で、<熱>だけを効率的に取り出す機器が考えられる。
技術・文明は時にして、大切な一面を切り落とす。
効率・技術では補い得ない<何か>。
人類のDNAに組み込まれた、<輪になって火を取り囲む>原始社会からの
習慣。
これは囲炉裏を囲む日本人の原風景に重なる。
囲炉裏の空間こそ、<炎>に求める風景かもしれない。
加えて配慮しなければならない<安全性><機能性>を考えれば、
新たな囲炉裏空間が、想像できる。
今は<耐火ガラス・耐熱ガラス>等、火を囲う材料は色々ある。
<臭い><色><音>を切り捨てることなく、<炎の癒し>を
手に入れる。
何かできそうな気がする。
想いが<囲炉裏>に発展した。
癒しの根源を<炎>とすれば、そこから受ける情報・・・
<色>
<臭い>
<音>
<暖気>
これらのものが、直接感じられなければならない。
<利便性> <安全性>・・・これらのことを配慮すると、
ストーブのような密閉された空間の中で、<熱>だけを効率的に取り出す機器が考えられる。
技術・文明は時にして、大切な一面を切り落とす。
効率・技術では補い得ない<何か>。
人類のDNAに組み込まれた、<輪になって火を取り囲む>原始社会からの
習慣。
これは囲炉裏を囲む日本人の原風景に重なる。
囲炉裏の空間こそ、<炎>に求める風景かもしれない。
加えて配慮しなければならない<安全性><機能性>を考えれば、
新たな囲炉裏空間が、想像できる。
今は<耐火ガラス・耐熱ガラス>等、火を囲う材料は色々ある。
<臭い><色><音>を切り捨てることなく、<炎の癒し>を
手に入れる。
何かできそうな気がする。
薪ストーブの写真と、仕組みの図面を入手。
資料が小さくて見難いと思うが、上部に四種類の薪ストーブ・・・下段にストーブの切断図を載せる。

メモ57
構造の大まかなイメージは、薪を燃やす燃焼室と、それを取り巻く
空気を暖める通気空間からできている。
部屋内の空気を、燃焼室の周囲を通過させることによって暖め、
温まった空気を再び部屋に送り返す。
空気は汚れず、温度だけが上がる。薪から出る二酸化炭素と臭気は煙突を介して、
外へ廃棄する。
熱交換だけが合理的に完結する。外に廃棄してしまう暖気を、どれだけ部屋内に還元できるかは、
ストーブメーカーのノウハウだろう。
こうしてみると、ストーブのマイナス点も見えてくる。
薪がパチパチと燃えるときに発する<音>が聞こえるだろうか・・・?
薪が燃えるときに発する<臭い>が臭うだろうか・・・?
何れも多少は期待できる。
暖炉もしくはストーブに求める<癒しの原点>を何に置くか・・・・
<機能と効果>の鬩ぎ合いを、検討していこう!
資料が小さくて見難いと思うが、上部に四種類の薪ストーブ・・・下段にストーブの切断図を載せる。

メモ57
構造の大まかなイメージは、薪を燃やす燃焼室と、それを取り巻く
空気を暖める通気空間からできている。
部屋内の空気を、燃焼室の周囲を通過させることによって暖め、
温まった空気を再び部屋に送り返す。
空気は汚れず、温度だけが上がる。薪から出る二酸化炭素と臭気は煙突を介して、
外へ廃棄する。
熱交換だけが合理的に完結する。外に廃棄してしまう暖気を、どれだけ部屋内に還元できるかは、
ストーブメーカーのノウハウだろう。
こうしてみると、ストーブのマイナス点も見えてくる。
薪がパチパチと燃えるときに発する<音>が聞こえるだろうか・・・?
薪が燃えるときに発する<臭い>が臭うだろうか・・・?
何れも多少は期待できる。
暖炉もしくはストーブに求める<癒しの原点>を何に置くか・・・・
<機能と効果>の鬩ぎ合いを、検討していこう!












