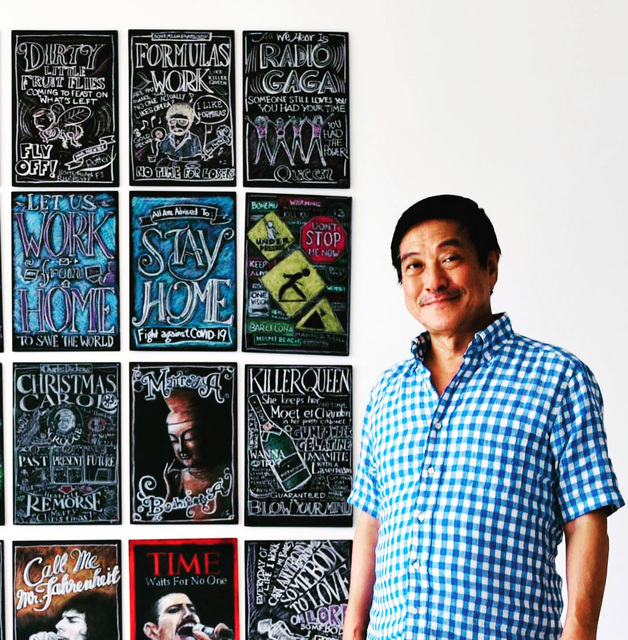5月11日時点での日本の新型コロナでの死亡者は621人。日本のテレビでは、死者数を「こんなに低く抑えられている」と報道しています。しかし「低い」というのは、アメリカやヨーロッパに比較しての話。亡くなった人のことを思えば、この人数を少ないとは決して言えません。この数の中に、志村けんさんとか、岡江久美子さんなども含まれていますが、日本の高度な医療体制をもってして、どうして、こんなに多くの人々の命を救えなかったのかと疑問を感じます。
私は今、シンガポールに住んでいるのですが、日本のテレビでは「優等生と言われていたシンガポールが急に感染者数を伸ばしていて、中国に次いでアジア最悪の国になった」というのが最近の決まり文句となっています。シンガポールでは、バングラデシュなどの外国人労働者が大量に働いているのですが、彼らはいくつかの寮で集団生活をしていて、そこでの感染が広がり、毎日数百人規模での感染者が出ています。しかし、一般シンガポール人の市中感染は、ほぼ一桁に抑えられています。
そして、シンガポールでの新型コロナでの死者数は、現時点で累積で20人です。シンガポールでは医療崩壊の心配はなく、何としても命を守るよう、全力を尽くしています。これに比べてみると、日本の死者数は、何と多く見えることでしょう。日本は、感染拡大の数字だけを見て、シンガポールを見下しているのですが、命をどれだけ守れたかという数字で見てほしいと思います。
自分は専門家ではないので、中途半端にこういうことを書くと、いろいろお叱りを受けるかもしれないのですが、日本の死者数を眺めていると、重症化する前に、もっと早めに治療できていたら、あるいはその前に、感染者との接触を避けられていたら、命をなくす事もなかった人が多くいたのではと思うのです。
ヨーロッパに比べると、アジアは相対的に死者数が少ないのですが、アジア・パシフィックの国々で比較してみると、日本より死者数が多い国は、中国、インド、フィリピン、インドネシアくらいで、韓国も、台湾も、マレーシアも、タイも、ミャンマーも、オーストラリアも、ニュージーランドも日本よりはるかに少ない数です。
たまたま仕事の関係で、バングラデシュのデータを調べていたのですが、WHOのサイトを見ていたら、バングラデシュは、感染状況のレポートをかなり詳細に開示しているんですね。
COVID-19 Situation Report No. 10
PCRテストをどれだけやって、感染者数がどれだけいるか、何人退院したか、何人亡くなったか、などがきちんと出ています。日本の同様のレポートをWHOのサイトで探そうとしたんですが、日本のは残念ながら見つかりませんでした。
この中で、CFRという数字のことを初めて知りました。Case Fatality Rateの略なのですが、感染者のうち何人が死に至ったのかをパーセントで示す数字です。日本語では「致死率」というようですが、バングラデシュでは、5月4日時点で、これが1.79%。日本は、5月11日時点の数字で、3.93%。バングラデシュの2倍以上です。シンガポールは0.09%。日本は、PCR検査の数が少ないので、潜在感染者がかなりいるのだと思いますが、致死率に関して、現状ではバングラデシュにも負けています。

こちらのグラフは、縦軸が死者数、横軸が感染者数で国別にプロットしたものですが、斜めの点線がCFRを示しています。これをみると、日本のCFRの数値は決して低くはないというのがわかります。ヨーロッパ諸国は、感染者数も死者数も高いですが、CFRも高いレベルです。アメリカはずば抜けて感染者数、死者数が多いですが、CFRは日本と同レベルです。アジアの大半の国は日本よりも低いレベルです。シンガポールの優秀さが際立っていますね。このデータはこちらのサイトから引用させていただきました。
Current Case Fatality Rate
日本としては、今後、PCR検査を増やして、無症状の感染者を洗い出し、感染拡大を防ぎ、その一方で患者の命を徹底的に守っていくということが重要です。ハイリスクの高齢者とか、病気療養中の方には、絶対に感染させないという対応も重要です。コロナと共に生きるということをしばらくは継続させないといけないのでしょうが、コロナで亡くなる可能性のある命を、少しでも救っていただきたい、そして私たちは、感染が広がらないよう最大限協力をしていければと思います。
私は今、シンガポールに住んでいるのですが、日本のテレビでは「優等生と言われていたシンガポールが急に感染者数を伸ばしていて、中国に次いでアジア最悪の国になった」というのが最近の決まり文句となっています。シンガポールでは、バングラデシュなどの外国人労働者が大量に働いているのですが、彼らはいくつかの寮で集団生活をしていて、そこでの感染が広がり、毎日数百人規模での感染者が出ています。しかし、一般シンガポール人の市中感染は、ほぼ一桁に抑えられています。
そして、シンガポールでの新型コロナでの死者数は、現時点で累積で20人です。シンガポールでは医療崩壊の心配はなく、何としても命を守るよう、全力を尽くしています。これに比べてみると、日本の死者数は、何と多く見えることでしょう。日本は、感染拡大の数字だけを見て、シンガポールを見下しているのですが、命をどれだけ守れたかという数字で見てほしいと思います。
自分は専門家ではないので、中途半端にこういうことを書くと、いろいろお叱りを受けるかもしれないのですが、日本の死者数を眺めていると、重症化する前に、もっと早めに治療できていたら、あるいはその前に、感染者との接触を避けられていたら、命をなくす事もなかった人が多くいたのではと思うのです。
ヨーロッパに比べると、アジアは相対的に死者数が少ないのですが、アジア・パシフィックの国々で比較してみると、日本より死者数が多い国は、中国、インド、フィリピン、インドネシアくらいで、韓国も、台湾も、マレーシアも、タイも、ミャンマーも、オーストラリアも、ニュージーランドも日本よりはるかに少ない数です。
たまたま仕事の関係で、バングラデシュのデータを調べていたのですが、WHOのサイトを見ていたら、バングラデシュは、感染状況のレポートをかなり詳細に開示しているんですね。
COVID-19 Situation Report No. 10
PCRテストをどれだけやって、感染者数がどれだけいるか、何人退院したか、何人亡くなったか、などがきちんと出ています。日本の同様のレポートをWHOのサイトで探そうとしたんですが、日本のは残念ながら見つかりませんでした。
この中で、CFRという数字のことを初めて知りました。Case Fatality Rateの略なのですが、感染者のうち何人が死に至ったのかをパーセントで示す数字です。日本語では「致死率」というようですが、バングラデシュでは、5月4日時点で、これが1.79%。日本は、5月11日時点の数字で、3.93%。バングラデシュの2倍以上です。シンガポールは0.09%。日本は、PCR検査の数が少ないので、潜在感染者がかなりいるのだと思いますが、致死率に関して、現状ではバングラデシュにも負けています。

こちらのグラフは、縦軸が死者数、横軸が感染者数で国別にプロットしたものですが、斜めの点線がCFRを示しています。これをみると、日本のCFRの数値は決して低くはないというのがわかります。ヨーロッパ諸国は、感染者数も死者数も高いですが、CFRも高いレベルです。アメリカはずば抜けて感染者数、死者数が多いですが、CFRは日本と同レベルです。アジアの大半の国は日本よりも低いレベルです。シンガポールの優秀さが際立っていますね。このデータはこちらのサイトから引用させていただきました。
Current Case Fatality Rate
日本としては、今後、PCR検査を増やして、無症状の感染者を洗い出し、感染拡大を防ぎ、その一方で患者の命を徹底的に守っていくということが重要です。ハイリスクの高齢者とか、病気療養中の方には、絶対に感染させないという対応も重要です。コロナと共に生きるということをしばらくは継続させないといけないのでしょうが、コロナで亡くなる可能性のある命を、少しでも救っていただきたい、そして私たちは、感染が広がらないよう最大限協力をしていければと思います。