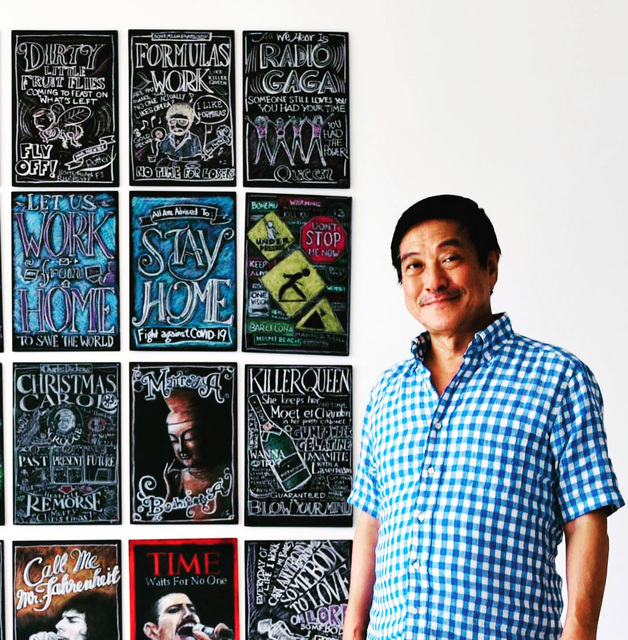シンガポールに「オンランサロン川端会議」という勉強会があり、月に2回ほど夕方オンラインのセミナー形式で開催されている会なのですが、2021年10月5日のテーマは、小川さやか著『チョンキンマンションのボスは知っている』という本から得たインスピレーションをもとに議論をするというものでした。
香港にある重慶大厦(チョンキンマンション)の話、そこでのタンザニア人のコミュニティのネットワーク構築の方法、信頼関係の話、また文化人類学的視点という、じつにファジーで、ごった煮的なテーマでした。チョンキンマンション自体がカオスなのですが、それに伴いこの議論もラビリンスの中を彷徨うような、知的脱出ゲームをしているような(?)経験となりました。
ここでの議論の出発点になった、香港のチョンキンマンションに関して、4年間香港に住んでいて、その後も数年間、時々訪れていた私としては、非常に思い入れがあり、懐かしく、語りたいことがいっぱいなので、この機会に語ってみたいと思いました。
チョンキンマンションのことを語るまえに、まず、きっかけとなった『オンラインサロン川端会議』のことをご説明しておきたいと思います。
私は、このオンラインサロンには、2020年の10月のスタート時から参加させていただいています。ASEANやアジアの様々な情報を、月に2度ほど、議長の川端隆史さん(元外交官、NewsPicsを経て、現在米国リスクコンサルティングファームのクロールのシンガポール支社のシニアバイスプレジデント)が、いろいろな切り口で、独自の視点で報告してくれる会です。
参加メンバーはシンガポールにいる人だけでなく、日本や、中国や、タイで仕事している方も何人かいます。たとえアジアの中にいても、刻々と変化するアジアの動きは捉えにくいので、こういうところでアジア情報を、マクロxミクロの視点でキャッチアップしていく必要があると感じて、この会に参加させていただいています。興味のある方はこちらをご覧ください。
https://www.oneandco.sg/ja/community/kawabatakaigi/
日本のマスコミの情報では報道されない情報や、視点を提供してくれるので、個人的にはとても楽しんでいます。前回は、元NHKのインド支局長だった広瀬公巳さんをゲストにお招きし、米印関係の歴史的整理をしていただき、またアフガニスタンに対するインドの関わりに関してまとめていただきました。目から鱗のことばかりで、インドの政治的な立ち位置を把握する上では非常に役立ちました。
前置きが長くなりましたが、本題のチョンキンマンションに関して語ってみたいと思います。
川端会議で取り上げられたのは、小川さやかさんの『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』という本です。
小川さやかさんは、学者として、香港のタンザニア人ネットワークに、チョンキンマンションのボスと呼ばれるタンザニア人を介して潜入調査をしていき、ファジーな信頼をベースにしたインフルエンサー経済、インフォーマル経済、「ついで」経済などの存在を確認していきます。
小川さんは、アフリカの専門家なので、タンザニア人コミュニティーに着目し、香港のチョンキンマンションにアプローチしていきます。いきなり脱線して恐縮ですが、タンザニアといえば、今年のノーベル文学賞は、タンザニア出身の作家、アブドゥルラザク・グルナさんが受賞しました。グルナさんは1948年生まれ。インド洋のザンジバル島で育ち、60年代末に難民として英国に渡り、21歳の時に亡命者の立場で執筆活動を始め、母国語のスワヒリ語ではなく英語を用いたのだそうです。これまで発表した作品の底流にあるのは、難民の混乱というテーマということです。
タンザニアは、アフリカ東岸で、ケニアの南にある国ですが、タンガニーカとザンジバルという二つの国が併合して出来た国です。現在でも正式国名はタンザニア連合共和国(United Republic of Tanzania)となっています。もともとはイギリスの植民地だった地域ですが、タンザニアとなったのは1964年の4月。最初の東京オリンピックの年です。オリンピックには、タンザニアではなく、タンガニーカとして参加していました。
ノーベル文学賞を受賞したグルナさんは、ザンジバル出身ということですが、ザンジバル出身で世界的な有名人といえば、クィーンのフレディ・マーキュリー。映画『ボヘミアン・ラプソディ』の中でも、ザンジバルの革命の中で、家族は命からがら難民となって生き延びたという過去が語られるシーンがあります。調べてみると、フレディ・マーキュリーが生まれたのは1946年、小説家のグルナさんが生まれたのは1948年。ほぼ同じ頃です。フレディ・マーキュリーもグルナさんも同じ時代、同じ場所で、困難を同時体験していたというのを考えると感慨深いです。
おそらく同じように難民となったザンジバル出身のタンザニア人が香港のチョンキンマンションのネットワークにも数多くいたのではないかと推測されるのですが、タンザニアというこれまであまり注目してこなかった国が急に身近に感じられます。小川さやかさんの本にも出てくる「チョンキンマンションのボス」と呼ばれるカラマという人物も、「ザンジバル出身のオマーン系アラブ人の父と、アフリカ系ザラモ人の母との間に生まれ、35歳の時、天然石ビジネスのため香港にやってきた」
ということだそうです。
で、いよいよ、本題のチョンキンマンションのことに関して語りたいと思います。私自身は、2007年から4年間香港に住んでいて、その後も東京の広告代理店の香港現地法人の責任者を続けていたので、3ヶ月に一度くらい香港に通っておりました。
仕事で、インドの広告キャンペーンにも関わっていて、インドの映画やエンタメに関していろいろ調べていたので、チョンキンマンションにあるインド系のDVDショップにはよく通っていました。他の国ではなかなか入手できないインド映画が、最新ヒット作も、マイナーなものも含めてほぼ揃っているのです。ここで毎回かなりの数のDVDを買い付けていたのですが、インド映画は、3時間、4時間と長いのが多く、買ったはいいけどなかなか見る時間がないという状況でした。
チョンキンマンションは、中国語では重慶大厦と漢字表記になっていますが、北京語ではChóngqìng dàshà (チョンチン ダーシャー)という発音になりますが、広東語ではチョンヘン ダーイハーという音になります。英語では、Chungking Mansions となります。
香港の九龍側のネイザンロードという観光地として有名な通りに面して立つ16、7階建てのビルなのですが、1961年にできたもので、一等地にありながら、上の階には安宿が数多くあり、入り口付近には両替屋がひしめき、地上階とその上の階にはインド人経営する携帯電話、DVD、食材、雑貨、レストランなどのお店が雑多にあるカオスな世界です。
ここ数年行っていないので、最近の状況はわかりませんが、コロナ禍で旅行者が激減しているので、両替や、宿泊もかなり影響を受けているものと思われます。
私自身は、チョンキンマンションは、インド人のネットワークの拠点と認識していました。地上階とその上の階は、ほとんどインド系のお店ばかりでした。インド料理屋にもいくつか行って食事したことがありました。
たまたま、私は、2012年に、日経リサーチのサイトで「世界の街角ライブラリー」という小コラムを連載していたことがあるのですが、そこで、チョンキンマンションとインド人ネットワークのことにちょっと触れていましたのでこちらにリンクを貼っておきます。
世界に張りめぐらされたインド人ネットワーク
日経リサーチ グローバル・マーケティング・キャンパス
この記事の中でも触れていますが、映画『恋する惑星』(原題“Chungking Express”)という作品があります。金城武や、フェイ・ウォン、トニー・レオンなどが出演していますが、この中で、チョンキンマンションの場面も登場するのですが、疾走するカメラワークが斬新でかなりの衝撃を受けたことを覚えています。
こちらがその映画のトレーラーです。
VIDEO
また、チョンキンマンションは沢木耕太郎さんの『深夜特急』でも登場してきていて、80年代後半に発表されたこの作品によって、チョンキンマンションはバックパッカーの聖地にもなりました。
何年か前に、CP+というカメラ関係の展示会で、沢木耕太郎さんがニコンブースで講演されたことがあり、たまたまお話を伺ったことがありました。その頃、写真家のキャパに関する本を出されたので、その話がメインでしたが、考え方も、佇まいもすごくかっこよかった印象があります。
香港は1997年に英国から中国に返還され、中国でありながら中国とは一線を画し、通貨も、パスポートも、言語も、文字も違う特別行政区という位置付けで自由を謳歌してきたのですが、年々強まる中国政府の圧力で、ここ数年は自由が次々と剥奪されていくという歴史でした。
2014年の雨傘運動の時にも、香港に行きましたが、高速道路を埋め尽くした学生たちのテントを見て、まさに「レミゼラブル」の光景と同じだなと感じたものでした。「学民の女神」として民主化運動でも活躍した周庭(アグネス・チョウ)さんは2020年に刑務所に収監され、その後釈放されましたが、りんご日報の廃刊などとともに、香港の自由がどんどん磨り減っていくという歴史を私たちは目撃してきました。
『チョンキンマンションのボスは知っている』の著者の小川さやかさんが香港に滞在して、チョンキンマンションの取材をしたのは、2016年10月からの半年間。香港は雨傘運動が終わり、立法会議員選挙が行われ、民主派の議員たちがまだ自由を取り戻すことを夢見て頑張っていた時代です。おそらくその頃もチョンキンマンションは昔ながらの、自由な香港の中にあって、さらに治外法権的な、なんでもありのカオス的自由を謳歌していたと思われます。
その後、2019年から2020年にかけて民主化運動とその弾圧がエスカレートし、中国政府の力が圧倒的になったと同時にコロナが訪れました。
今年の東京オリンピックで、香港の張家朗選手がフェンシングの男子フルーレ個人で金メダルを獲得した時、香港の旗が掲げられたにも関わらず、演奏された曲は中華人民共和国の国歌だったということで、香港の人々の反発を招いたという出来事がありました。香港というシステムの中に中国がどんどん入り込んできているという象徴でした。
チョンキンマンションが今、どのような状況なのかわかりませんが、無法地帯だった場所に、法律が入り込み、かつてのおおらかな自由が失われる過程にあるのか、それともアンダーグラウンドの部分を死守できているのか、その辺はなんともわかりません。中国になってしまったら、かつてのチョンキンマンションという蜃気楼のような存在も、過去の物語になってしまうのではないかと心配です。
香港には、私の同僚で、フィリピン人と結婚し、カラオケバーをやっていた人間もいて、チョンキンマンションとは別のアンダーグラウンドな世界との間で、小説に出てきそうな人生を送った日本人もいます。数年前、香港のランタウ島の自宅でおそらく酒が原因で客死したのですが、そんなのもいたり、香港島のセントラルのマンダリンホテルで自殺したレスリー・チャンのこともあったり、映画『慕情』に影響されて、香港で『慕情』という名の日本食レストランを何十年も前に始め、レスリー・チャンがよく一人で食べに来ていたと語るオヤジさんもいたり、いろんな思い出がいっぱいあります。
古きよき、自由な香港は、いつまでも無くなってほしくないですね。