朝日新聞1月11日 文化の扉「時代や社会 映す暦」が出ていました。
管理人は10年程前、市民大学講座で1年に5~6回の天文講座を5年続けて
担当していました。
ネタに困って暦や星占いについて話したところ、好評だったので、2年毎に
行いました。
国立天文台天文情センター暦計算室のサイトは暦について詳しく解説している
ので参考にしていました。


時代や社会、映す暦
日本は長く太陰太陽暦/時を支配、権力の証し
私たちの暮らしに欠かせない「暦(カレンダー)」。年の初めに、暦の歴史や世界で
使われている暦について考えてみたい。
暦の目的は、季節や昼夜を年・月・日などの単位に当てはめて、農業などを計画的に
進めることにある。そのために太陽などの天体を観測してきた。
国立天文台天文情報センターの片山真人・暦計算室長によれば、現在世界で使われて
いる暦は大きく分けて3種類。
(1)地球が太陽の周りを一周する日数(年365.242日)を基準にした
「太陽暦」。グレゴリオ暦など
(2)月の満ち欠け(月29.531日)を基準にした「太陰暦」。イスラム暦など
(3)月の満ち欠けと太陽の動きの両方を基準とし、約3年に1度のペースで閏月
を設ける「太陰太陽暦」だ。中国の宣明暦、日本の「旧暦」
紀元前3000年頃、太陽暦が生まれた古代エジプトでは、日の出の直前に
「シリウス」という星が昇る時期を観測し、ナイル川の洪水の時期を察したと
される。1年は12カ月と5日、1カ月は30日、1旬は10日で構成されて
いた。「古代エジプト暦」(太陽暦)
手を加えたのが古代ローマのユリウス・カエサルだ。紀元前45年、エジプトの
太陽暦を手本に、1年を365・25日、4年に1度の閏年を設けた。「ユリウス暦」
だが、太陽の周りを地球が一周するのは約365・24219日で、誤差が累積する
と季節と日時がずれるため、1582年にローマ教皇グレゴリオ13世が1年を
平均365・2425日とする「グレゴリオ暦」を取り入れた。
東アジアでは、古代中国で生まれたと考えられる太陰太陽暦が長年使われてきた。
日本に伝わったのは6~7世紀とみられる。奈良時代には中国・唐に留学した
吉備真備が持ち帰った「大衍暦」などが使われたが、平安時代に渤海国(中国東北
地方から朝鮮半島北部を支配)を経由して「宣明暦」が導入されると、800年
余り用いられた。
日月や星を観測し、暦を作る「暦学」は、江戸時代には幕府天文方を中心に発達する。
1685年には、渋川春海の手になる初の日本独自の暦「貞享暦」が導入され、
平安以来累積した宣明暦の誤差を修正した。
暦づくりは幕府を中心に行われたが、京都の朝廷に取り戻す動きもみられた。
中牧弘允・国立民族学博物館名誉教授(宗教人類学)は「暦の作成は権力者の
専権事項とされ、時を支配することのあかしだった。封建制に対抗し、欧州で
市民が町の広場に時計台を盛んにつくったのも同じ理由です」と話す。
暦は、それぞれの地域の歴史や文化を色濃く反映している。中牧さんによれば、
イランがイスラム国家で珍しく太陽暦を併用するのは、太陽を光の化身とみる
ゾロアスター教の影響。インドネシアのバリ島では複雑な民族構成を反映し、
1枚のカレンダーに西暦以外にも中国暦、イスラム暦、インドのサカ暦など、
複数の表記がみられる。
日本では1873(明治6)年、太陰太陽暦から太陽暦に変わった。中牧さんは
「明治政府が旧暦にあった吉凶などの暦注を迷信として排除したため、民間では
大安や仏滅などの六曜を新たな暦注とした。その結果、かえって別の吉凶を
気にするようになってしまった」と話す。(編集委員・宮代栄一)
芸術性高いものも
カレンダーメーカー・トーダン社長、強口邦雄さん
1903年に団扇や扇子を製造販売する会社として東京・日本橋で創業しましたが、
冬場にカレンダーを扱ったのがカレンダーメーカーになるきっかけでした。父の代
からカレンダーを収集し、今では数千点に上ります。欧米のものが多いのですが、
海外出張のたびに買い求めたり、オークションで競り落としたりしています。
ドイツやフランスのカレンダーは芸術性が高く、絵画とみまごうものも少なくありません。
戦前は1枚の台紙に簡単なこよみ情報と商店の広告を入れる「年表」と呼ばれる
ものを多くつくっていました。大正ごろから日めくりが増え、戦後は月ごとの
スケジュールを確認できる「月表」と呼ばれる形式が主流です。ここ20年ほどは
パソコンの普及で卓上型の出荷が増えました。カレンダーは時代と文化、暮らしを
反映しています。
<知る> 暦の研究者らも加わり、暦の文化に関する普及活動をしているのが、
日本カレンダー暦文化振興協会(東京都台東区)である。理事長を務める中牧弘允
・国立民族学博物館名誉教授の『世界をよみとく「暦」の不思議』(イースト新書Q)
は、わかりやすい入門書だ。
<見る> 暦関係の貴重な資料は、東京都三鷹市の国立天文台の天文台歴史館で
公開している。ただし、現在はコロナウイルスの感染拡大のため閉鎖している。
過去の展示のウェブはhttps://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/index.html
別ウインドウで開きます。










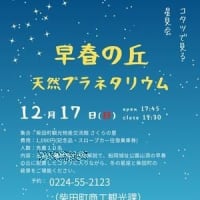










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます