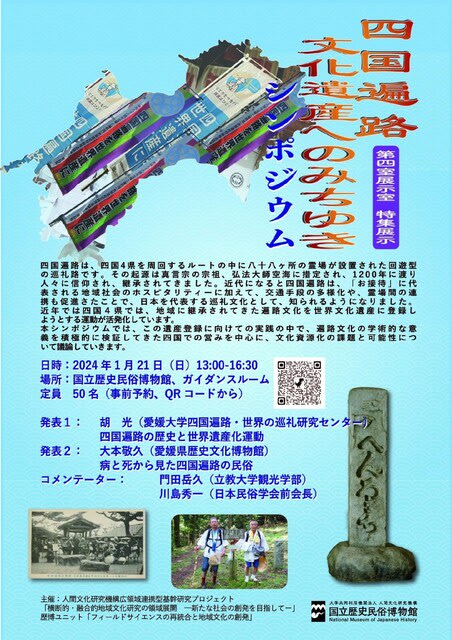四国遍路世界遺産登録推進協議会(事務局は香川県庁)の「普遍的価値の証明」部会では、四国遍路の世界遺産登録に必要となる「顕著な普遍的価値」の検討を進めるため、四国4県の大学、博物館等の専門家で構成する四国遍路関係資料調査研究会を設置し、令和3年度から5年度にかけて調査研究等を行い、その成果として『四国遍路関係史料集-古代・中世編-』が刊行されました。
私もこの3年間、四国遍路に関係する古代史・古代文学分野を担当し、調査を進めてきました。事前の文献調査や執筆にかかる時間、編集に関わる作業など、時間的にも精神的にも私がこれまで経験したことのない、かなりの負担量となりましたが無事に刊行されて安堵しているところです(おかげさまでこの仕事で体重もかなり落とすことができました。執筆、編集時のことは過去のこと。思い出さず、忘却の彼方へ・・・)。
これまでの四国遍路研究では活字本や校訂本を引用する形で調査、研究、史料解釈等が行われる傾向にありましたが、今回の調査研究会ではできるだけ原史料を確認の上、再解釈するという立場で調査、執筆、編集を進めてきたところです。特に古代史・古代文学分野では「校訂」前の原文、そして現代語訳(意訳)を掲載することにより、今後の四国遍路研究への基礎データを提示できたのではないかと考えています。
この史料集の編集は、愛媛県庁のまなび推進課が事務局となって行われたものです。まなび推進課のみなさまお疲れ様でした。残念ながら、冊子の発行部数が僅かで、私をはじめ委員の執筆者にも1部のみの配布となっており、入手は困難です。一般販売もしていません(そこは心残り。文化財調査報告書などと同様、官公庁の刊行物なので、いつも悩むところです)。各都道府県立図書館や四国4県の県立図書館・博物館等、四国各県の市町立図書館等に配布したとのこと。ご覧になりたい場合は、お手数をおかけしますが、そちらで閲覧ください。冊子版で掲載している資料画像についてはこのPDF版では削除されています(史料の画像が見られるのがこの史料集の最大の特徴でもあります)。史料図版と対照しながら読む場合は、冊子版をご覧ください。
PDFデータは、こちらで公開していますので、ぜひご活用ください。
四国遍路世界遺産登録推進協議会HP(普遍的価値の証明部会)
https://88sekaiisan.org/subcommittees/pdf/shikokuhenro-ancient_medieval.pdf
なお、私が担当して執筆した項目は以下の19項目です。
「四国八十八ヶ所霊場一覧」、「聾瞽指帰 巻下 仮名乞児論(「玉藻所帰之嶋」)」、「聾瞽指帰 巻下 仮名乞児論(「金巌」・「石峯」)」、「三教指帰 巻上 序」、「三教指帰 巻下 仮名乞児論(「金巌」・「石峯」)」、「三教指帰 巻下 仮名乞児論(「玉藻所帰之嶋」)」、「日本霊異記 下巻 第三十九」、「新猿楽記 次郎条」、「為忠家後度百首 五三・七六」、「色葉字類抄」、「梁塵秘抄 巻第二 三〇〇」、「梁塵秘抄 巻第二 三〇一」、「梁塵秘抄 巻第二 二九七・二九八」、「梁塵秘抄 巻第二 三一〇」、「梁塵秘抄 巻第二 三四八」、「新古今和歌集 巻十 九一七」、「新勅撰和歌集 巻十 五七四」、「古今著聞集 巻二 五二」、「四国遍路関係史料集古代・中世編関係年表」
私もこの3年間、四国遍路に関係する古代史・古代文学分野を担当し、調査を進めてきました。事前の文献調査や執筆にかかる時間、編集に関わる作業など、時間的にも精神的にも私がこれまで経験したことのない、かなりの負担量となりましたが無事に刊行されて安堵しているところです(おかげさまでこの仕事で体重もかなり落とすことができました。執筆、編集時のことは過去のこと。思い出さず、忘却の彼方へ・・・)。
これまでの四国遍路研究では活字本や校訂本を引用する形で調査、研究、史料解釈等が行われる傾向にありましたが、今回の調査研究会ではできるだけ原史料を確認の上、再解釈するという立場で調査、執筆、編集を進めてきたところです。特に古代史・古代文学分野では「校訂」前の原文、そして現代語訳(意訳)を掲載することにより、今後の四国遍路研究への基礎データを提示できたのではないかと考えています。
この史料集の編集は、愛媛県庁のまなび推進課が事務局となって行われたものです。まなび推進課のみなさまお疲れ様でした。残念ながら、冊子の発行部数が僅かで、私をはじめ委員の執筆者にも1部のみの配布となっており、入手は困難です。一般販売もしていません(そこは心残り。文化財調査報告書などと同様、官公庁の刊行物なので、いつも悩むところです)。各都道府県立図書館や四国4県の県立図書館・博物館等、四国各県の市町立図書館等に配布したとのこと。ご覧になりたい場合は、お手数をおかけしますが、そちらで閲覧ください。冊子版で掲載している資料画像についてはこのPDF版では削除されています(史料の画像が見られるのがこの史料集の最大の特徴でもあります)。史料図版と対照しながら読む場合は、冊子版をご覧ください。
PDFデータは、こちらで公開していますので、ぜひご活用ください。
四国遍路世界遺産登録推進協議会HP(普遍的価値の証明部会)
https://88sekaiisan.org/subcommittees/pdf/shikokuhenro-ancient_medieval.pdf
なお、私が担当して執筆した項目は以下の19項目です。
「四国八十八ヶ所霊場一覧」、「聾瞽指帰 巻下 仮名乞児論(「玉藻所帰之嶋」)」、「聾瞽指帰 巻下 仮名乞児論(「金巌」・「石峯」)」、「三教指帰 巻上 序」、「三教指帰 巻下 仮名乞児論(「金巌」・「石峯」)」、「三教指帰 巻下 仮名乞児論(「玉藻所帰之嶋」)」、「日本霊異記 下巻 第三十九」、「新猿楽記 次郎条」、「為忠家後度百首 五三・七六」、「色葉字類抄」、「梁塵秘抄 巻第二 三〇〇」、「梁塵秘抄 巻第二 三〇一」、「梁塵秘抄 巻第二 二九七・二九八」、「梁塵秘抄 巻第二 三一〇」、「梁塵秘抄 巻第二 三四八」、「新古今和歌集 巻十 九一七」、「新勅撰和歌集 巻十 五七四」、「古今著聞集 巻二 五二」、「四国遍路関係史料集古代・中世編関係年表」