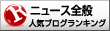時限ストの日が来た。みんな初めての体験だが、正午過ぎに会社の近くの○✖公園に集まる。啓太も小出や今村と連れ立って公園へ行った。すでに20人余りの組合員が集まっていたが、報道部では夜のニュースのADを務める木内典子(のりこ)が来ていた。
「やあ、木内さんは早いね。張り切ってるな」
今村が声をかけると彼女が答えた。
「ええ、だって私は夜のニュースですもの。昼間はなんでもできます」
木内がすっきりした笑顔を浮かべ啓太らを出迎えた。彼女は2歳年下だが、高校卒でFUJIテレビに入ったため社歴は古い。組合活動には熱心で、報道では女性ただ1人の発起人になっていた。すらりとした長身で背丈は啓太ほどあったが、知的で穏やかな性格が職場の人望を集めていた。
やがて集会が始まるころには組合員も40人ほどに増えただろうか、ドラマ制作部の山村邦男が基調演説を始めた。BUNKA放送出身の彼は啓太よりも2年先輩で、労働組合を立ち上げた実質的な中心人物である。啓太が一緒に仕事をした植木ADとは同期の仲だ。
山村は張りのある声でみんなに訴える。
「女子25歳定年制の撤廃は最大の目標だが、われわれはさらに週休2日制の実現、8時間労働の実施などを会社側に強く要求しなければならない。
そのためには、職場の大幅な人員確保が必要であり、これも会社側に強く求めていく方針だ。また、NIPPONテレビやTOKYO放送テレビがすでに実施している残業時間の“青天井”を、1日も早く勝ち取っていかなければならない。そうでないと、残業は単なるタダ働きになってしまうのだ」
一呼吸置いて、山村はさらに訴えた。
「これらの要求は中長期的な目標だが、当面は期末手当・ボーナスの大幅なアップを実現させよう! これはすでに団体交渉でも言っているが、最低でも5カ月分は勝ち取ろう! みんなが団結して戦えば、実現は決して不可能ではない!」
山村の勇ましい演説が続く・・・ 昼下がりの公園は家族連れなど関係のない人もかなりいたが、FUJIテレビ労組の集会はなお続いた。やがて山村の演説が終わり、各職場の代表が現状報告をしたが、労組や民放労連の旗、それに赤旗などが林立し、公園は異様な光景に包まれた。
こうして、時限ストの集会はいちおう成功裏に終わったが、啓太は次第に報道の職場の方が気になっていた。4月から午後2時の『奥さまニュース』が始まったのに、自分や小出ら報道部員は集会に参加している。ニュースの準備はきちんと進んでいるだろうか・・・ どうも気になるのだ。
時限ストは午後1時までだが、集会が少し伸びたので啓太らは急いでテレビ局に戻った。すると案の定、報道の職場はニュースの準備で大わらわだ。原稿のまとめやテロップの発注などが遅れ、稲垣デスクとKYODOテレビの報道部員2人が四苦八苦している。ほかの管理職も手伝っていた。
「すいませんでした!」
啓太は思わず謝って、ニュース原稿や通信社のゲラの整理などに取りかかった。
「いや、参ったよ。君たちがいないと、ニュースが出ないぞ。ハッハッハッハ」
稲垣デスクが自嘲気味に笑ったが、やれやれという感じだった。追い込み作業が続いた結果、『奥さまニュース』はなんとか無事にオンエアされたが、少ない人数では時限ストの影響は無視できない。放送が終わって啓太は小出に話しかけた。
「時限ストもいいが、これではニュースが駄目になる恐れがあるよ」
「それは分かっている。でも、しょうがないだろう」
小出はぶっきらぼうに答えたが、どこか不安げな表情を見せていた。組合の執行部からの指令だから仕方がないが、啓太はこのままではいずれ放送事故が起きるのではと心配になった。しかし、余計なことは考えまいと気を取り直すしかない。
夕方になると、木内典子が夜のニュースの準備で報道の部屋に戻ってきた。「夜ニュース班」はたいてい夕方からスタンバイする。木内が自分の席で、なにやら雑誌を取り出して読んでいる。少し時間があったので、啓太は興味を覚え彼女に聞いてみた。
「何を読んでるの?」
「今月の『言論春秋』よ。ここに私の記事が載ってるの」
そう言って、木内はページを開けたまま新刊の月刊誌を啓太に見せた。そこには「なぜFUJIテレビに労働組合ができたのか」と題する記事が載っていた。筆者は“河田新子”となっている。
「会社が新宿の河田町にあるから、ペンネームを河田新子にしたのよ」
啓太が聞きもしないのに、木内は微笑みながらやや得意気に話した。彼女がそこまで言うとは、すでに『言論春秋』の記事が多くの人に知れ渡っているからだろう。啓太はそれにざっと目を通したが、夕方のニュースの仕事があるので、あとでゆっくり読むと木内に告げ自分の席に戻った。
それから2日後、啓太が今村と雑談をしていると、彼が話題を変えて『言論春秋』の話をしてきた。
「木内さんの記事はもう読んだか?」
「うん、読んだよ。よく書けていると思うね」
啓太が素直に答えた。
「彼女はあの山村さんの後輩だってね。都立NISHI高校の先輩・後輩という仲だそうだ」
「えっ、山村さんの・・・そうか」
山村とは先日、時限ストの集会の時に基調演説をした山村邦男のことである。組合屈指の雄弁家であり人望もあるので、若いながらも執行部に名を連ねている。そうすると、木内典子は山村の影響を受けて組合活動に積極的になったのか? いろいろな疑問が啓太の心に湧いてきた。
それから数日して、典子が山村に好意を寄せていることが組合員の話でだいたい分かった。2人は杉並区の宮前に住んでおり、もうかなり前から顔見知りだったという。山村が近所では評判の秀才でTOKYO大学に進学したため、典子はいつしか彼に好意を抱いていたのだろう。
そして、彼女が都立NISHI高校を卒業してFUJIテレビに入ったのは、彼がBUNKA放送からFUJIに移ったことが大きな要因だったのだ。典子も優秀な高校生だったが、家庭の事情(父親が病気で入院中)で大学進学を諦めテレビ局に就職した。2人は同じ高校を出た先輩・後輩という関係で、ますます親密度を深めたらしい。啓太は典子と山村の関係をそう思ったのだ。
一方、そのころ石浜部長は、組合対非組合の対立に頭を悩ませていた。彼は組合の勢力をなんとしても削ぎたいと考えたが、安易な“不当労働行為”は禁物である。そんなことをすれば、組合に訴えられるかもしれない。陣内社長は「不当労働行為をやっても、死刑にはならない」と言ったが、それはあくまでも経営側の姿勢を強調したものなのだ。
そこで、石浜は次善の策として、組合に対抗できる「第2組合」の結成を考えるようになった。これは自然の流れだろう。経営陣やほかの管理職も、ストをやらないで会社に協調的な第2組合を模索するようになっていた。しかし、それはすぐにはできない。ある程度の時間をかけて準備するしかないのだ。
こういう状況の中で、組合は1週間後に再び時限ストを実施することになった。その日、啓太らはまた近くの○✖公園に集まり、山村ら執行部の演説を聞いた。今度は労働環境の改善など中長期的な話は少なく、当面の期末手当・ボーナスの要求などが中心であった。
集会は延々と続く。会社側との団体交渉の話が紹介され、ボーナスの大幅アップなどが決議された。しかし、集会に参加していて、啓太はまた職場の混乱が気になってきた。ニュースのオンエア時間が次第に近づく・・・
「もう帰らないと、放送が大変だぞ」
啓太は傍にいる小出にそっと話しかけた。
「しょうがないよ。ストなんだから」
小出は面倒くさそうに答えて、知らん顔をする。啓太はじりじりしてきた。この前の報道の混乱ぶりが目に浮かぶ。このままでいいのか・・・ 啓太は意を決してその場を離れた。小出や木内が不審な目付きをしたが、彼は公園を後にしたのである。
どう思われたっていいさ。俺は“スト破り”をするのか・・・? そう思われたって仕方がない。俺は報道の職場に戻る! 啓太は足早に会社へ戻っていった。
そういう日々を送っているうちに6月も終わり、暑苦しい7月を迎えた。すると突然、報道部の人事異動が行われた。気になったのは労働組合員の処遇だったが、それはまだ大した動きにはならず、外勤記者の入れ替えなどが主なものだった。しかし、啓太が驚いたのは、同期の大橋剛(つよし)が厚生省記者クラブに配属されたことである。大橋は報道部に来て間もないではないか。
「剛(ごう)ちゃんはいいな。もう“記者”をやるのか~」
啓太がうらやましそうに言うと、大橋は豪快に笑って答えた。
「石浜さんが決めてくれたんだよ。部長とは相性がいいからね、ハッハッハッハ」
彼は組合を相手にしないから、石浜に認められたのだろうか。組合員の啓太は複雑な気持になってくる。なにか大橋に差を付けられた気がするのだ。啓太は黙って退いたが、どうも面白くなかった。同様に、内勤が長くなった同期の小出誠一も面白くなかっただろう。
もう一つ意外だったのが、以前、報道番組で一緒だった先輩の三雲大輔が、ニュース報道に来るなりいきなり労働省記者クラブに配属されたことだ。しかし、三雲は非組合員だが啓太より2年先輩で、ラジオのBUNKA放送時代に外の取材経験が豊富だったから、これは納得しなければならないだろう。
組合員と非組合員の“差別化”が進んでいるのだろうか。それははっきりしないが、どうもそんな感じがしてくる。しかし、それでくよくよしても始まらないので、啓太は気を取り直して内勤業務を続けることになった。
やがて、夏休みの時期になった。以前はアナウンス室の同僚と海へ遊びに行ったりしたが、今年はなんの声もかからない。みんな、組合問題で悩んでいるのだろうか。どこか疑心暗鬼な雰囲気になっている。アナウンス室ではベテランのアナウンサーが数人、組合を脱退したと聞いている。陰に陽に、会社側の工作が進んでいるようだ。
そんな折、石浜部長が啓太に声をかけてきた。
「来週末に、川崎や金森たちと海へ行かないか。NIPPON放送の杉山も一緒だ。久しぶりに泳ごうじゃないか」
弾んだ声で石浜が誘うので、啓太は一瞬ためらったがすぐにそれに応じた。一瞬の“ためらい”とは、このグループがみんな非組合員か、社外の人たちだったからだ。しかし、川崎や金森はよく知っているのでまったく違和感はなかった。もちろん、石浜とは昔からの縁がある。 こうして、翌週の末に啓太は“石浜グループ”と逗子(ずし)へ海水浴に行くことになったが、小出や今村たち組合員には内緒にしておいた。
そのころ、啓太の家でもFUJIテレビの組合問題が話題になった。父の国義や母の久乃は石浜をよく知っていたので、彼の立場を擁護してしつこいぐらいに啓太に注意するのだ。
「石浜さんの言うことをよく聞けよ。彼の言う通りにすれば間違いはない」
国義は啓太に何度も念を押した。
しかし、それがあまりに“しつこい”ので、啓太はかえって反発を感じた。両親の言うことは正しいと思うが、耳にタコができるのだ。うんざりしていると、久しぶりにわが家へ帰ってきた兄の国雄が良いことを言った。
「労働組合ができて当たり前さ。ましてFUJIテレビにできて良かった。これで正常な労使関係になると思うよ」
国雄がそう言うので、啓太はホッとした。国雄は当時の「同盟」系の労働運動に関わったことがあり、会社で組合の執行役員を務めていたほどだ。兄に助けられ、啓太は両親の言うことを聞き流すようになった。
数日後の週末に、啓太は石浜部長らと一緒に逗子へ海水浴に出かけた。そして、安旅館に一泊し夜は酒を飲んで楽しんだが、みんなを誘った石浜が妙に口数が少なくて静かだ。まるで部下の様子を探っているみたいで、気味が悪い。
「石浜さん、もっと愉快に騒ぎましょう。歌でも歌いますか・・・」
川崎が水を向けるが、石浜は気のない返事をするだけだ。やはり組合問題が重くのしかかっているのかと啓太は思ったが、口に出すことはしなかった。そこでひとり陽気で多弁だったのが、NIPPON放送の杉山宏だった。彼は最近のラジオ局の模様について、面白おかしく説明する。
これには啓太も川崎たちもほとんど無関心だったが、石浜が寡黙なため仕方なく聞き役に回っていた。石浜だけはNIPPON放送の出身だけに、時おり杉山に質問する。
「テレビって、いいなあ。俺も移りたかったよ。でも、俺は優秀だから上が離さないんだ。本当だぞ」
彼が自慢げに言うので、圭太たちは苦笑した。
「おい、杉山、君は本当に優秀なのか? ハッハッハッハ」
石浜が初めて愉快そうに笑った。これで座が少し和んだのか、みんなが勝手に雑談を楽しんでいたが、やがて石浜が意味ありげなことを言い出した。
「いいか、9月には何もかもはっきりさせる。今は言えないが、FUJIテレビにとっては重要な9月になるぞ。みんな、心して待っていろよ」
これには誰も神妙な気分になったが、すぐに雑談に興じるようになった。
「石浜さん、国枝は組合に突っ込みすぎて変ですよ。報道にいない方がいいですね」
川崎が同期の国枝久のことを言った。啓太にとっては川崎も国枝も3年先輩に当たる。
「うん、この前、国枝がいろいろなことを言ってきたので、お前のような優秀な男は報道には要らないと言ってやったよ。そうしたら、ずいぶん怒ってたな、ハッハッハッハ」
石浜が我が意を得たりとばかりに答えた。国枝は昭和36年入社組の“ホープ”と目されている男なのだ。
「国枝さんは庶務の滝川さんと仲が良さそうですね。この前、2人が連れ立って新宿を歩いているのを見かけましたよ」
金森がそう言うと、石浜がびっくりしたような表情を見せた。
「えっ、そうか。滝川君は良い娘(こ)だよ。ただ、彼女は来年4月には定年になるんだよな。わが社では女子25歳定年制の第1号ってわけだ」
この石浜の答えに、啓太は複雑な気持になった。彼が言うように、たしかに滝川和江は素直でよく働く評判の良い社員だった。
「定年さ、定年、仕方がないじゃないか。陣内社長が決めたんだもの。うちもそうだよ」
杉山が大きな声を出したが、NIPPON放送も同様の制度になっている。陣内がNIPPON、FUJI両社の社長を兼ねているから、当然のことなのだろう。
「しかし、国枝が滝川君と仲が良いとは知らなかったな。25歳定年制で、彼女にいっそう同情しているのかな。彼はそういう男だよ」
石浜がさも納得したように言ったが、啓太は内心では女子25歳定年制に不満を持っていた。しかし、今それを言ったところでどうしようもない。みんなの雑談がなお続き、最後はカラオケで歌ったりしてその晩はお仕舞いになった。
翌日も海水浴を楽しんだあと一行は別れたが、啓太は石浜が言った9月が重要だということを思い出していた。きっと労働組合への反撃が始まるだろうが、それは「第2組合」をつくるということか。多分そうだろうが、いろいろ憶測しても仕方がない。当面は仕事に集中しよう。
啓太はそう考えたが、ちょうど夏のニュース企画が浮上してきた。稲垣デスクの話では何をやっても良いというので、地方駐在の契約カメラマンにいろいろ当たってみた。デイリーニュースばかりやっていると飽きてくるので、この企画づくりは新鮮な感じがする。
結局、青森駐在の吉野カメラマンの案に同意し、啓太は八戸(はちのへ)沖合のイカ釣り漁を取材することになった。8月初旬、啓太は列車で八戸へ直行し吉野さんと落ち合うと、さっそく彼が話を付けていたイカ釣り船に乗り込んだ。夕方になると、何十隻というイカ釣り船が八戸漁港から出発する。
夜、船が沖合に出ると、一斉に“集魚灯”に明かりがともった。海は鏡のように静かに広がっている。そこに無数の橙色の灯が映り、まるで灯籠(とうろう)が漂っているみたいだ。啓太はこれほど美しい海の夜景を見たことがなかった。ただ茫然と眺めているだけである。
するとガラン、ガランと音を立てて何台もの“巻き上げ機”が作動する。これは自動イカ釣り機だが、そこには数多くのイカが掛かっていた。イカ釣りは夜通し行われる。この模様を吉野さんが16ミリ・フィルモで撮影していたが、どういう訳か途中からしゃがみ込んで動かなくなり、苦しそうな表情を見せた。
「吉野さん、大丈夫ですか?」
啓太が声をかけたが、返事がない。すると、側にいる漁船員が言った。
「船酔いだよ」
えっ、船酔いだって? こんなに静かな海なのに・・・ 仕方がない。啓太は吉野さんのフィルモを取り上げて撮影を始めた。
彼は前にもカメラ撮影をしたことがあるが、ごく初歩的な段階で(2~3カ月で)止めてしまったことがある。それは海外ニュース班へ異動になったからで、以来 撮影はしていないのだ。啓太は慣れない手付きでカメラを回し始めた。照明のライトも点けている。
こうしてなんとか撮影を続けるうちに、日の出となった。イカ釣りも終わりガラン、ガランという自動釣り機の音も止んだ。獲れたてのイカはみんな薄茶色をしている。漁船員の話だと、これが見る見るうちに白くなるそうだ。ホッと一息ついていると、彼らの1人がイカの刺身を持ってきてくれた。
薄茶色の身は少し気味が悪かったが、醤油とワサビで食べてみると実に新鮮で美味しい。お腹が空いていたので、あっという間に一皿たいらげた。そして、船が八戸港に戻るうちに、吉野さんがようやく船酔いから覚めたようだ。彼はアクシデントにえらく恐縮していたが、啓太は撮影は順調に済んだと何事もなかったように話しておいた。
こうしてイカ釣り漁船の取材は終わったが、局に帰ってフィルムを見直すと、どうしても新人カメラマンの下手な撮影ぶりが目につく。藤森ディレクターが不審に思ってあれこれ聞くので、啓太はとうとう正直に吉野さんの件を話してしまった。藤森は事情が分かったのかすぐに吉野さんに電話をかけ、イカ釣り撮影の撮り足しを指示した。
数日して、今度は見事なカメラワークのイカ釣りの映像が届き、これをもとにニュース企画『夏の風物詩・イカ釣り船』ができあがったのである。啓太の企画は評判が良く、初めて多くの人に褒められた。こんなこともあるのか(笑)。イカ釣りの企画が成功し、彼はなんとなく自信をつけたようだ。
デイリーニュースの仕事は相変わらずだったが、8月も終わりに近づくと、ようやく夏休みを取れることになった。
「どこかへ行くのか?」
今村が聞いてきたが、別に大した予定はない。啓太は生返事をしていたが、そのうち、急にどこか遠くへ行きたい衝動に駆られた。組合騒動に揺れる会社のことは、一時でも忘れたかったのか・・・ それは分からないが、彼は“山陰地方”へ行ってみたくなったのだ。大急ぎで国鉄の周遊券などを手配し、8月から9月にかけて旅行することになった。
啓太は学生時代に兵庫県北部の豊岡に行ったことがあるが、山陰地方は初めてである。豊岡には学友がいたので訪れたが、今回も山陰本線で鳥取から島根へと入った。途中、米子の皆生(かいけ)温泉や松江の玉造温泉に立ち寄ったが、旅館の仲居さんと未明まで飲み明かしたりして楽しんだ。
そうした中で、宍道湖(しんじこ)の美しさは目を見張るものがあった。特に夏の陽射しが湖面を照らしていると、湖が浮かび上がってくるように見える。ここは“水の都”なのかと思うほど、心がしっとりと潤ってくるのだ。啓太はもし許されるなら、湖畔に“いつまでも”たたずんでいたいと思った。
彼は宍道湖の風景に見とれていたが、そう長居はできない。次に、松江からそう遠くないので出雲大社へと向かった。ここは“縁結び”の神様として有名だそうだが、啓太は別にそれを願ったわけではない。ただ有名スポットなので、一度は行ってみようということだ。神社の境内には、それらしきカップルも見受けられた。
その帰りに付き合った女性のことをいろいろ考えてみる。高校や大学時代、そしてテレビ局へ入ってからの女性・・・ 五代厚子や江藤知子のことも思い出してみた。でも、彼女らとは縁がなかったのだ。これからどうなるかも考えてみる。しかし、そんなことはまったく分からない。自分はもうすぐ25歳になるが、考えても仕方がないと思うだけだった。
啓太はそのあとまた山陰本線に乗り、最後の旅行先である山口県・萩市へ向かった。ここは松下村塾など幕末から明治維新にかけての史跡が数多く残っている。それらをできるだけ見て回ったが、夏休みの期限が翌日一杯となって急ぎ帰ることになった。帰路は山陽本線や新幹線に乗ってである。そして、夏休み最後の日の夜遅く帰宅した。
(8)協議会の発足
9月、陣内社長は労働組合に対抗する「FUJIテレビ協議会」の設置をついに決断した。これは“第2組合”のようなもので、組合とは違って労使協調の路線がきわめて色濃いものだ。第2組合的組織の誕生は社内ですでにささやかれていたから、社員の多くはそれほど驚かなかった。むしろ、当然と見ていただろう。
社長の指示で、人事部を中心に管理職は協議会設置に動いたが、ここで注目されるのは石浜報道部長の取り組みである。まだ内々のことだったが、彼は報道に出向してきたKYODOテレビの70数人を全員、FUJIテレビの社員にするよう陣内社長に強く働きかけた。これには陣内も驚いた。
彼は経営のトップにいるから、そう簡単に社員を急増させるわけにはいかない。しかも70数人をいっぺんにである。だが、石浜は陣内に食い下がった。
「社長、報道はこれからテレビの中心になっていく重要な部署です。社長はこれまで何度も『わが社の報道はウィークだ(弱い)』と言ってきたではありませんか。今こそ報道を強化する時です。そのためには、KYODOテレビから出向している者たちを、わが社の社員に加えることだと思います」
この石浜の主張に陣内はもう驚かなかったが、次の発言に大いに心を動かされた。
「彼らは70数人いますが、私はその全員を協議会に入れたいと思います。組合には絶対に入れさせません! 彼らはFUJIの社員になるので、喜んで協議会に入るでしょう。もし協議会に入らないのであれば、そういう者は一切 社員にはしません!」
「う~む、それはすごい組合対策だ。石浜君、君はずいぶん大胆なことを考えるな。大したものだよ」
「いえ、恐れ入ります」
「年内は無理だが、来年の経営課題としておこう。私も報道の強化は必要だと考えている。それは異論がないので、近いうちにKYODOテレビの野際社長とも話し合おう。石浜君、いい案だよ」
陣内社長がその提案を称賛したので、石浜は心から満足した。
そして数日後、FUJIテレビ協議会設置の正式な日取りが決まり、各部署に伝達された。これに組合側は大いに反発したが、啓太も同様の気持になったのだろうか・・・ 会社側の措置は分からないではないが、労働組合の存在意義も十分に理解できる。それを考えると、双方の板挟みになるみたいで複雑な気持になった。
そんな時、同期アナウンサーの石黒が啓太に愚痴をこぼした。
「輿石さんが組合を脱退したよ。俺は彼を屋上から突き落としてやりたいぐらいだった」
輿石というのはベテランアナウンサーで、石黒の大先輩に当たる。彼が数日前、石黒を会社の屋上に呼び出し、組合を脱退して協議会に入ると述べたというのだ。石黒は非常にくやしそうな表情で語ったが、啓太はその気持が十分に分かる気がした。どの部署でも、組合の脱退工作が進んでいるようだ。
「石浜さんは“悪い奴”だよ。彼のせいで、報道でも何人かが組合を辞めたそうだな」
石黒が突然、石浜を名指しで非難した。そう言われても、啓太には心当たりがない。組合活動に熱心な石黒だから、各部署の情報が早く入るのだろう。
「そんなことは知らないよ。あさって、報道部の討論集会があるんだ。そこでいろいろなことが分かると思う」
啓太はそう答えるのが精一杯だった。
「窪川さんも組合を辞めたんだって。あの人も“日和見”だな」
石黒がそう続けたが、啓太はまったく知らない。
「えっ、窪川さんも・・・ もういいよ。石黒、僕は変わらないさ。それじゃ」
啓太はそう言って石黒と別れたが、なにか不吉な予感がしてくる。あさっての討論集会はどうなるのだろう? なにか参加したくない気持にもなる。討論しても“亀裂”が深まるばかりで、前向きなものは何も生まれてこない気がするのだ。
啓太は世の中の動きを努めて見ようとする。報道記者として当然のことだ。すると、一会社の中で組合だ、非組合だと騒いでいるのが空しくなる。それも人生経験だろうが、あまりにも小さく見えるのだ。それとも、自分は組合騒動から逃げようとしているのだろうか・・・ この年(1966年・昭和41年)、日本の総人口はついに1億人を突破した。右肩上がりでますます増えていくようだ。
しかし、この年は「丙午・ひのえうま」といって、生まれる女の子は男を食い殺すという迷信があったため、出生率は前年より25%も下がった。あまりにも馬鹿馬鹿しい迷信で啓太はあきれ返ったが、それでも人口は着実に増えていった。ただし、交通事故による死者が急激に増え、「交通戦争」という言葉も生まれた。
一方、東京オリンピック後の反動で悪くなっていた景気は、完全に回復したようだ。いわゆる“いざなぎ景気”が実現し、史上最高のボーナスが支給され、世の中は「3C」という三種の神器、つまりカー、クーラー、カラーテレビが飛ぶように売れていった。デパートの売り上げは史上最高を記録、自動車の生産高は世界第3位に躍進した。
こうした国内情勢とは逆に、国際情勢はますます緊迫してきた。ベトナム戦争はさらに激化していったが、人々を最も驚かせたのは、隣の中国で「文化大革命」の嵐が吹き荒れたことだ。8月、北京で“紅衛兵”の100万人大集会が開かれると、その嵐は中国全土に広がっていった。中国はどうなっていくのか・・・
それはマスコミだけでなく多くの日本国民の関心事であったが、いかにせん国交のない国である。実情はほとんど分からないのだ。一部の外電を頼りにあれこれ推測するしかないが、日本国民にとって中国は“謎”の国だったと言える。マスコミは中国を取材したがっていたが、国交がないので厚い壁に阻まれた形になっていた。
世の中が激しく変貌する中で、報道部の討論集会の日を迎えた。ところが、その日の午後、東京・荒川の工場街で大きなガス爆発事故が起き何人もの死者が出たというので、討論集会は急きょ延期になった。少ない人数で報道に当たっているFUJIテレビでは当然のことである。
同期の今村はガス爆発の現場取材でずっと不在だ。小出もカメラ取材の応援で出ている。この日の内勤整理に当たっていた啓太は、居合わせた木内典子に声をかけた。
「討論集会が延期になって、残念だな」
「ええ、でも、集会は何度やっても同じだと思うわ」
「そうか~、そうかもしれない。かえって亀裂が深まるだけだね」
啓太と木内は顔を見合わせて微笑んだ。お互いに相手の気持が分かっているようだ。結局、その日の夜、稲垣デスクの通達で、報道部の討論集会は1週間延期されることになった。啓太はなぜかホッとした気分になったのである。