13)死から生へ
一九六一年の元旦は、行雄にとってこの上もなく暗いうつろな幕開けとなった。 彼は家族ともろくに口もきかず、ほとんど部屋に閉じこもって物思いに沈んでいた。時の流れが、これほど長く切ないものに感じられたことはなかった。 全ての苦悩が、なんの仮借もなく彼の心を蝕んでいくようである。
唯一の喜びは、森戸敦子から“ありきたり”の年賀状が届いたことだった。 それは、神からも人間からも見捨てられた、哀れな孤児に届いた福音のようなものであった。 行雄は嬉しさのあまり神経が高ぶり、その年賀状に口づけして涙ぐんだ。そして、無性に敦子に会いたいと思った。
しかし、挫折した自分の惨めな様を、どうして彼女に見せることができるだろうか。こうして不様に虫けらのように生きている自分には、彼女に会う資格はないのだと思う。 この哀れな男にも、最後のプライドというものはあるのだ。 会いたいと思っても、今は敦子に会うことはできないと行雄は断念した。
危機が確実に近づいていた。 行雄は全てのことに関心や興味を失い、生きていく欲望も気力も持つことができなかった。人生とはこんなにも味気なく、一時、一時がこんなにも耐え難いものなのだろうか。 砂を噛むような思いとは、こういう状況を言うのだろうか。ただ呼吸をして“生物的”に生きているだけの自分なのだ。
絶望とは、ある哲学者が言ったように「生きることもできない、死ぬこともできない」状態を言うのだろう。 現在と未来になんの希望も光明もなく、ただ漠然と呼吸しているだけのこの生き物。 行雄は絶望していた。どこに暗闇からの出口があるのだろうか。どこに救いの光りがあるというのか。
何もない、何もないのだ。 死・・・全てを無にし、全てに永遠の安らぎをもたらす死。 俺も大川らのように、ブロバリンを飲んで死んでもいいのだ。自殺・・・馬鹿野郎! この俺が、どんな悪いことをしたというのか! 俺にはなんの罪もないはずだ、死んでたまるか!
そうは思ってみても、どこに生きることへの、喜びや張りがあるというのだろう。何もないのだ。有るのはただ挫折感と苦悩だけだ。 行雄は悶々として冬休みを過ごした。 憔悴し切った彼は両眼が落ち込み、“まぶた”が一重から二重に変っていた。
唯一の慰めは、テレビで大相撲中継を見ることだった。 大好きだった横綱・栃錦は引退していたが、柏戸、大鵬といった若手の大関らが奮闘する様を、放心したように見ていた。 そうした時だけが、安らかな気分になれたのである。
ある日のこと、向井が久しぶりに行雄を訪ねてきた。 彼は行雄が学生運動から離れたことを知っていたので、励ましのつもりで来たのだろうが、行雄は少しの間雑談を交わした後「これ以上、君と話すことはないよ」と言って、冷たく向井を追い返してしまった。 行雄は誰とも話したくない心境だったのである。冬休み中、まるでうつ病や自閉症患者のように、彼はほとんど部屋に閉じこもって過ごした。
三学期が始まっても、行雄はまともに大学の講義を聴きに行くことはなかった。 クラスメートにも会いたくないし、ましてや全学連の活動家とは顔を合わせたくなかった。 時たま外出するようになったが、当てもなく東京の街頭を彷徨うくらいである。
そんなある日、行雄は突然、美味しいものを食べたいという衝動に駆られた。 食べ物にはまったく関心がなかったのに、どういうわけか動物的に旨いものが食べたいと思ったのだ。日頃の彼は、家でも食事は不規則だし、食べたいものを言わないので久乃を当惑させていた。 日々の空腹感が極まって、そういう欲望が起きたのかもしれない。
財布の中には五千円ほどあった。よしっ、俺は今日これを全部使って、美味しいものを食べるぞと誓った。 夕方になって、行雄は新宿の繁華街に出かけた。彼はこの一年以上にわたって、旨いものを食べたことがなかった。それは、自分が“革命家”であるという自覚を持っていたからである。
革命家たるものは、清貧に甘んじなければならないと思っていた。 武士は食わねど高楊枝ではないが、革命家であるという強烈なエリート意識がそうさせていたのだ。 デモ行進して喉が渇いても、行雄は一般の学生のように、アイスキャンデーやアイスクリームを口に入れることは決してなかった。
しかし、今は違う。自分は革命家でもエリートでもない。挫折した一介のルンペンなのだ。そういう革命家としての誇りは、もう必要ないのだ。よしっ、食べるぞと決意したが、その決意は、かつての国会突入の前の気持に似ていた。 彼は歌舞伎町の界隈でいろいろな料理店を物色した。
とある街角の近くで、ロシア料理店が目についたので行雄はその店に入った。 メニューを見たが何がなんだか分からないので、ウェーターに聞いて最上級のマトンのシチューと高級ウオッカを注文した。
胸の高鳴りを覚えながらシチューをスプーンですすると、とろけるような熱い味が腹の底まで浸みとおる。旨い! こんなに旨いものは、この一年以上食べたことがなかった。 マトンを貪るように食べると、これがまた何とも言えず柔らかく、その美味しさは格別であった。
次いでウオッカを一口飲むと、喉が火のように熱くなり目頭がジーンとしびれてきた。 行雄はウオッカの酔いで心地良い疲労を感じながら、俺は革命家ではない、エリートでもないと再び自分に言い聞かせた。
俺はいま自分のために飲み、食べているのだと自覚した。 そして、それは誰からも咎められるものではなく、かつて他人の幸せや解放を念じて行動したために、多くの人達から非難され弾圧されたことが馬鹿々々しく思えるのだった。
ロシア料理店に一時間ほどいた後、行雄はまた繁華街に出て街頭をぶらついた。財布にはまだ二千円ほど残っている。 全部使わなくてはと思いながら、今度は立派な店構えの中華料理店に入った。店内は家族連れなどの客で賑わっていた。
いつも食べているラーメンや餃子などには目もくれず、芝エビのチリソースと酢豚、春巻きを注文しビールを飲んだ。 隣りのテーブルでは、親子四人連れが楽しそうにおしゃべりをしながら、料理に舌鼓を打っている。 行雄には、その一家団らん振りが羨ましく思え、独りきりの自分を寂しく感じた。
家族の団らんなどは“プチブル”のささやかな楽しみだと、つい先日までは軽んじていたのに、今ではそれが非常に羨ましく感じられるのだ。 俺はいつから家族の団らんを忘れてしまったのだろうかと、行雄は悲しい思いに駆られた。
しかし、とにかく腹一杯食べようと思い、彼は注文した料理をほとんど平らげてしまった。 先ほど飲んだウオッカにビールが混ぜ合わさったせいか、酔いが一層強くなって気持悪くなったが、彼は満腹感に満足していた。 俺は腹一杯食べて飲んだのだから、これでいいのだと自分に言い聞かせた。
それから数日後、青白い顔付きでぶらぶらしている行雄を見兼ねて、クラスメートの橋本敏夫が、キリスト教を信仰する学生の会に彼を誘ってきた。 宗教には関心のない行雄だったが、橋本が熱心に勧めるので、彼について練馬の「友愛の家」という施設を訪れた。
和室が四部屋ある古びた家屋は、学生クリスチャン達が廃材などを組み立てて作ったもので、彼等が「友愛の家」と呼ぶものである。 大工仕事に素人の学生にしては、有り合わせの廃材で見事に建てたものと言えよう。
そこに十数人の学生が集まり、一緒に夕飯を作って食事をした。 この後、学生達は互いに「敏夫さん」とか「一郎さん」などと名前を呼び合って、神の愛についてティーチインを始めた。 行雄は、キリスト教のことは良く分からないので黙って聞いていたが、ティーチインは延々と三時間以上も続いた。
その晩、行雄達はシュラーフザックに身を包んで寝たが、翌日、学生達は隣接する精神障害者施設のために、無償で便所を建ててあげることになった。 行雄も便所作りに一日中汗を流したが、和気あいあいと楽し気に働く学生達の姿は印象に残るものだった。
夕方になって勤労奉仕が終ると、行雄は橋本と一緒に帰路についた。 橋本が「友愛の家」や今日一日の労働について感想を聞いてきたが、行雄は大した感慨もなかったので、「さあね」と冷たくいい加減に答えた。
すると、橋本が語り始めた。「君はやっぱり自己中心主義者のようだね。 自己も大切だが、人間は自分独りで生きていると思ったら大間違いだよ。 この社会と大自然の中で、人によって生かされ、神によって生かされているということを知らなければならない。
別にこれは、キリスト教だけの考えではないのだが、そういう認識に達しない限り、人間はいつまでたっても孤独だし、人生の本当の喜びを感じることはできないと思う。 君は学生運動も随分やり、本もいろいろ読んでいるようだが、肝心なことをいつも忘れているような気がするよ。
お節介なことを言って悪いけれど、それは君が、いつも自己中心にものを見ているからだと思う。 僕から見ると君は絶えず背伸びをして、焦りながらやっていたような感じがしたね。 君はいま、確かに苦しい思いをしていると思う。学生運動をあれほどしていたからね。
君は君なりの仕方で脱却すると思うが、自分の生き方をもっと他人との関係、社会や大自然との関連において見直すべきだと思う。 そうした点から、人の愛、神の愛というものが分かってくるのではないのか。 君はどう思う?」
橋本にそう言われても、行雄は黙ったまま答えなかった。 彼の言わんとすることが分からないではないが、素直にそうだとは言えなかった。無償の勤労奉仕はとても良いことだが、それと宗教の問題とは別の次元のものである。
行雄はもともと宗教には関心がなかったので、心の底からキリスト教に“身震い”しない限り、信仰しようという気持にはなれないのだ。 それでもクリスチャンである彼等は幸せだと思う。宗教的信条があるからだ。 それに比べて、自分には今やなんの信念も思想もない。 自分はいま、苦悩の中を彷徨っているだけである。
しかし、行雄はそれでも良いと開き直った気持になった。傷つき挫折した人間が、そう簡単に救われるだろうか。 心の底から納得できる思想を体得しない限り、自分は救われないのだ。自己中心主義者となんと言われようとも、自分はそういう人間である。 自分をごまかすことはできない。他人からどのように見られようとも、自分の力で救われるまでは、苦悩に耐えていかなければならないのだ。 行雄はそう思いながら橋本と別れた。
「友愛の家」を訪れた後も、行雄の煩悶はますます深刻になっていった。 朝、目を覚ますと、今日も鉛のように重苦しい一日が始まるのだと思う。 俺は、なんの存在価値もない塵(ちり)や芥のような人間だと思う。自分にはなんの生きがいも目標もないのだ。
マルクス主義もアナーキズムも乗り越えた自分だと知りながら、塵や芥のような人間なら、どうして生きていくことができるだろうか。 死ぬことは簡単だ。誰もがやるように、ブロバリンを飲んで首を吊ればいい。 敗北者だとかなんとか、他人からどのように言われてもいい。
しかし、死ぬことの意義があるのだろうか。もっとも、生きることの意義もあるのだろうか。 何もない、何もないのだ! この呼吸だけしている虫けらが・・・ああ、生きることも、死ぬこともできないこの虫けら。 行雄は絶望感に苛まれていた。
ふと、自分はどうして生まれてきたのだろうかと思ってしまう。生まれてこなかった方が良かったのかもしれない。 あの太平洋戦争の末期、俺は母の背におんぶされて、なんの覚えもなく逃げまどっていた時、アメリカ軍の爆弾に当たって死んでおれば良かったのだ。 そうすれば、今のような耐え難い苦悩を経験することはなかったのだ。
虫けらのような自分を思うと、切なさに涙が込み上げてくる。泣けるものなら泣こう。 行雄はベッドにうつ伏し懊悩しながら泣いた。泣いているうちに、いくらか心が安まってきた。 俺の十九年の短い人生は何だったのかと思う。ぼんやり物思いに耽っていると、安保闘争の頃の思い出が蘇ってくる。
機動隊と真正面から対峙した時の緊迫の瞬間。 六月十五日の国会突入、女子学生の死を聞いて泣いたあの時・・・その後の機動隊の凄まじい実力行使。 国会を二重、三重にデモ隊が取り囲み、赤旗をなびかせながら行進していく情景。
デモ行進した後、徹夜で座り込んだ日々。 座り込みから警察官にしょっぴかれ、いよいよ留置場にぶちこまれるのかと期待していたら、途中で放免された時の悔しさ・・・俺は雑魚(ざこ)なのかと情けなく思ったものだ。
大川や笹塚らと、日本革命の展望について果てしなく議論した日々。 競馬新聞社を経営している元マルキストの社長を訪れ、革命運動の資金をもらおうと四苦八苦したあの時・・・社長さんはなかなか金を出そうとしなかったが、ついに何万円かをせしめた時の喜び!
ある時、俺を連行する大男の機動隊員を「税金泥棒」と呼んだら、失神するほど顔面を殴られ、思わず「すいません!」と悲鳴を上げたこともあった。 デモ隊の中に敦子に似た女子学生を見つけた時、俺は「敦子ちゃん」と声をかけたくなったものだ。
行雄の思い出は敦子のことに移っていった。安保闘争以前の彼女との甘く切なく、楽しい日々。それを思い出していると、彼は無性に彼女に会いたいと思った。 自分の不様な姿を見られたくないので、一度は彼女に会うことを諦めたが、今や矢も楯も堪らない気持になった。
苦悶の底無し沼から自分を救い出してくれるのは、結局、敦子しかいないと思う。 傷ついたこの哀れな男を癒してくれるのは、彼女しかいないのだ。行雄の想いは次第に狂おしくなっていった。
そして一月末のある夜、彼は再会の願いを込めて敦子に手紙を書いた。電話では、とても自分の気持が十分に伝わらないと思ったからである。 この手紙は、心の錯乱状態がそのまま表れたような激しく悲痛なもので、普通の人間なら冷静に読むのに耐えられないようなものだった。 行雄は過去の非礼を詫びてから、再会の願いを切々と訴えた後、乱れる心情をそのまま文末に吐露した。
「できることなら、君の暖かいその胸に顔を埋めて泣きたい。 君の柔らかな優しいその手で愛撫されるなら、僕の耐え難い苦悩も癒され、僕はきっと蘇ることができるだろう。 いま朽ち果てようとしている枯れ木に、君は水を注ぎ、太陽の光を恵んでくれるのだ。
ああ、僕の永遠の女性、救世主よ。どうか僕を助けてほしい。 愛なくして、どうして生き物が救われることがあるだろうか。君の愛なくして、どうして僕は生き延びていくことができるだろうか。 君の愛がなければ、僕の人生は暗闇であり地獄だ。そんな人生なら、生きていく価値は何もない。死んだ方がましだ。
ああ、僕の女神よ。君の暖かい胸の中で、僕は光と希望を取り戻すことができるのだ。“僕の敦子”と呼ぶのを許してほしい! 君と結ばれることがなければ、僕は死を選ぼう。 ああ、敦子、敦子、君の全てに、君の全身に接吻したい。お願いだから、それを許してほしい! 君は永遠に僕のものなのだ」
通常の精神状態なら恥ずかしくなるようなその手紙を、行雄は速達で敦子に送った。彼は息を凝らして彼女の返事を待った。 四日後、敦子からの返事が届いた。
「私はいま、大学受験を目前にして、とても貴方に会えるような状態ではありません。 冷たいと思われるかもしれませんが、受験が終って落ち着いたら、貴方と会うことも考えてみたいと思います。
貴方が私を褒めちぎることには当惑しています。 貴方は相変らず熱烈で極端で、幻想を追い求めているようですね。いまの私は、以前、貴方が考えていたような女ではなくなっています。 お互いにもう少し落ち着いたら、冷静に話し合えるのではないでしょうか」
敦子の手紙は短かった。 そして、将来の結婚については英語で「Good Heavens!」と書かれていた。 行雄は英和辞典を調べて、Good Heavens!が「とんでもない!」という意味だと分かると、奈落の底に突き落とされた感じがした。
なんて冷たいんだ・・・これが、救いを求めた哀れな自分に対する返事なのか。行雄は憤りと悲しみで目が眩んだ。 悪魔! 鬼! 畜生! 彼は心の中で敦子を呪った。 これが、あの優しく麗しかった彼女の返事なのか。行雄は逆上のあまり、気も狂わんばかりになった。
彼は直ちに、机の引出しの中に大切に仕舞っておいた敦子の写真や手紙を取り出すと、それらを全てビリビリに破いてしまった。 それでも気持が治まらず、それらを風呂の焚き口へ持っていきマッチで火をつけた。行雄にとって“宝物”であった写真や手紙は、あっという間に炎に包まれ灰になった。
彼は去年の大晦日、革命に関する全ての機関紙誌やパンフレットを燃やしたことを思い出した。 これでいいのだ、どうせ俺は脱落者であり、革命からも恋からも見捨てられた敗北者なのだと思った。 これ以上、どうして生きていく必要があろうか。死んでやる、死んでやる! いや、このまま野垂れ死にしてたまるか!
行雄の心は生と死をめぐって千千(ちじ)に乱れた。 死んでたまるかという思いと、生きていても何の意味もないという思いが錯綜し悶え苦しんだ。 俺が死んでも多分両親が悲しむだけで、他に誰も俺の死なんか悲しむ者はいない。敦子だって悲しまないのだ。
それならば、死ぬ前に敦子に“面当て”の遺書を書いておこう。 それがいま、俺にできる唯一の生の証しなのだ。傷つき死んでいく自分の残像が、彼女の心に刻み込まれれば本望というものだ。 行雄はそう思い、便箋を取り出すと敦子宛てに最後の手紙を書き出した。 少し前に、彼女の写真や手紙を全て廃棄したことで、彼の心はむしろ穏やかになっていた。
「先日は、あなたに大変失礼な手紙を書いたことをお許し下さい。でも、あれは僕の本心です。 この手紙があなたの手元に届く頃、僕はもうこの世にはいないでしょう。遠い宇宙の彼方から、この地球を眺めながら、あなたの幸せを願っていることでしょう。
僕は、革命にもこの世の生活にも敗れた脱落者です。 しかし、わずか十九年の人生だったとはいえ、僕はこれまで自分がやってきたことに何の悔いもありません。 しかし、僕は疲れた。この一、二ヵ月の苦痛、煩悶については、あなたには分かってもらえないと思います。
今はあなたの幸せを願い、あなたの心の中に、永久にこの哀れな僕が生き続けていくことしか望んでいません。 この一年以上、ありがとうございました。あなたは僕にとって永遠の女性でした。女神でした。本当にありがとう。
こうして最後の手紙を書いていると、涙があふれてきて目の前が霞んできます。 手が震え、上手に字を書くことができない。ごめんなさい。 でも、僕が永久にあなたの心の中に生きてゆけるのであれば幸せです。
心からあなたを愛します。最後にあなたを抱擁し接吻します。 あなたとの楽しい思い出を抱いて、僕はあの世へ行きます。いつまでも幸せに。 さようなら 敦子様 あなたの行雄より」
書き終った時に行雄は泣き崩れた。涙にくれながら敦子宛の遺書を胸に抱くと、彼はベッドの上に倒れ込んだ。 これなら、もういつ死んでもいいと思うと、かえって安らかな気持になり、彼は打ち続く苦悩と疲労からすぐに眠りについた。 そして、その夜、行雄は不思議な夢を見ることになった。
純白のローブを着た敦子と手を取り合って、行雄は天国へ上っていく。 二人はそのまま天空の彼方へ上っていくように見えたが、途中で敦子が制止した。 彼女はニッコリ微笑むと「ごらんなさい。あの美しい地球を」と言って、下界を指差した。
下界には、雲間から緑に輝く地球が見える。その美しさに行雄がうっとり見とれていると、敦子が優しくささやいた。「帰りましょう、地球へ」 行雄がためらっていると、彼女は彼の手を強く握り締めて下界の方へ降り始めた。
「待ってくれ、僕は天国へ行くんだ!」 行雄は叫んだが、敦子は彼の手をさらに強く握り締めると、どんどん下界へと引っ張っていく。 下降するスピードがますます強まり、敦子の純白のローブが風に翻る。
「待ってくれーっ!」 行雄が必死に叫ぶが、二人は矢のようなスピードで地球へ落ちていく。 丸い球体が、行雄の眼前に見る見るうちに迫ってきて、息がつけないほどになってきた。青く広がる大海原が二人を待ち構えている。「危なーいっ!」行雄が叫んだ瞬間、彼は夢から覚めた。
夢か・・・行雄はほっと胸をなで下ろした。彼は背中にびっしょりと寝汗をかいていた。 夢とはいえ、地球にフルスピードで落ちていった時は、なんと恐ろしかったことか。あのままいけば、海面に叩き付けられて即死するところだった。
敦子は俺が天国へ上っていくのを押しとどめ、地球に引きずり戻したのだ。 しかも今、俺は地球に叩き付けられずに生き残っている。彼女はもっと生きろということを、俺に暗示したのだろうか。 行雄は自分が見た夢を分析していた。胸に手をやると敦子宛の遺書がある。
そうだ、俺は昨夜彼女に遺書を書き、この世を去ろうと思っていたのだ。 しかし、彼女は夢の中でそれを制止したのだろう。あの夢のせいか、何かから解放されたような気がする。 俺は革命にも恋にも敗北したが、敗北したまま死ぬなということか。このまま死ねば“犬死に”ということではないか。 このまま死んでたまるかという思いが、行雄の胸中に湧き上がってきた。 それにしても、あの天空と地球はなんと美しかったことか・・・
その時、彼の脳裏に思いがけない発想が浮かんだ。 プラネタリウムへ行ってみよう。星を見るのだ、星を見て宇宙の生命と神秘を探るのだ。それが俺の救いになるかもしれない。 いまの自分には、他に何の救いの手立てもないのだ。そう考えると、行雄は藁(わら)にもすがる思いでプラネタリウムへ行くことにした。










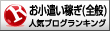















筆力があるので一気に読んでしまいました。馬鹿食いをしたかと思えば次はムプラネタリウムですか、案外人は他愛のない行為に癒やされ蘇るものかもしれませんね。
この辺は創作の部分が多くなっていますが、馬鹿食いや「友愛の家」、プラネタリウムと彷徨したのは事実です。青春の苦悩の軌跡と言ってよいでしょう。