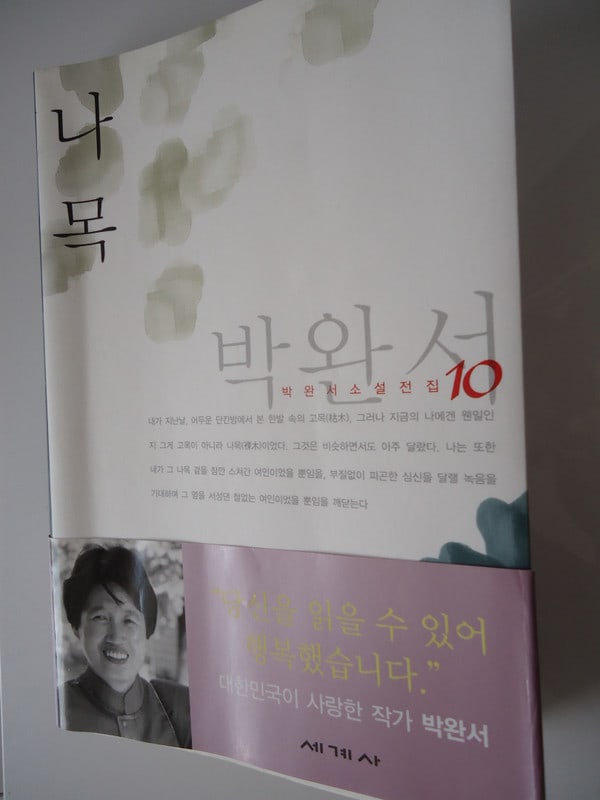翻訳 朴ワンソの「裸木」69
243頁3行目~247頁1行目
しかし、何を着ても優雅で端正な、比較できないほど寛大な彼女。しかし、私にとって今彼女は、オクヒドさんの情熱的な接吻を受けていた夢の中の彼女だった。
私は彼女に猛烈な敵意を感じた。憎悪で胸の中のすべてが荒々しくのたうちまわって、ついに憎悪が膨れ上がって全身に充満した。私は彼女に対する憎悪に満足した。ようやく彼女に対する私の感情が鮮明になったわけだから。そして私は、他人を憎むことがこんなにまでも満ち足りて、気分がいいということに初めて気づいた。
「お世話になりました。必ずこのご恩をお返ししますから、そう思ってください」
「何をいうの、キョンア…」
彼女は何かをやや低く言い続けたが、私は聞くふりもせず、靴のかかとで凍った土を元気よく叩きながら、路地を抜け出た。
他人を愛する時も、とうてい楽しむことのできないでいた充実感を、憎悪を通して得られたのだ。
私は車に乗らないでまっすぐ家へ向かった。もちろん彼女の願いのためではなかった。空気は冷たかったが、豪華で明るい朝だった。日差しが広がるとわりあい温かい秋の日だっただろう。大寒を過ぎてもう大分経つので、立春に近かったとか、過ぎたとか…私は今日が何日か考えようとしなかったのか、まるっきり思い出さなかった。
私はゆっくり長い路地を歩いて入って行った。垂直に屋根を仰ぎながら姿勢と呼吸を乱さずに、泰然と大門の前に立った。
東向きの古家は瓦にたっぷりの霜を被ったまま朝の陽光の中に粛然としていた。霜のかかった古家は比べ物がないほど美しかった。
私は、吹っ飛んだ屋根の一角の瓦と、泥土の塊と砕けた垂木の切れ端がゆらゆらと垂れている穴を、見たくなくても目をパチパチさせずにはっきりと見た。
「私のせいだったのかしら?」
躊躇しながら尋ねた。
「私のせいだったのかしら?」
もう少し大胆にその問題と対決した。
私が戦々恐々として怖がっていることは、実は砕けた屋根ではなく、まさに兄達の死が間違いなく私のせいだろうという呵責だった。兄達を表門の両側の部屋の押入れに隠そうと考え出したのは、まさに私だったから。
私は、兄達の死が私のせいだという思いが、発狂しそうなほど恐ろしく、その思いを追い出す代わりに、崩れた古家という新しい偶像を、畏敬するものとして仕えていたのだ。
まったく私が急いでその下級官吏の小部屋のような中に彼らを押し込めていなかったなら、その中で繰り広げられた凄惨さがどんなに衝撃的でも、崩れた屋根の前で長い間震えはしなかっただろう。
例え、片方の翼を失っても、残った軒は依然として空へ向かって、優雅な弧を描き、塀の石垣は長い年輪と戦火にもかかわらず、品位があって孤高を守っていた。
美しい古家。私は、父が次男であっても祖父が財産を分けた時に、他のものをすべて嫌がって、なぜかこの古家を相続したのかわかるような気がした。もう一度、
「私のせいなのかしら?」
私は、投げた質問の矢から十分余裕をもって退いた。
私のせいでも戦争のせいでも、ひょっとしたらそのような運勢なのかもしれない。
私は自分の過失を別な言い訳と一緒にすることで、自分が作った過失と同じぐらいつらくなったと信じたかった。
偶像の前で精一杯愚かに萎縮していた私は、真相の前でもう少し余裕があって狡猾だった。私は兄達の死に私を除いてもう少し別な言い訳もした。そして自分にはもう少し寛大になった。寛大というのはどれほど大きい美徳であろうか。
私は戦傷を受けた古家をようやく哀れみと愛情をもって眺めた。久しぶりに古家を古家として眺めた。
古家から自由になった私は明るい朝の日の光から、なまじっか春を感じるまでになっていた。しかし、私は大門を叩きはしなかった。私は背を向けた。
私が自分の過失に寛大になっても、母の過失にまで寛大になるわけはなかった。私は決して母を許すことができないのだ。
「どうして娘だけ遺してしまったのか」
その無情な記憶を二度と忘れないつもりだ。母は夜中に私の安否を心配しなかったわけで、私もやはり母の安否が心配なわけもないので、今更門を叩いて母に会わなければならない理由がなかった。
私はオクヒドさんの奥さんと別れた時のように、元気一杯で靴のかかとで地面を叩きながら、長い晩冬の路地を戻った。こつこつと爽快な音が聞こえて、全身が満たされたように活気が溢れた。
昼食時に休憩室で無心にお弁当をほどきながら、ちょっととまどった。キムチでないおかずが変だった。袋に入れた海苔巻き、豆の醤油煮、卵だ。オクヒドさんの奥さんの心のこもった巧みな手並みだった。
私は誇らしくゆっくり食事を楽しんだ。セールスガール達がしきりに出入りしても、お弁当を隠す理由がなかった。
ダイアナがとても大きな赤いバックを見事に肩にかけて入ってきた。
「今、昼食なの?」
彼女はたった今昼食を済ましてきたようだ。ルージュが剥げた唇をコールドですっきり磨くと、本来の唇より大きく大胆に真っ赤なルージュを塗って、顔を何度か叩いている間に指で目鼻の小じわをくるくると回しながらこすってからバックを閉めた。
「昨日はご馳走様でした」
私は自分が久しぶりにとても社交的になったと感じながら、昨日パンを食べた挨拶をにこやかにした。
「何…」
「お子供達とよく立ち寄るんですか?」
「子供達はパン屋に行きたがるけど、どこに暇があるの。昨日も何日か暇をねらっていて連れて出てきたのよ。連れて出てきても、どこか行くところがあった? 子供達が行くところよ」
「多くの大人が行く場合は街ですか?」
「多くじゃないわね。ダンスホールがないし、ホテルもないし、劇場もないし、口だけの戦争で、エンジョイする場所が多いのよ」
私は、自分が子供なのか大人なのかと思って力なく笑った。
せいぜい玩具屋の前から聖堂までを上ったり下ったりしただけで、大人達の本場には疎いまま、どれぐらい成熟した煩悩と歓喜を経験していたのか。
「お子供達、ハンサムでしたね」
昨日もそれを言ったようだが、また言ってやった。
「間違いなく夫に似ていないわ」
昨日もそれと同じことを聞いたようだ。
「お父さんは…あの子達のお父さんはどこにいるんですか?」
「ふーん」
「どうして亡くなったんですか?」
「死んだのかしらね。二つの目が元気に生きていたんだってよ」
「じゃ、一緒に暮らしているんですか?」
「あれまあいやらしい。この子は人を何だと思っているの、私がどんなにひどい売女かと思っているの? 夫を置いて情夫を、それもやたらに黒人白人と姦通して…」
彼女はむごたらしいように総毛立った。
「じゃ、子供達のお父さんは軍人で出征したんですか?」
「この子はだんだんひどいことを言うのね。私は夫を戦地に送り出して、その間に耐えられずに情夫を…」
「あ…わかりました」
彼女が同じ小言を繰り返そうとするや、私は慌てて遮った。
「何がわかったの? ふーん、あんたが何をわかるの。私の苦しい事情をあんたがどうしてわかるのよ?」