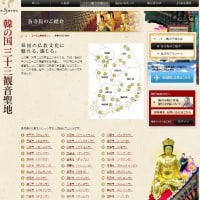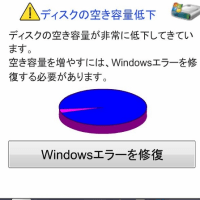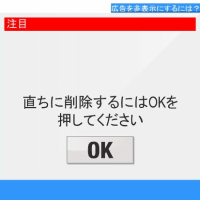漢方の先生が、NHKラジオで「未病は小火(ぼや)である」といった。それでインターネットを覗いてみた。
未病(みびょう)という用語は、黄帝内経で初めて使用された言葉とのこと。
1.既病(きびょう)とは、既に発病したこと、未病とは発病する前の状態を言いう。
日本未病システム学会では「自覚症状はないが検査では異常がある状態」と「自覚症状はあるが検査では異常がない状態」を合わせて「未病」と定義し、「自覚症状もあり検査でも異常が認められる状態」を病気(既病)と呼んでいる。
2.未病とは、肩こり、腰痛、便秘、不眠、20代より10Kg以上太った、検査値異常など、体が何らかのサインを出しているけれど、明確な症状がないため病院では病気と判断できないなど、このような状態を言います。
要するに、健康な人と、病気の人の間、半病人の状態のことです。 小生は、重症筋無力症の疑いで半年間通院や入院を繰り返したが、結局症状はあるが、病名を特定できず経過観察の身となった。まさに未病の極みといったところである。
現在、医師の手紙が送られてきており、これを持参して以前からかかりつけだった病院に通院し経過を観察することになった。
両眼複視は、原因不明が7割と言う、小生の場合には原因不明ゆえ全く治療がなされないので症状の改善は自然治癒を待つことのみである。
ありがたいことに、非常にゆっくりであるが回復基調にあるので、気分的にもずいぶん改善されている。
3.日本では貝原益軒が84歳にして著した「養生訓」に登場。
「聖人は既病を治すのではなく、未病を治す」
「聖人は未病を治すとは、病いがまだおこらざる時、かねてつつしめば病いなく、もし飲食・色欲などの内慾をこらえず、風・寒・暑・湿の外邪をふせがざれば、其おかす事はすこしなれども、後に病をなす事は大にして久し。
内慾と外邪をつつしまざるによりて、大病となりて、思ひの外にふかきうれひにしづみ、久しく苦しむは、病のならひなり。病をうくれば、病苦のみならず、
いたき針にて身をさし、あつき灸にて身をやき、苦き薬にて身をせめ、くひたき物をくはず、もにたきものをのまずして、身をくるしめ、心をいたましむ。」 こうなると、メタボなどはこの最たるものである。
子や孫たちに迷惑をかけないためにも、定期的な病院通いに加えて、生活習慣を変えないといけないのである。