ガリア総司令官二年目にしてユリアヌスはあらかたこの地を平定し、リヨン・オータン・ストラスブール・マインツ・ケルン・・・などに軍団基地を再建した。
一連の蛮族相手の大勝利の実績で、若き哲学者は部下の将兵から英雄と認められ、ローマ帝国の「インペラトール(皇帝)」とみなされた。しかし、みなされたのみであって、正式の皇帝になったわけではなかった。
民衆達から絶大な信望を抱かれたユリアヌスは、 住民の平穏な生活を取りもどしたのみはでは不十分で、住民の活気を取り戻さねばならなかった。
このためには、法と徴税の公正な実施を実現することが一番だと彼は考えた。 ローマ帝国末期のこの時代は、紀元前の光り輝いていた元首政時代とは全て反対の考えが支配していた。
ローマ帝国が光り輝いていた頃の税制は、シンプルかつ広く浅い徴税と前に書いたが、これを具体的に説明する。
元首政時代のローマでは、「国家」は「納税額の範囲内」でやれるだけの事をやり、「地方自治体」もまた同様であった。そして足りない分は、「私」が補うという税の考え方であった。
その一例として、帝国の高速道路といわれるローマ街道網は、「国」が8万km、「地方自治体」が15万km、そして「私」が敷設し開放したのが7万kmで、建設以降のメンテンアンスもこの分担だった。
(「私」が公益に関する義務感を強く持ち、それを誇りとして行うという高邁な心掛けに溢れていた時代だったからこそ可能だったのであるが。)
このような仕組みのため、直接税は10%、関税15%、消費税(売上税)1%というシンプルな税制と広く浅い三本立ての徴税であった。
ところが、後期のローマ帝国は、社会貢献や寄付をするという崇高な精神はどこかに消え、さらに兵士と行政官僚の数を倍増したので、当然歳出も倍増したのであった。 その上、ライン河やドナウ河流域の蛮族による破壊で主要産業の農業の生産性は著しく低下し税の減収を生じた。
これらの事が特別税をはじめとし、税制は複雑化の一途を辿り「広く浅く」から「狭く厚い」税制となった。 当然のように、官僚達は、特別税なるものを捻り出すことになった。
ユリアヌスは、官僚達がもっともらしく提出した特別税案を決然と拒否したのであった。
さて、ユリアヌスは、このような難局といかに戦うか、次のテーマは「ユリアヌスの改革」とする。
長々とお付き合い頂いてきたが、次回が小生の書きたかった第一番目の山場なのである。
追記;ローマ帝国末期は、なんだか現在の日本に似ている気がしてならないのである。
おまけ:
今回は、メル友が紹介してくれた、アルザス地方の民族衣装をご紹介する。
一部分英語で残りはフランス語である。写真だけ見ていただければよいと思う。
日本の着物もそうであるが、いずれの国の民族衣装も美しい、伝統が培った美を堪能して頂きたい。
http://costumes.alsace.site.voila.fr/historique/en/index.html











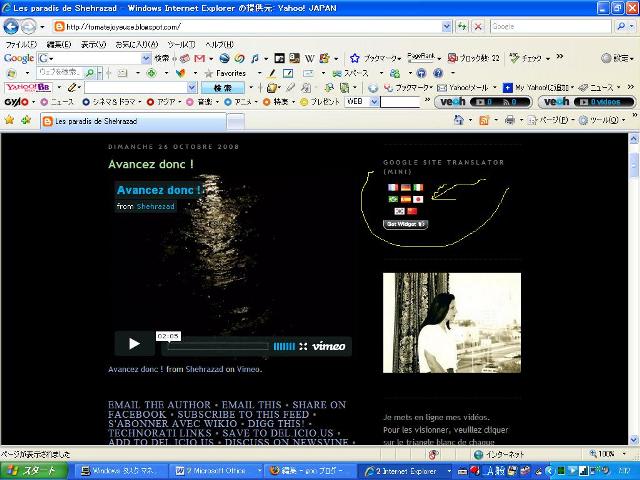



 ケーキ屋の店先
ケーキ屋の店先


































