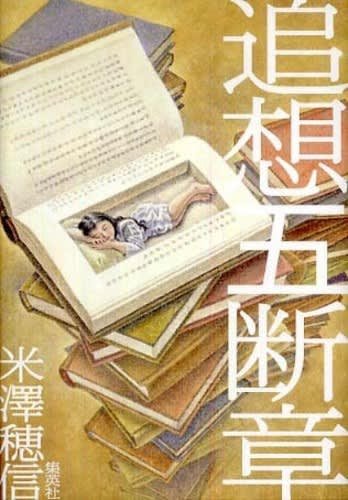09年11月号「一回どう?」はこちら。
 「一つの試みとして、4月公開『シャッターアイランド』で、より分かりやすい、伝わりやすい業界初の“超日本語吹替版”を制作して、新しい洋画ファン獲得の足掛かりにしたい」
「一つの試みとして、4月公開『シャッターアイランド』で、より分かりやすい、伝わりやすい業界初の“超日本語吹替版”を制作して、新しい洋画ファン獲得の足掛かりにしたい」
パラマウントピクチャーズジャパンのラインナップ発表会にて高田和人マーケティング本部シニアマネージャーが。
……いつか誰かがこんな発想になるんじゃないかと思ってた。洋画の(特にハリウッドの)興行収入が下がり続け、しかし邦画が絶好調であることで“わかりやすい”“伝わりやすい”吹替に……要するに寒いギャグとかをオリジナルにこだわらずに入れていこうってことだろ?芸人も多数起用して。賭けてもいい。そんなことをやっていたら洋画興行は破滅するぞ。
「なにが夫婦放談だって(笑)」
山下達郎と竹内まりやがFMの放送で同時に。「サンデーソングブック」でこの企画をやり始めて、もう十数年になるのだとか。それで驚いてはいけない。大滝詠一との放談は二十年以上!。どうかいつまでも。どうか死が二人を分かつまで。
「(スーザン・)ボイル? 目玉は日本にいる人間で作らなきゃ」
和田アキ子の紅白に関する発言。もうみんな気づいていることと思う。芸能マスコミは“便利だから”和田という装置を使ってさまざまな意思表示を行っているだけだ。そして和田自身はみずからが文字通りゴッドにでもなった気でいる。本気で(“事務所の意向”なんてものにふりまわされず)芸能ニュースをやろうと思うメディアはないのか?
10年1月号「内閣の弱点」につづく。











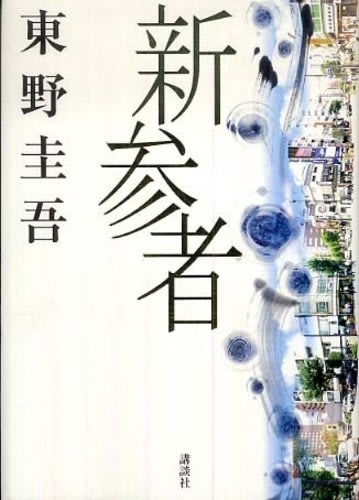


 今回の犯人はフットボールチームのGM(ゼネラルマネージャー)。チームを愛し、スポーツを愛するこの男(
今回の犯人はフットボールチームのGM(ゼネラルマネージャー)。チームを愛し、スポーツを愛するこの男( 決め手になったのはGMがかけた電話に「入っていた音」ではなくて「
決め手になったのはGMがかけた電話に「入っていた音」ではなくて「