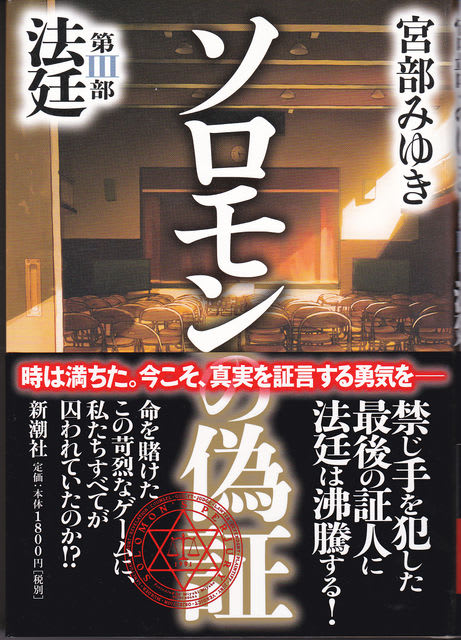そうか今日で「笑っていいとも!」終わっちゃったんだ。80年代は毎日録画して見ていたくらい耽溺していたのに、いつのまにか(中年になったってことでしょうかね)まったく見なくなってしまっていたのはなぜなんだろう。一種の権威になっていたことは確かにしんどかったけど。
そうか今日で「笑っていいとも!」終わっちゃったんだ。80年代は毎日録画して見ていたくらい耽溺していたのに、いつのまにか(中年になったってことでしょうかね)まったく見なくなってしまっていたのはなぜなんだろう。一種の権威になっていたことは確かにしんどかったけど。
前にタモリを特集したとき、深夜芸人だった彼が生き残れたのは自分の色を消したからだと不遜なことを申し上げた。その思いはいまも変わらない。徹底して攻撃型の芸人である明石家さんまとのトークが成立していたのは、彼が事実上なにも言い返さなかったからだ。絶妙の返しを発するチャンスはいくらでもあったはずなのに(「タモリ倶楽部」ではそれが健在なので、できなかったはずはない)、彼はおとなしく仕切るだけだった。
わたしが驚愕したのは、芸人の登竜門にまでなったあの番組を凌駕したのが、日テレのみのもんたの番組だったこと。ある意味、おもいっきり下品な路線をとったあの番組が“主流”になるあたりに日本のテレビの不幸はあったと思う。
わたしは「笑っていいとも!」のすべてが素晴らしかったとは言わない。フジテレビのバラエティ制作能力がどんどん落ちていたのはみんな承知の上だろうし、キャストの選択もまた、疑問符がつくことが多かった。
でも、テレフォンショッキング(すでにこのコーナー名がしゃれであることが美しいと今では思う)という、「徹子の部屋」と同様の企画でありながら、ステージに並ぶ花やメッセージなど、これが芸能界なんだという事情をあからさまにしたのが、芸能界にもっとも向かない人間の番組だったことは意味があった。
つまり無意味ではないかと。わたしが最も笑ったのは、このコーナーにおいて、間違い電話のせいで素人たちがテレフォンショッキングに一週間訪れたことがあって、タモリはいつものようにそれを仕切っていたのだ。あの人は芸能界をなめきっている!
三十年以上もこんなばかげた祝祭をつづけながら、なお普通の神経を保っているのは、彼の神経の強靱さと、繊細な計算があったからに外ならない。しかし残念なのは、結局はわたしがテレフォンショッキングに出演できなかったことなのよね(笑)。みんな一度は“自分がタモリと対談”するとしたら、って考えたことあるでしょう?










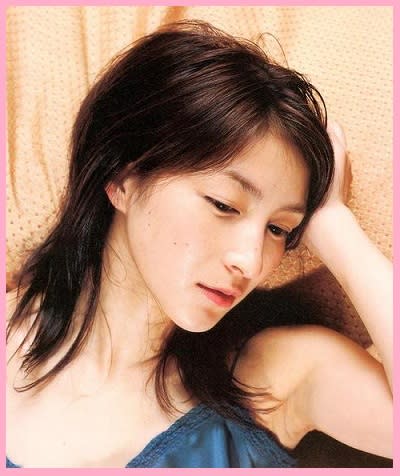

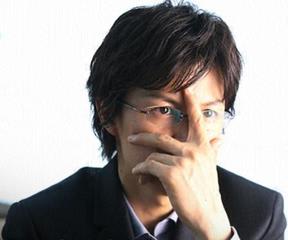


 恥ずかしながら告白すると、わたし、中学のころにいちばんなりたかった職業は
恥ずかしながら告白すると、わたし、中学のころにいちばんなりたかった職業は
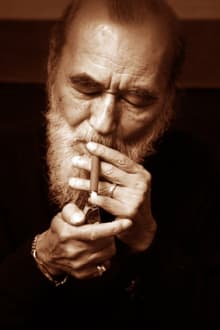 第十一話「命がけの宴」は
第十一話「命がけの宴」は