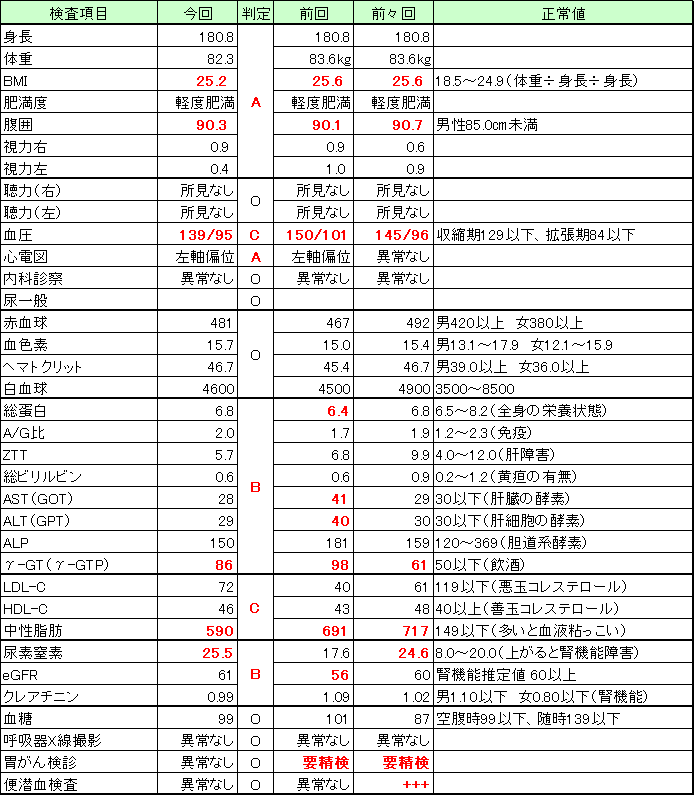第三十七回「信之」はこちら。
今日はタイトルどおり真田昌幸(草刈正雄)の最期。九度山に蟄居させられてからの十年を一気に。
この大河をこれまでリードしてきたのは草刈正雄。誰だってそう思っている。あの美男なだけだった男が、古畑任三郎の神の回「ゲームの達人」を経由してここまでの役者になった。代表作を問われれば文句なく「真田丸です」と答えることができるのだ。もって瞑すべし。いや草刈さんは死んでないですけど。
前回の視聴率は17.3%と的中。昌幸だけでなく、本多忠勝(藤岡弘、)、加藤清正(新井浩文)までが退場。代わりに登場したのが大人になった秀頼(中川大志)。堂々たる偉丈夫。だからこそ家康があせるというのはわかりやすい。自分の息子(星野源)よりもよほど有望なので(笑)。
久しぶりに歴史オタク教師から関ヶ原総括が。特に今回まったく登場しない北政所(鈴木京香)がらみは参考になった。
・実子がいなかったことで、客観的な判断ができた人だった
・血族が秀吉のせいで不幸になっていくことで、より冷めた目で世の中を見た
・大恩ある織田家の様子を見ていて、平和のために権力が移ることに抵抗感がなかった
……なるほどなるほど。特に秀次の扱いで豊臣という存在を客体化し、それ以上に、本人の意向はどうあれ“そうあったのではないか”と徳川が煽ったというのはいかにも。
同じように床につきながら、妻の薫(高畑淳子)は信之(大泉洋)のもとで食欲ありあり。夫の昌幸は信繁(堺雅人)のもとで死んでゆく。長男が捨てざるをえなかった“幸”の字を受け継いでくれという運びは泣ける。そう来るかあ。だから二週つづけて人名がタイトルなんだね。
昌幸が信繁に託した策は驚天動地のもので、同時に現実的だ。十年かけて考えた策が、息子に受け継がれていく(微妙にねじれていくのだけれど)ことを確信しながら冥土に旅立ったのだ。総括すれば確かに晩年は恵まれなかったかもしれないけれど、この十年を「どう徳川を倒すか」だけに傾注。幸せな人生ではないでしょうか。
孫(彼もまた悲劇的な最期を迎える)に、いじめっ子への対策を授けて倒れる展開は、もちろん「ゴッドファーザー」のマーロン・ブランドを意識したのでしょう。すばらしい演技だった。草刈正雄のこれからに期待。今回は絶対に18%台!
第三十九回「歳月」につづく。