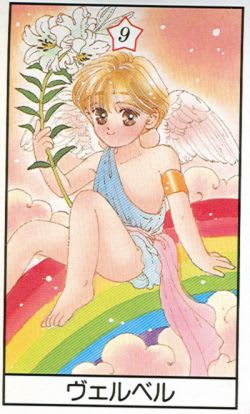(画像はクリックされましたら拡大します。)
某少女雑誌におけるシリーズで、過去に少女達の間に
小さな妖精ブームがあったものの、反対にこの「妖精
シリーズ」の終盤当たりに若干登場した「天使シリーズ」の
方は殆ど注目されないまま終わってしまったように
記憶しています。
画像の方は、その中の小天使の一人、「ヴェルベル」のカードです。
この天使シリーズの中で、「小天使」は一般の天使を大人と
すると、丁度「子供」に相当する存在と説明されています。
このシリーズの中で、(小)天使について説明されています。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"てんし"という漢字は「天の使い」と書くでしょう?
その字の通り、天にいる神様の心を伝えたり、人間のお願い事を
神様に伝えたりという、お使いの役目についたのです。
人間は神様を直接見る事は出来ません。
恐れのあまりに死んでしまうからです。
だから、神様との間を取り持ってくれる存在がどうしても必要なのでした。
小天使達は、私達の精神面や生活面で、事細かに見守っています。
彼らは目には見えにくいでしょう。
でも、あなたが何かに頑張っている時は、必ずそばで応援して
いてくれます。
小天使達は頑張る人が大好きなんですもの。
カードに登場するのは、女の子ととても相性のいい小天使ばかり。
小天使とお友達になりましょう!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
80年代後半~90年代初頭に全盛を迎えたこの雑誌の妖精
シリーズも、90年代も中頃になると、時代も変わってあまり
注目されなくなったようです。
現在ではそうしたものの面影がないほどこの雑誌も変貌して
しまいましたが、90年代まではまだ妖精や天使が登場して
少女達に美しい心を保つ努力の必要という事を教えていました。
この「ヴェルベル」という小天使というのはわたくしにはあまり
わかりませんが、マイバースデイの本には以下のような説明が
ありました。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【小さな試練を与える天使 ヴェルベル】
人間は、いい事ばかりでは成長しません。
時には苦しい事を乗り越えるのも、必要です。
ちょっぴり落ち込む事や残念な事を起こして、私達の心を
鍛えてくれる天使の一人がヴェルベルなの。
手に持つユリは試練に耐えようとする人の純粋な心を表して
いるの。
雨上がりの午後、窓からヴェルベルにお祈りすると、苦しい事に
耐える勇気が得られるはずよ。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
このカードの絵柄などは、わたくしから見て非常に90年代的
ですが、それでも言っている事などは正しいように感じます。