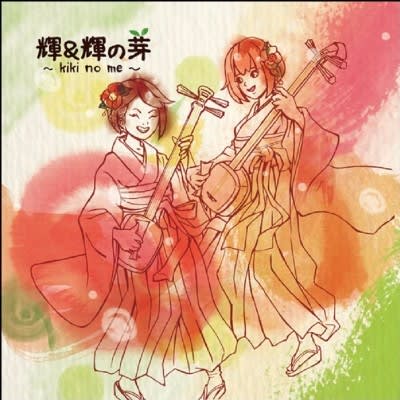P-200の配送は代引だったため曜日時間指定でお願いしたところ、配送待ちで寒い倉庫に寝かされたらしく、
クール便で届けられたとおもうほどキンキンに冷えた状態で我が家に到着しました。
さわると金属の筐体が長く触っていられないほど冷えており、結露必至だったので、しばらく室温の低い寝室で放置。
付属の電源ケーブルだけ暖かい部屋においていたら、電源ケーブルが結露しましたwww
外観をチェックしましたが、天板の大傷はあらかじめ写真で分かっていたので、まあよし。
天板は見えないようにセッティングするつもりなので、特に問題ありません。
気になっていたフロントパネルは、確かに正面から見れば傷はわかりますが、斜め上から見るとそれほど気になるほどでもなかったので一安心。
結露の心配をしなくてすむ程度に本体が温まったところで、PC部屋に入れて仮置きで接続してみました。
電源ケーブルは付属のものを使用せずに、ミニアンプの電源用にとりあえず使用していたSilverDragonのものを使用。
P-200付属ケーブルはミニアンプの電源用に回しました。
P-200の付属の電源ケーブルはそれなりの太さですが、結構柔らかく取り回しはよさそうなです。
ただし、ラックスマン製品の多くに付属している純正のJPA-10000という電源ケーブルではなく、汎用品のようです。
JPA-10000のプラグとインレットにあるラックスマンのマークがなく、プラグのブレードも真鍮でした。
BabyfaceとATH-2000ZをP-200に接続して、ドキドキしながら音出し。
うむ、Babyfaceのヘッドフォン端子と大差ない。
というか輸送直後ということもあり音が安定していない感じがしたので、P-200の電源を入れっぱなしにして翌日確認。
なんかBabyfaceのヘッドフォン端子のときと出てくる音の傾向が変わってしまいました。
非常に滑らかで繊細な音になりましたが、ATH-2000Zの特徴である高音の伸びがなくなってしまった。
Babyfaceのヘッドフォン端子接続の時に若干感じていた高音の刺激成分は一切感じなくなったのはいいのですが、ATH-2000Zの持ち味が生かされていません。
一番の問題はボーカルが奥引っ込んで前に出てこない。空間の広がりはよくなるどころか、むしろ狭く感じる。
これはまずい。P-200とATH-2000Zの相性悪いのか、俺はやっちまったのか。
一瞬考えて、とりあえず電源ケーブルを交換してみました。
今までPC用に使っていたshima2372の電源ケーブルをP-200に接続し、PCにはSilverDragonでは長さが足りないので、P-200の付属ケーブルを回しました。
改めて音をチェック。音が激変といっていいほど変わりました。
Babyfaceのヘッドフォン端子に接続したときと同傾向ですが、低音はしっかり駆動されているらしく、さらに締まってタイトな方向に変化しました。
問題のボーカルが埋もれず、ちゃんと前に出てきたので一安心。高音の伸びも復活しました。
そういえばSilverDragonの線材は細線をたくさん使った構造だったような気がする。
確認すると使っていたSilverDragon Power cable は、直径14mm 極細素線 0.12mm×224本という構造でした。
こういう素線に極細の線材をたくさん使っているの電源ケーブルは音が繊細でおとなしくなる傾向っていうのを何かで読んだ気がする。
まさにそんな方向の音の変わり方でした。対してshima2372の方はベルデンの19364のはずです。
芯線の構成までは分かりませんが、見た感じそんな細い素線ではないようです。
電源ケーブル一本でこれほどまでに音が変わるなんて、P-200恐ろしい子!
P-200用の電源ケーブルはshima2372に変更し、SilverDragonは元通りミニアンプの電源用になりました。
さて、P-200用の電源ケーブルが一応決まったところでセッティング。
P-200はフルサイズではないもののB4サイズなので、それなりに場所をとります。
P-200をPCモニター台にして、P-200に直接モニターを載せてしまおうかと思ったのですが、
P-200の発熱も多少気になるので、PCモニター台を導入して、その下にP-200を収めることにしました。
モニター台はサンワサプライのMR-LC102というのが棚板の高さが調節できて、大きさもちょうどよさそう。
実際セッティングをしてみると、デスクの幅が少々足りず、モニター台の棚板とミニアンプ用の電源が干渉してデスクからはみ出してしまうので、
モニター台とスピーカースタンドの両方の下に自作インシュレーターを挟んで高さを調整しうまく収まりました。
スピーカースタンドの天板下にちょうどモニター台の脚が入れることができたので、奥行きも足りました。
そうして、いままでPCデスクに散らばっていた周辺機器をうまいこと並べなおしたのが、下の状態。

ヘッドフォンハンガーに掛けたヘッドフォンがスピーカーにかかっていたので、自作インシュレーターの余りとCクランプを使って回避。
モニター台にモニターを載せるとモニターの画面が高くなりすぎるかなと思っていたのですが、
たまたま新しくしたばかりのEIZOのモニターが画面の高さを調節できるタイプだったので、
ギリギリまで低くすると今までの高さと大差なく首が痛くならなくて済みそう。
今まで奥にあって電源のオンオフがやりづらかったBabyface用電源も手前に持ってこれたし、
Babyface接続しているBus-Power ProもBabyfaceと直線的に並べることができて配線がかなりすっきりしました。
モニターの画面がスピーカーにかかっているのは今までと同じですが、ウーハーにギリギリかからない位置にできたのでその点もよかったです。
PC用の外付けHDDはモニター裏からPC上へお引越し。これで使い勝手がよくなりました。
このセッティングをして改めて気付いた点がひとつ。
ヘッドフォンとスピーカーのボリュームはそれぞれヘッドフォンアンプとミニアンプ側で調整するので、
Babyfaceは固定でいいのですが、出力がスピーカー用のライン出力のみとなります。
今まではBabyface のセレクトボタンでヘッドフォンとスピーカーの出力を切り替えて使っていました。
その切り替えが不要になったのはよかったのですが、ヘッドフォン使用時にサブウーハーから音が出てしまうのです。
P-200のスルーアウト端子はP-200の電源オンでオフでも機能します。
普段はサブウーハーのボリュームを絞っておいて、スピーカー使用時だけボリュームを調整すればよいのですが、
サブウーハーのボリュームがサブウーハー本体の裏側にあり、ボリューム調整が面倒です。
そもそもサブウーハーを導入したのがスピーカーをLS-K731に変える前で、
スピーカーをLS-K731に替えたら、サブウーハーなしでも十分低音が出るようになったので、正直サブウーハーの必要性はあまり感じていなかったのです。
接点とボリュームが1つ増えることもあり、サブウーハーを外すことにしました。
Babyface+P-200+ATH-2000Zという組み合わせになってしばらく聴き込んだのでその総括をすると、「効果はあったが限定的」という感じでしょうか。
電源ケーブルをshima2372を変えてからは、Babyface直挿しと同傾向音色になったものの、低音の制動力が増し、より低音が引き締まる傾向になったのと、
やや空間に広がりが出たかなという程度で、劇的な効果は得られていません。
その原因を考えてみたのですが、BabyfaceはすでにBusPower-Pro+フィデリクスACアダプターを導入済みで電源が強化されていたことに加え、
Babyfaceのヘッドフォン端子の出来がよかったのだと思います。ATH-2000Zがインピーダンスが40オームと低く、鳴らしやすいということもあると思います。
もしP-200を新品で買っていたら、コストパフォーマンスとしては大失敗ですが、
中古で新品の半分以下の値段で手に入れているので、まあなんとか納得できるレベルになっています。
ボリュームにかすかにガリがありますが、使用にはほとんど支障ないレベルなのでこのまま使用を続けます。