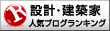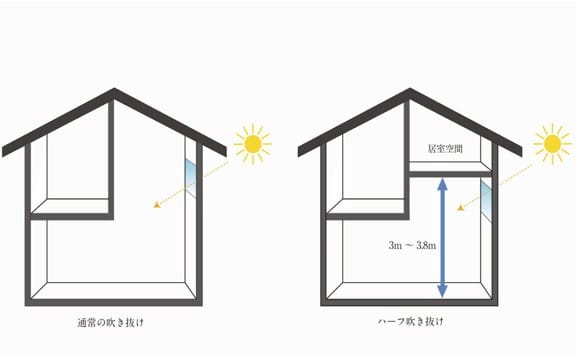ウッドデッキのある家
を計画する際に
考えておくべき情報整理。

※ウッドデッキのある家ビルトインガレージの家外観
家づくりを考える際、
多くの人が「ウッドデッキ」の設置を
検討します。

※リビングから続くウッドデッキと芝生の広い庭をアウトドア空間として楽しむ暮らし
実際にホームページの
お問合せからも
庭や家のリフォーム計画を通じて
ウッドデッキ計画の
ご質問等を
新規でいただ事も多いです。

※天然木を「R加工」して二段式の階段をベンチにも出来る工夫
オシャレな暮らしの
イメージや
見た目の良さ、
アウトドアスペースとしての
活用など、
魅力がたっぷりですが、
実際には設置後の
メンテナンスや使い勝手
コスト面の
事前考慮も重要です。

※リビング側からウッドデッキの間はストリップ階段で視界を調整し憩いの場になる工夫を提案

※夜は風景としても楽しむエリアになるように設計
今回のblogでは、
「ウッドデッキ」を
取り入れた
暮らしの魅力や
デメリット、
設置の際に
注意すべきポイントを
少し書いてみたいと思います。

※平屋の数寄屋の家にも濡れ縁では無くウッドデッキとして提案(但し人工木デッキ)
ウッドデッキの魅力。
ウッドデッキは
BBQスペースとしても最適で、
外観の美しさもそうですが
使い勝手の良いスペースに
計画する事で
機能性もよりよくなります。

※風景を楽しむ場所でありリビングからの繋がりを意識したレイアウトと実用的な使えるカタチ提案
以下で少し、
ウッドデッキを
設置することで得られる
具体的なメリットを。

※LDKから近い位置関係にウッドデッキをつくる事で身近に使える配置関係に
家族で過ごす
第二のリビングスペース。
ウッドデッキは、
リビングからつながる事で
アウトドアリビングとして
活用できます。

※LDK・キッチンからも移動しやすい事でブランチスペースやBBQの際にも活用しやすい位置関係に
休日のブランチを楽しんだり、
子どもが遊ぶ
スペースにしたり、
ペットのくつろぎの場にも
最適です。
※ハンモックやアウトドア家具も重要なアイテムです。
家全体の雰囲気とデザイン性。
ナチュラルな木材は、
家の外観を
演出します。

※裏庭に面する一面に計画したウッドデッキスペース・植樹スペースを兼ねるエリア
ウッドデッキがあるだけで、
家全体が一段と
魅力的にも見えます。

※裏庭全体を楽しむスペースとして計画する際に連動するウッドデッキスペース
庭との調和も取りやすく、
四季折々の風景を
楽しめます。

※LDK空間とつながるウッドデッキスペースは庭への出入りや庭の鑑賞スペースになる位置付け
家の価値を高める
ウッドデッキを設置することで、
家の付加価値が
向上します。
特に、
中古住宅市場では
「ウッドデッキ付き」という
条件が
バイヤーにとって
魅力的に映ることもあります。
簡単なDIYでアレンジ可能
ウッドデッキは、
家具や植物を置くだけで
簡単に雰囲気を
変えることも出来ます。
ライトアップや
パーゴラの設置で、
夜の時間も活用できます。
グランピングスペースの
一部にもなりますし
計画性や間取りとの
相性にもよりますが
過ごす場所としての
快適性もよくなります。
ウッドデッキのデメリット。
ウッドデッキには
魅力がたくさんありますが、
慎重に検討すべき
デメリットも存在します。
設置後に
後悔しないために・・・・・。
メンテナンスが必要。
木材は定期的な
手入れが欠かせません。
塗装や防腐処理を怠ると、
腐食の原因になります。
特に雨や湿気の多い
地域では、
年に一度か二度の
メンテナンスを
行う必要があります。
設置コストが高い。
ウッドデッキの設置には
材料費と
施工費がかかります。
さらに、
高品質な木材を選ぶ場合や
広いスペースを
確保する場合は
コストがさらに上昇します。
天候の影響を受けやすい。
直射日光や
雨にさらされる
ウッドデッキは、
木材が反りやすいという
特性があります。
そのため、
日よけや屋根の設置も
最初の段階から
検討する必要があります。
長期的な耐久性の問題。
天然木材は
耐久性が心配です。
年数が経つと、
シロアリ被害や
腐食が発生するという
リスクがあります。
そのため、
メンテナンスの頻度を
見越した
設計が求められます。
ウッドデッキ設置のポイント。
素材選びがカギ。
ウッドデッキの素材には、
天然木材
※ウリン、セランガンバツなど
そして人工木材(樹脂デッキ)が
あります。
天然木材は
自然な質感が魅力ですが、
人工木材は
耐久性やメンテナンスの
容易さで優れています。
設置場所の検討。
ウッドデッキを
どこに設置するかも
重要です。
日当たりや
風通しの良さを考慮し、
家族のライフスタイルや
土地の特徴を加味した
配置を計画する事が
重要です。
ウッドデッキのある暮らしを
楽しむアイデア。
ガーデニングスペースに。
鉢植えや
プランターを並べて、
緑豊かな空間を
演出する事も
室内からの眺めや
外観を含む眺望にも
プラスの要因になりますし
簡易的ですが
花や野菜を育てる
楽しみが加わります。
家族のBBQスペース。
ウッドデッキは、
アウトドアクッキングにも
ぴったりのスペースです。
専用のグリルを
設置すれば、
家族や友人と
気軽にBBQを楽しめます。
テレワークスペースにも最適。
ウッドデッキに
屋外用のテーブルと
椅子、日よけや
落ち着くことが出来る
目隠しを置けば、
屋外でも読書や仕事ができます。
リフレッシュ効果が期待でき、
生産性もアップしやすくなる
という統計DATAも
存在します。
ウッドデッキの設置は、
暮らしの空間において
快適なアウトドアライフを
提供する
素晴らしい方法です。
ただし、
素材選びやメンテナンス、
コスト面の考慮が
必要です。
この記事で紹介した
メリット・デメリットや
設置のポイントを
参考にしながら
家造りについて
理想的な
ウッドデッキライフを
実現できるようにと思います。
日常をよりよく楽しむ
週末住宅のような暮らしに
ウッドデッキのある
環境デザイン提案。
皆さんは
暮らしの目的に
何を意識しますか?。
住まいの新築・リフォーム
リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
ホームぺージ・Contact/お問い合わせフォームから
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
https://www.y-kenchiku.jp/
-------------------------------------