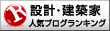二世帯住宅で「安心・快適」な
ライフスタイルを実現する
という選択肢もあります。

※やまぐち建築設計室の二世帯住宅・同居の為のリーフレット
親世帯と子世帯が
ひとつ屋根の下に暮らす。

二世帯住宅を計画された
※オフィシャルホームページへのリンク・二世帯住宅をリノベーションで計画した住まい手さんからのお手紙
二世帯住宅に関しては
デメリットクローズアップが
大々的にされることが多いので
デメリットのことばかり考えてしまい、
同居することを
ためらっていたかも知れません。
しかし近年は、
それぞれがお互いのメリットを求めて
積極的に同居する
という価値観も多い時代になりました。
家事や育児の分担・協力ができ、
心身ともに
サポートしてもらうことが
可能になるケースも多くなりました。
近くに頼れる相手がいる
というのは
心の支えになりますので、
二世帯住宅は
とてもメリットの多い
住み方であるとも言えます。
二世帯住宅を建てるポイントは
「距離感」です。
親が所有する土地を分割して、
親世帯と子世帯
それぞれに住まいを建てるケース。
親子共同で土地を購入して
建てるケース。
さまざまな
同居のスタイルがあります。
また、
両親の退職や
子どもの入学等のタイミングで、
二世帯住宅にして
同居を考えている
というご家庭は少なくありません。
共働きで忙しく働く
子育て世代にとって、
子どもの世話を助けてくれる
両親との同居は
メリットも大きく感じます。
しかし実際には、
ライフスタイルの異なる世代間の
同居にはデメリットもあり、
ストレスなく暮らせるかどうか
不安かと思います。
昔、住宅雑誌企画での
対談会・座談会やインタビュー記事の際にも
話したことがあるのですが
正月やお盆休み、GWだけではなくて
一か月ほど仮同居をしてみてくださいと
お話しをしたことがあります。

※座談会

※座談会記事・二世帯住宅計画の事も座談会では話題に
イメージと実際の生活環境を
整える意味で。
そうすると二世帯同居に関しての
問題点の解決策も
見えやすくなりますから。
互いに気を使うよりも
それぞれの親子間での
生活文化の違いを
事前に受け入れる。
そういう意味です。
適切な距離感を保つことで
デメリットを解決し、
メリットをより大きくできます。
それぞれのライフスタイルに合わせた
間取りとプランニングで、
家族が幸せに暮らせる
家づくりを実現できるように。
そんな間取りの工夫にも
要約すると様々な間取りの分類が出来ます。
○完全同居タイプ
玄関・リビング・ダイニング・キッチン
水回りなどを共有した
間取りです。
常にお互いの気配を感じられ、
祖父母と子ども(孫)との
交流も頻繁にあるため、
家族の絆も深まるケースもあります。
子育ても含め、
家族で一緒に過ごす感覚が
強くなる一方で、
プライバシーは守られにくい
というデメリットがあります。
夫婦どちらかにとっては、
義理の両親との生活になるため、
お互いに気を遣いあうシーンも
多く出てくる可能性があります。
また、
光熱費を含む生活費が
共同となるため、
費用負担を
はっきりとさせておく必要も出てきます。
○部分共有タイプ。
玄関など一部の
設備を共有しながらも、
キッチンや浴室など
生活空間は各世帯に
それぞれ設けるかたちです。
1階・2階で分けられるケースが多く、
それぞれの気配を感じながらも
適度にプライバシーが
守られます。
キッチンや浴室・洗面
トイレなどの水回り設備が、
世帯ごとに独立しているため、
生活する時間帯がずれても
心配することは少ないプランになります。
玄関が世帯共有なので、
子どもたちが
学校から帰宅したときも
祖父母が出迎えてくれることで
安心感も増します。
部分的に
共有している場所があることで
電気代などの
光熱費負担の振り分けが
難しい点などデメリットもあります。
また設備が二つずつ必要になる分、
建築費用が高くなります。
○完全分離タイプ
同じ建物内に暮らしていますが、
玄関をはじめとした
すべての設備を分けた
間取りの二世帯住宅のことです。
左右分離又は
1階・2階で分けられる
というパターンがほとんどです。
完全に生活を分けているため
プライバシーは守りやすく、
いざという時は
コミュニケーションを取り、
お互いをサポートしやすい環境です。
光熱費や生活費も
完全に分けることができるため、
費用負担の問題は解決できます。
※法律上は長屋又は
重層長屋として取り扱うケースになります。
しかし、
子育てのサポートの面では、
完全同居タイプ
部分共有タイプに比べると
相互サポート力はさがってしまいます。
また、部分共用タイプと同じように
設備が各世帯に必要なため、
建築費用が高くなる傾向にあります。
※長屋の法律上「界壁」も必要。
子育て世代が
親と二世帯住宅で暮らすには、
さまざまなハードルや
不安があるかともいます。
単世帯・核家族の住宅と同じく
二世帯住宅には、
メリットもデメリットもあります。
また家づくりには、
親子でもきちんと話し合い、
それぞれの家族内で
決めるべき事柄もあります。
家族みんなが寄り添い、
笑顔で暮らすためには、
家族がいつも一緒
だけではなくて
ほどよい距離感が必要だと考えます。
お互いのライフスタイルや
プライバシーを考慮しながら、
家事や育児を
サポートしやすい
二世帯住宅での暮らしを考えてみませんか?
ご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
-------------------------------------