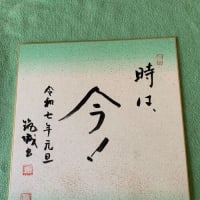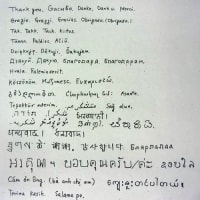ヘリコプターまで行かなくても、救急車で来院したり、救急車で搬送するケース、医療をする上では、欠かせない。
ヘリコプターまで行かなくても、救急車で来院したり、救急車で搬送するケース、医療をする上では、欠かせない。 横浜市と言えば、人口360万程の大都市。そこでは、救急車が62台あり、普段、40台ほどが稼働している。
で、何と、消防指令センターに、1日に650件もの電話の要請があるとのこと。つまり、2分に1件だ。しかも、それが増加傾向にある。
高齢化の増加に伴って、急病での搬送が多くなっている。このまま行くと、対応が間に合わなくなる恐れもある。
要請の中には、「鼻水が止まらない」「しゃっくりが止まらない」「便秘が3日も続いて、お腹が痛くてしかたない」ってケースもあり、時に、行くと、「ペットの動物!」だったりする。(動物は、救急車では、運べません!)
約、4分の1が、救急でないとのこと。
消防指令センターで対応する職員の深刻な悩みは・・・→連絡がはっきりとれない状態で、急に電話が切れてしまう場合。つまり、電話をかけて来た人が、連絡しようと思っても、状態が悪くて、・・・電話口に出れない状態を想定して、それを確認しないといけないこと。
119に電話した人は、間違えたと思って、思わず切ってしまうことなく、その旨をしっかりと伝える義務がある。
医療では、資源に限りがあります。救急医療はもちろん、救急車においても、それを利用する側にも、それなりの適切な判断が必要と思われます。