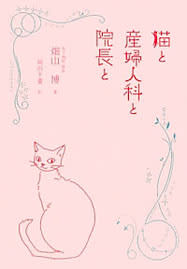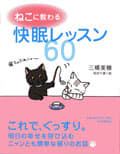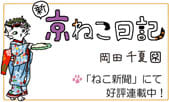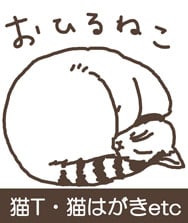ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ
猫と千夏とエトセトラ
カレンダー
| 2008年1月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||
本が出ました
| イラスト(426) |
| 猫マンガ(118) |
| 猫じゃないマンガ(2) |
| 猫(512) |
| 虫(49) |
| 魚(11) |
| works(75) |
| 鳥(20) |
| その他の動物(18) |
| Weblog(389) |
| 猫が訪ねる京都(5) |
| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |
| GIFアニメーション(4) |
最新の投稿
| 節分 |
| 沖縄・三線猫ちゃん |
| 猫又のキミと |
| アダンの浜 |
| サンタさんを待っているうちに寝落ちしてしまった子猫たち |
| 「白い猫塔(にゃとう)」 |
| 新嘗祭 |
| いい猫の日 |
| 「ハロウィンの大収穫」 |
| 銀閣寺~椿の回廊2024 |
最新のコメント
| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| 千夏/残暑 |
| タマちゃん/残暑 |
| 千夏/「豊穣」 |
| タマちゃん/「豊穣」 |
| 千夏/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |
| 与作/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |
| 千夏/家族が増えました |
| 与作/家族が増えました |
最新のトラックバック
ブックマーク
|
アトリエおひるねこ
岡田千夏のWEBサイト |
| それでも愛シテ |
| 手作り雑貨みみずく |
| くろうめこうめ |
| 忘れられぬテリトリー |
| 猫飯屋の女将 |
| 雲の中の猫町 |
| イカスモン |
| タマちゃんのスケッチブック |
| あなたをみつめて。。 |
| 眠っていることに、起きている。 |
| ノースグリーンの森 |
プロフィール
| goo ID | |
amoryoryo |
|
| 性別 | |
| 都道府県 | |
| 自己紹介 | |
| ねこのまんが、絵を描いています。
ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |
|
検索
gooおすすめリンク
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |

「猫は犬より働いた」須磨章著

当時の私は犬派で猫なんか好きでもなんでもなかったので、そうだそうだと利口なドン松五郎の勝利を小気味よく思ったのだけれど、すっかり猫派になってしまった今、この「猫は犬より働いた」という興味深いタイトルの本を手にとって、その「ドン松五郎」の一シーンを思い出した。
警察犬や盲導犬、介助犬など、人と一緒にさまざまな仕事をこなす犬に比べて、猫は、まさに「猫の手も借りたいほど」と言われるように、何の役にも立たないイメージが強いし、猫好きにとっては、そういう猫の役に立たなさというのがまた猫の魅力のひとつであるように感ぜられていたから、このタイトルはとても意外であった。
本書のプロローグによれば、猫派の著者に送られてきた「猫にも犬のような功績があれば教えて欲しいものだ」というある犬派の人からの手紙が、本書を書くきっかけになったのだという。猫の名誉挽回のために、猫だって負けずに仕事をしたのだということを立証しようというわけだ。
したがって、本書には古今東西の働く猫のエピソードが紹介されている。猫の仕事で主だったものといえば、やはりねずみを狩ることで、特に、幕末から昭和初期にかけて最盛期を迎えた日本の養蚕業が猫によって守られたということが協調されている。当時の日本経済を猫が支えていたという記述は、猫好きな読者なら決して悪い気はしないだろう。
また、壱岐地方ではかつて猫を湯たんぽ代わりに飼っていて、「湯猫」という言葉まであるというから、ドン松五郎と井上ひさしと、犬派だった自分を見返してやった気分だ。
働く猫とはあまり関係のないエピソードも多く載せられているので、本書の全体的なイメージとしては、歴史上の猫と人との係わり合いというような印象である。それはそれで面白いが、中世ヨーロッパの魔女狩りで多くの猫が殺された事実など、目をそむけたくなるような話もある。
膨大な数の文献に当たって、よくこれだけの猫話を拾い上げたものだと感心するが、それに対する著者の主張にはあまりぴんと来ないものが多い。たとえば、中世ヨーロッパで広く行われた魔女狩りにともなう処刑よりも、同時期にパリの一印刷工場で起きた虐殺事件を「信じられない事件」として大きく扱っているのは、問題のとらえ方がずれているように思われるし、犬や猫が地震を予知する能力についての項では、遺伝子に関する理解の程度があまり高くないとうかがわせるような記述もある。
もっとも、エピローグで著者が、現代の人と猫との関係について、猫を人間の枠にはめるばかりでなく、少しは人間を猫のほうに合わせてみるのも悪くないと述べている点については、私も大いに賛成である。
『猫は犬より働いた』須磨章
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )