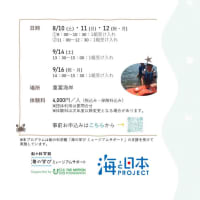髪を切りに行ってきました。
スッキリにはなったので、ヨシ!ではあります。
以前行っていた美容室では、
「ボブっぽいのがいいんだけど、パッツンな感じは嫌で、
ついでに横の髪が邪魔じゃないようにして、耳にかけたらショートに見える感じ」とか、
「縮毛矯正かけるけど、毛先はまるっぽいのがいいんです」とか、
「縮毛矯正するけど、張り付いたようなストレートは嫌」とかとか、
そういう注文しても、店長が希望を叶えてくれていました。
今行っている美容室は、そういう注文すると、
「縮毛矯正で髪まっすぐだから、できません」といわれます。
必要なきちんとした髪型にはしてくれるので、
今は近場で節約モードです。
でも、そういう美容室の存在を知っていると、
「髪切りのプロなんだから、修行せーよ!」と思っちゃいますね。
同時に、我が身も省みるんですけどね、ドキドキ。
私は幼稚園に着くと、「行かない~ 」と泣いている子どもでした。
」と泣いている子どもでした。
何が嫌だったのかは、まったく覚えていません。
嫌だといっても、毎回、幼稚園の先生に抱きかかえられて、
母は逃げるように去って行くので、幼稚園で過ごしていました。
そして、そのうちに友だちと遊んだり、歌を歌ったりの活動に参加して、
にこにこ顔で帰る時間を迎えていました。
でも、翌日はまたしても、「行かなぁ~い 」と泣くのです。
」と泣くのです。
水戸黄門の最後の印籠か、はたまた、幼稚園=泣くの条件反射のような感じでした。
以前、紹介した『発達の扉』という本にこんなことが書かれています。
2~3歳は、大きい自分を求めてやまない心が高まり、
そうならない自分との間で、悩み、葛藤するときでしょう。(中略)
友だちが「じょうずにお返事できたね」と先生にほめられると、
「あんなに上手にお返事できるだろうか」と思ってしまうのでしょうか。
そう思ったら最後、自分の番のときには、返事できなくなってしまいます。(中略)
一人ひとりの子どもたちが「おにいちゃんになりたい」「おねえちゃんになりたい」と願い、
しかし、自信が持ちきれない中で、「本当になれるのだろうか」と葛藤しているのです。
そんなとき、しっかりすること、がんばることを押し付けられたりしたら、
「いや」「おかあちゃんのアホ」などと、ことばの限りを尽くして反抗しないではいられない心の段階なのでしょう。
いいかえるなら、「おにいちゃん」「おねえちゃん」としての自分を切実に求めているのです。
2,3歳頃になると、部分と全体やたくさんと少しなどの「比べる」力が芽生え出すそうです。
これは、「対比認識」と呼ばれているそうです。
そして、この対比認識が獲得されはじめると、単に比べる言葉がわかるようになるだけではなく、
「できたかーできないか」「これでいいのかーこれではいけないのか」という評価に過敏になってくるそうです。
無邪気で天真爛漫だけの時期から、葛藤が生まれる時期なのですね。
先ほどの本の続きです。
障害をもたない子どもたちでも、
どんな友だち関係のなかにいるのかは、本人にとって、とても大きな問題です。
この友だちとの力関係を感じはじめたり、
「できるーできない」の結果と評価に過敏になりはじめる二分評価の段階は、
障害をもっている子どもたちにとって、どんなときなのでしょうか。
その子のいる集団によって、ずいぶん心のもち方は変化するでしょうが、
いつも「できない自分」「友だちより下手な自分」「友だちより遅い自分」を感じはじめて、
つらい思いばかりしている障害をもった子どもたちはいないでしょうか。
友だちに「早くおいで」と手をひかれることで、
「できない自分」をいっそう感じてしまう子どもたちはいないでしょうか。
いとこたちとの遊びで、トランプの7並べで負けては泣き、
ボールを取れなくては泣きと、できないくせに負けず嫌いだった私の場合は、
まさにこんな感じだったかもなぁ~、と思います。
たくさん励まされて、遊んでもらって、おだてられながら、
「できない自分」に卑屈になるのではなく、「できるかも」とチャレンジして、
1回できたら、2回、3回と成功を積み重ねながら、
発達の道をゆるゆる、よたよたと歩んで来たのだと思います。
私たちは、子どもたちを叱咤もするけど激励もしながら、
子どもたちが自分の輝く力を出せるように、
知恵ある良き二人三脚のパートナーでありたいものですね。
スッキリにはなったので、ヨシ!ではあります。
以前行っていた美容室では、
「ボブっぽいのがいいんだけど、パッツンな感じは嫌で、
ついでに横の髪が邪魔じゃないようにして、耳にかけたらショートに見える感じ」とか、
「縮毛矯正かけるけど、毛先はまるっぽいのがいいんです」とか、
「縮毛矯正するけど、張り付いたようなストレートは嫌」とかとか、
そういう注文しても、店長が希望を叶えてくれていました。
今行っている美容室は、そういう注文すると、
「縮毛矯正で髪まっすぐだから、できません」といわれます。
必要なきちんとした髪型にはしてくれるので、
今は近場で節約モードです。
でも、そういう美容室の存在を知っていると、
「髪切りのプロなんだから、修行せーよ!」と思っちゃいますね。
同時に、我が身も省みるんですけどね、ドキドキ。
私は幼稚園に着くと、「行かない~
 」と泣いている子どもでした。
」と泣いている子どもでした。何が嫌だったのかは、まったく覚えていません。
嫌だといっても、毎回、幼稚園の先生に抱きかかえられて、
母は逃げるように去って行くので、幼稚園で過ごしていました。
そして、そのうちに友だちと遊んだり、歌を歌ったりの活動に参加して、
にこにこ顔で帰る時間を迎えていました。
でも、翌日はまたしても、「行かなぁ~い
 」と泣くのです。
」と泣くのです。水戸黄門の最後の印籠か、はたまた、幼稚園=泣くの条件反射のような感じでした。
以前、紹介した『発達の扉』という本にこんなことが書かれています。
2~3歳は、大きい自分を求めてやまない心が高まり、
そうならない自分との間で、悩み、葛藤するときでしょう。(中略)
友だちが「じょうずにお返事できたね」と先生にほめられると、
「あんなに上手にお返事できるだろうか」と思ってしまうのでしょうか。
そう思ったら最後、自分の番のときには、返事できなくなってしまいます。(中略)
一人ひとりの子どもたちが「おにいちゃんになりたい」「おねえちゃんになりたい」と願い、
しかし、自信が持ちきれない中で、「本当になれるのだろうか」と葛藤しているのです。
そんなとき、しっかりすること、がんばることを押し付けられたりしたら、
「いや」「おかあちゃんのアホ」などと、ことばの限りを尽くして反抗しないではいられない心の段階なのでしょう。
いいかえるなら、「おにいちゃん」「おねえちゃん」としての自分を切実に求めているのです。
2,3歳頃になると、部分と全体やたくさんと少しなどの「比べる」力が芽生え出すそうです。
これは、「対比認識」と呼ばれているそうです。
そして、この対比認識が獲得されはじめると、単に比べる言葉がわかるようになるだけではなく、
「できたかーできないか」「これでいいのかーこれではいけないのか」という評価に過敏になってくるそうです。
無邪気で天真爛漫だけの時期から、葛藤が生まれる時期なのですね。
先ほどの本の続きです。
障害をもたない子どもたちでも、
どんな友だち関係のなかにいるのかは、本人にとって、とても大きな問題です。
この友だちとの力関係を感じはじめたり、
「できるーできない」の結果と評価に過敏になりはじめる二分評価の段階は、
障害をもっている子どもたちにとって、どんなときなのでしょうか。
その子のいる集団によって、ずいぶん心のもち方は変化するでしょうが、
いつも「できない自分」「友だちより下手な自分」「友だちより遅い自分」を感じはじめて、
つらい思いばかりしている障害をもった子どもたちはいないでしょうか。
友だちに「早くおいで」と手をひかれることで、
「できない自分」をいっそう感じてしまう子どもたちはいないでしょうか。
いとこたちとの遊びで、トランプの7並べで負けては泣き、
ボールを取れなくては泣きと、できないくせに負けず嫌いだった私の場合は、
まさにこんな感じだったかもなぁ~、と思います。
たくさん励まされて、遊んでもらって、おだてられながら、
「できない自分」に卑屈になるのではなく、「できるかも」とチャレンジして、
1回できたら、2回、3回と成功を積み重ねながら、
発達の道をゆるゆる、よたよたと歩んで来たのだと思います。
私たちは、子どもたちを叱咤もするけど激励もしながら、
子どもたちが自分の輝く力を出せるように、
知恵ある良き二人三脚のパートナーでありたいものですね。