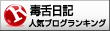篆刻(てんこく)とは、印章を刻すことであり、主に篆書を印文に刻むことから篆刻と呼ばれている。印章の起源は古く、中国においては夏・殷・周の時代から始まると考えられているが正確な起源についての定説はない。古代メソポタミアでは紀元前三六〇〇年頃の地層から発見された円筒印章の印影が最も古いとされている。古い時代には粘土板や木簡を束ねた縄の封泥に印章を押したものである。その主たる目的は商取引に伴う手紙や契約文書の主体を示すことにあった。
周王朝の理想的な制度について周公旦が書き残したものとされる「周礼・しゅうらい」に符節(わりふ)を管理する「掌節職・しょうせつしょく」という役職があり、その役職について説明した文章に「貨賄(金玉を貨といい、布帛を賄という)の授受には、璽節(じせつ)を使用する」とあるのが、璽節即ち印章に関する最も早い時期の記録とされる。因みに周というのは紀元前一〇四六年頃に殷を倒して建てられた王朝である。
秦の始皇帝が中国を統一して封建帝国を建設して以後、印章は権力者の権益を表示するものとなったが、秦代より以前には、普通の人々も、みな金・銀・銅・玉・犀の角・象牙など使って、一寸の璽を作り、龍や虎の形を鈕に刻すのも、自分の好みに従うだけのことであったと古書に記されている。
現在、盛んに行われている芸術的な篆刻は、明の時代になって文人墨客が「篆刻の道は詩と同じである」という考えのもとに好んで用いたことによる。
さて、面白くも無い能書きはこの位にして私の趣味とする篆刻とは一体どんなものかを申し上げよう。簡単に言ってしまえば年賀状の芋版である。芋版は薩摩芋に彫るが篆刻の場合は石に彫る。書画の類には必ずといってよいほど落款を捺してあるがあれと想ってもらえれば概ね間違いは無い。
印材は寿山石や青田石といった軟らかい石を主に使っているが竹の地下茎などに刻むこともある。道具は印刀であるが自転車のスポークを鑢で研いで刃をつければ十分に用を足す。印材と印刀、この二つが揃えば篆刻は出来るのであるが、印材を固定するための印床、下書きをするための小筆、印泥、印箋、篆刻字典などがあれば更に重宝である。
私は中国浙江省杭州市の篆刻家・王永虎先生が静岡へ見えられたときに王先生の仕事ぶりを半日間ずっと見続けて篆刻のやり方を学んだ。
私が普段やっている手順を示すと、先ず、印材の表面を調整する。私の場合は新しい砥石で平に研いでいる。
次に、印文を鉛筆で下書きする。この際に手鏡へ映して印面の逆字を確認する。下書きが整ったら細いマジックインキで印文のデザインをしっかりと書く。
篆刻には文字の部分を陰刻する白文と陽刻する朱文とがある。白文を彫るときは下書きの線の真ん中あたりに印刀の刃を当てる。黒い下書きの中に白くて細い線の印文が書ける。この段階でもう一度手鏡に映して全体の構成を確認し不具合は修正する。後は下書きのマジックインキにしたがってV字型に彫って線を拡げてゆけばよい。
朱文の場合は下書き線の輪郭に沿って印刀の刃を当て、印文以外の不要な部分を削り落としてゆく。印刀を使う時の要点は石の表面に対して一定の角度をつけることである。
篆刻の済んだ印章は紙面に捺して印影を確認する。私は印箋の代用として古い電話帳を利用している。完成するまでには何度何度も捺印するので古い電話帳は便利である。
篆刻は印文を選び、書体を選び、印材に刻むという作る楽しみのほかに、印譜などによって先人の作品を鑑賞するという楽しみ方がある。私が好きな篆刻作家は、呉熙載(ごきさい)、趙之謙(ちょうしけん)、呉昌碩(ごしょうせき)などであるがいずれも詩・書・画・印において優れた芸術家でもあった。
印材や印泥のことなど語れば限がないので今回はこの辺で端折っておく。
◆ 福徳長寿と幾度も印を捺す
周王朝の理想的な制度について周公旦が書き残したものとされる「周礼・しゅうらい」に符節(わりふ)を管理する「掌節職・しょうせつしょく」という役職があり、その役職について説明した文章に「貨賄(金玉を貨といい、布帛を賄という)の授受には、璽節(じせつ)を使用する」とあるのが、璽節即ち印章に関する最も早い時期の記録とされる。因みに周というのは紀元前一〇四六年頃に殷を倒して建てられた王朝である。
秦の始皇帝が中国を統一して封建帝国を建設して以後、印章は権力者の権益を表示するものとなったが、秦代より以前には、普通の人々も、みな金・銀・銅・玉・犀の角・象牙など使って、一寸の璽を作り、龍や虎の形を鈕に刻すのも、自分の好みに従うだけのことであったと古書に記されている。
現在、盛んに行われている芸術的な篆刻は、明の時代になって文人墨客が「篆刻の道は詩と同じである」という考えのもとに好んで用いたことによる。
さて、面白くも無い能書きはこの位にして私の趣味とする篆刻とは一体どんなものかを申し上げよう。簡単に言ってしまえば年賀状の芋版である。芋版は薩摩芋に彫るが篆刻の場合は石に彫る。書画の類には必ずといってよいほど落款を捺してあるがあれと想ってもらえれば概ね間違いは無い。
印材は寿山石や青田石といった軟らかい石を主に使っているが竹の地下茎などに刻むこともある。道具は印刀であるが自転車のスポークを鑢で研いで刃をつければ十分に用を足す。印材と印刀、この二つが揃えば篆刻は出来るのであるが、印材を固定するための印床、下書きをするための小筆、印泥、印箋、篆刻字典などがあれば更に重宝である。
私は中国浙江省杭州市の篆刻家・王永虎先生が静岡へ見えられたときに王先生の仕事ぶりを半日間ずっと見続けて篆刻のやり方を学んだ。
私が普段やっている手順を示すと、先ず、印材の表面を調整する。私の場合は新しい砥石で平に研いでいる。
次に、印文を鉛筆で下書きする。この際に手鏡へ映して印面の逆字を確認する。下書きが整ったら細いマジックインキで印文のデザインをしっかりと書く。
篆刻には文字の部分を陰刻する白文と陽刻する朱文とがある。白文を彫るときは下書きの線の真ん中あたりに印刀の刃を当てる。黒い下書きの中に白くて細い線の印文が書ける。この段階でもう一度手鏡に映して全体の構成を確認し不具合は修正する。後は下書きのマジックインキにしたがってV字型に彫って線を拡げてゆけばよい。
朱文の場合は下書き線の輪郭に沿って印刀の刃を当て、印文以外の不要な部分を削り落としてゆく。印刀を使う時の要点は石の表面に対して一定の角度をつけることである。
篆刻の済んだ印章は紙面に捺して印影を確認する。私は印箋の代用として古い電話帳を利用している。完成するまでには何度何度も捺印するので古い電話帳は便利である。
篆刻は印文を選び、書体を選び、印材に刻むという作る楽しみのほかに、印譜などによって先人の作品を鑑賞するという楽しみ方がある。私が好きな篆刻作家は、呉熙載(ごきさい)、趙之謙(ちょうしけん)、呉昌碩(ごしょうせき)などであるがいずれも詩・書・画・印において優れた芸術家でもあった。
印材や印泥のことなど語れば限がないので今回はこの辺で端折っておく。
◆ 福徳長寿と幾度も印を捺す