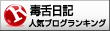我われ土方の鶴嘴・スコップが武門の槍・刀に相当するものであるとすれば、現場における薬缶は差しずんめ戦陣における水筒にあたるだろう。
この薬缶という湯沸し道具が、実はラグビーの試合における薬缶の役割と同様で、土方の野外生活には必要欠くべからざる重器なのである。
薬缶は銅鑵ともいい、昔は銅で造るのを専らとした。銅は熱の伝導率がよく、物が早く煮えることを昔の人達も熟知していた。そして、銅の成分が健康を害することも知っていたから、銅器の内側には、錫と鉛の合金である白目(しろめ)を塗って銅気を防ぐ工夫をした。
今日、一般的に使われている薬缶は、ほとんどがアルマイト製である。このアルマイト製の薬缶を焚き火へ直に吊るして湯を沸かすため、煤けて真っ黒けになっているのが相場である。
ところで、どこの現場にも必ず一人はいるのが、焚き火、湯沸しの名人である。この名人は、有り難いことに、他の土方仲間が知らない間に、ちゃんと火を焚いて、湯を沸かしておいてくれるのである。
現場においては、お茶っ葉を薬缶の白湯へ直に放り込むのが日常的である。お茶っ葉を切らした時などは、茶畑の生葉をしごき採って煮ることもある。
しかして、食事時これを喫するに各自の食器をもってするのだが、食事時以外は、薬缶の蓋をもって喫するのを常とする。
薬缶の蓋には湯気を抜く穴が開いている。この穴を中指の先で塞いでから茶を注ぐ。薬缶が古くて蓋の抓みが取れていることがある。この場合は人指し指と中指を使って、二つの穴を同時に塞がなければならず、漏らさずに飲むためには多少の骨を必要とするのである。