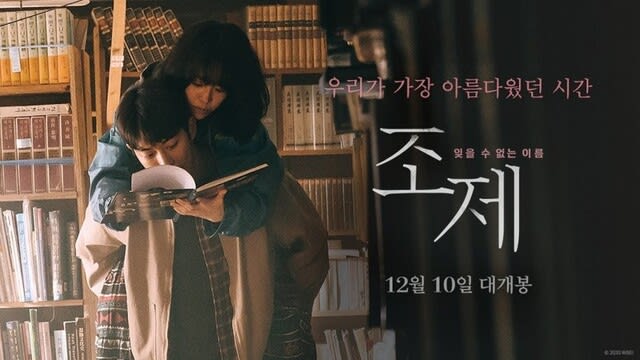6年前に訪れたポーランドの記憶と言えば、到着したワルシャワ・ショパン空港でハングル文字の標識を眼にした時の親近感以外は、何となく心に霧がかかっていたようで曖昧である。思うに、後に訪問したアウシュヴィッツ強制収容所と、その時のどんよりした空のイメージがあまりに強すぎたか為かも知れない。第二次世界大戦下、この地で主にユダヤ人を標的に、ナチスの優生思想により劣った民族と判断された百数十万がここで殺害された。ナチスドイツの占領下であったとは言え、ポーランドの人々にとって、この地は消えることのないある種に懺悔の念を抱かせる存在ではないか。そして、私にとって今回紹介するドキュメンタリーを理解する一助ともなった。
映画「ポーランドへ行った子供たち」は、1950年代、北朝鮮から秘密裏にポーランドへ送られた韓国戦争(六二五戦争、朝鮮戦争)孤児たちの知られざる歴史に焦点を当てたドキュメンタリー作品である。監督は、ホン・サンス監督の「気まぐれな唇」などで女優としても活躍してきたチュ・サンミ。当初より演出のも関心を持っていた彼女は、数年目より本格的に映画監督を目指して大学院で学び、今回が初の長編映画となった。本作品は2018年韓国で上映され、ドキュメンタリーとしては5万人以上を動員するヒットとなり、国内外の映画祭でも高い評価を受けた。作品制作のきっかけは、チュ・サンミ監督が産後鬱を患ったことで、子供への過度の愛情と不安の間で揺れていた時、偶然北朝鮮の孤児たちの映像を眼にしたことから始まる。1950年代、自国も厳しい情勢下に異国の孤児たちを我が子のように育て面倒をみるポーランド人教師たちと、彼らを「ママ」「パパ」と慕う朝鮮の子どもたち。チェ監督は、孤児たちの‘心の傷’と、そんな彼らを真摯に受け入れて面倒をみるポーランド教師たちの愛情の意味を知りたいと願う。その為に、監督は北朝鮮の戦争孤児をテーマに制作予定の劇映画のキャスティングオーディションで出会った脱北者の大学生イ・ソンを連れてポーランドを訪問し、いまだに子どもたちを懐かしく想い、当時を思い出しては涙を流す教師たちと出会い話を聞く。
1950~53年に朝鮮半島で起きた戦争により10万人以上が孤児になったとされる。そして北朝鮮では孤児たちの一部が、当時共産圏であった東欧諸国に送られ現地の孤児院で教育受けた。しかし、その目的や詳細は謎のままである。本作品内でも登場するが、この事実に関してはポーランド人ジャーナリストのJolanta Krysowata氏により最初に取り上げられ、ドキュメンタリー映画「Kim Ki Dok」として2006年に発表された。北朝鮮の要請に応じて東欧各国に送られた孤児は総6000人余り、ポーランドはそのうち1500人ほどを静かな森に囲まれた村プワコビツェ(Plakowice)に受け入れた。第二次大戦で大きく破壊され、国全体が貧しい生活を強いられる中、外国人の受け入れが反感を買わないように孤児院はできるだけ人目に触れさせない意図であったらしい。(コリア・ヘラルド)
孤児たちに同行した北朝鮮の監督者は思想教育への妨げになると「愛情と甘いもの」を与えない事をポーランド教師に要求する。しかし、彼らは愛情を十二分に注いで育て面倒を見た。チュ・サンミ監督はその理由を知りたいと切実に想い旅と取材を続け、ある結論に達する。紛争や戦争は過去から現在まで、ウクライナも含め世界中で絶えることない戦禍。国の指導者や権力者は戦闘や戦果に関しては多くを語るが、最も弱い立場にある人間は忘れ去られ、記録にも残らない。監督が幾度か口にする「傷の連帯」という言葉の中に、彼女がこの映画で訴えたかった本質と、映像の中に登場する人々の涙の意味が刻まれている。














 作品の中で映し出される釜山の街並みは、今やGDP世界10位まで成長した韓国でソウルに次ぐ第二の大都市の名に相応しい洗練された姿である。私が学生であった1980年代、釜山大学に通う友人を訪ねた思い出の中にあるのは、一地方の港町。海水浴客もまばらな浜辺で寝そべり、日が暮れる前から露天商から発達したチャガルチ海鮮市場の屋台で、山盛りの魚介類をつまみに焼酎を飲んだ頃のイメージとはかなり異なる。「釜山」という名称が歴史に登場したのは朝鮮王朝1470年の『宗実録』が初であった。それ以前の書物『世宗実録(1402)』『慶尚道地理志(1425年)』『世宗実録地理志(1454年)』や同時期の『慶尚道續撰地理志(1469年)』『海東諸国記(1471)』では「富山」と表記されていることから、15世紀末に富山から釜山に名称変遷があったらしい。そしてこの名称の由来となった山―山の形がずんぐりして釜に似て~と『海事録』の中にある「登釜山詩」で表されたのは、現在の釜山東区 佐川洞背後の「甑山(チュンサン)」とされる。韓日関係から顧みると、日本と最も地理的に近い街と言える釜山は、良きも悪しきも歴史的深いかかわりを持つ。秀吉よる朝鮮出兵(文禄の役 1592~)で最初に上陸したのが釜山。これをきっかけに幾つかの漁村が点在しているに過ぎなかった海岸沿いには,日本に対する前線基地としての「釜山鎮」が設置され,その後さらに湾の南側には,李氏朝鮮が開国を迫られる中で,日本人使臣のための臨時的宿所としての「(草梁)倭館」も設けられた。その後も日韓併合、朝鮮戦争(6.25戦争)など多くの困難を経て、現在は近代的な国際都市として今があるのだろう。映画界でも毎年開かれる釜山國際映画祭はアジア最高の映画祭と呼ばれる存在だ。
作品の中で映し出される釜山の街並みは、今やGDP世界10位まで成長した韓国でソウルに次ぐ第二の大都市の名に相応しい洗練された姿である。私が学生であった1980年代、釜山大学に通う友人を訪ねた思い出の中にあるのは、一地方の港町。海水浴客もまばらな浜辺で寝そべり、日が暮れる前から露天商から発達したチャガルチ海鮮市場の屋台で、山盛りの魚介類をつまみに焼酎を飲んだ頃のイメージとはかなり異なる。「釜山」という名称が歴史に登場したのは朝鮮王朝1470年の『宗実録』が初であった。それ以前の書物『世宗実録(1402)』『慶尚道地理志(1425年)』『世宗実録地理志(1454年)』や同時期の『慶尚道續撰地理志(1469年)』『海東諸国記(1471)』では「富山」と表記されていることから、15世紀末に富山から釜山に名称変遷があったらしい。そしてこの名称の由来となった山―山の形がずんぐりして釜に似て~と『海事録』の中にある「登釜山詩」で表されたのは、現在の釜山東区 佐川洞背後の「甑山(チュンサン)」とされる。韓日関係から顧みると、日本と最も地理的に近い街と言える釜山は、良きも悪しきも歴史的深いかかわりを持つ。秀吉よる朝鮮出兵(文禄の役 1592~)で最初に上陸したのが釜山。これをきっかけに幾つかの漁村が点在しているに過ぎなかった海岸沿いには,日本に対する前線基地としての「釜山鎮」が設置され,その後さらに湾の南側には,李氏朝鮮が開国を迫られる中で,日本人使臣のための臨時的宿所としての「(草梁)倭館」も設けられた。その後も日韓併合、朝鮮戦争(6.25戦争)など多くの困難を経て、現在は近代的な国際都市として今があるのだろう。映画界でも毎年開かれる釜山國際映画祭はアジア最高の映画祭と呼ばれる存在だ。