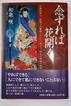「鬼平犯科帳」、「剣客商売」、「仕掛人藤枝梅安」などのシリーズものがどうしても有名な時代小説となっている池波正太郎先生。大長編小説なら「真田太平記」であり、戦国時代を紐解くには最高の小説である。真田一族とその目となって働いた忍びの集団を通して、戦国時代から徳川幕府成立、さらに徳川幕府安定期までを学ぶことができる。
その徳川幕藩体制も綻びはじめて崩壊の一途をたどり、世は明治維新へと大きく時代が動いた。つまり、戦国時代から明治維新までの長い日本の歴史のうねりが書き綴られている池波小説群、どの一遍を取り上げてもその時代のうねりを感じ取ることができる。
歴史に埋没した名のある人たち、さらにそれを支えた名もなき人々の息遣いまでもが、ヒシヒシと感じとれる。池波小説を解説されている佐藤隆介氏によると、戦後の政治と教育の歪みによって、今の若者は日本の歴史から遠ざかり過ぎている。
400年以上前の戦国時代も、徳川幕府時代も、明治維新のあった近代日本もすべてが今ここに至る時代へと繋がっており、日本の歴史を知ることは日本人として大事なことである。そのためにも歴史の事実をベースに描かれている一連の池波時代小説は、日本の歴史を紐解くための一つの手段であり、何よりも文章が優れており、読みごたえがあるので寝る間も惜しまれると記されている。
さて、池波小説群の中でも、忍びの者を通して戦国武将が描かれている一連の小説がある。武田信玄を描いた「夜の戦士」では甲賀忍び丸子笹之助が主人公、上杉謙信を描いた「蝶の戦記」では甲賀杉谷忍び於蝶が主人公、信長死後から豊臣秀吉を描いた「忍びの風」は、甲賀忍び井笠半四郎と於蝶が主人公。
さらに秀吉の死後、石田三成や真田昌幸・幸村親子を描いた「忍者丹波大介」では、甲賀を裏切った丹波大介が主人公、また、「忍びの女」では、福島正則が克明に描かれており、女忍び小たまが主人公である。
そして、今回の「火の国の城」では、関ケ原の戦いから5年後、丹波大介が生きていたという設定から、大阪の役までが描かれている。既に福島正則が描かれた「忍びの女」の対極に加藤清正を描いた小説が、この「火の国の城」であり、池波忍者小説の完結編ともいわれている。
そのため、主人公は丹波大介であるが、その大介を支える甲賀杉谷忍びの於蝶、島の道半なども登場。その時の大介は、30代前半で於蝶は60代後半くらいの年齢となっている。一連の忍びの小説群を読むとよくわかる。
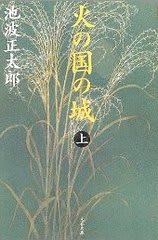

また、この大介は「夜の戦士」(甲賀忍び丸子笹之助)を読み終えると、笹之助の子供とも受け止められるところがあり、「夜の戦士」と「忍者丹波大介」の双方を読むことをお勧めしたい。
ところで、朝鮮にわたり勇猛果敢に戦をし、清正の虎退治として豪傑振りで名はせた加藤主計頭清正(かとうかずえのかみきよまさ)は、築城の名手として描かれている。そのため、家康から名古屋城築城、江戸城修復などを命ぜられている。
豊臣恩顧の武将である清正の財力をそぐことも目的であった家康。次々と難題を吹きかけるも飄々としてやり遂げる清正は、猪突猛進の福島正則とは対照的に頭の切れるしたたかな面もある武将である。また、家康にうまく取り入って、天下無双の熊本城を築城するから、いやはや大したものである。
その清正と浅野幸長が、関ケ原以後徳川と豊臣の戦をさせないためにも、秀頼君を何とか家康上洛のおりに対面させようと懸命に策を練る。ここらあたりの駆け引きなども克明に描かれており、実に面白い内容となっている。
対面した秀頼が余りにも立派に成長している様子に瞠目する家康、それに付き従う清正と幸長にも不安を覚える家康はついに決断をくだす。すなわち清正を亡き者にしようと・・・。
長年清正のお膳を任されていた料理人の梅春、実はこの人物は甲賀山中忍びであったことが、小説の後段で判明するから・・・えらいこととなる。あと、5年加藤主計頭清正が生かされていたなら、時代も大きく変わっていたと思うと残念な結末である。
この小説には、真田忍びの奥村弥五兵衛や向井佐助が登場、また甲賀五十三家の筆頭ともいえる山中俊房なども登場。これらの人物は、池波忍者小説には必ず登場する。
甲賀を裏切って伊那忍びとなった主人公の丹波大介、それに甲賀杉谷忍びのお婆の於蝶や老忍者・島の道半が大介を助ける。徳川方に組している山中俊房が抱える甲賀山中忍びや伊賀忍びと大介たちの死闘も詳細に描かれており、次々とページをめくらざるを得ない面白さがある。
関ケ原の戦が終わってもなお、自分の目の黒いうちに豊臣一族を滅亡させるか、豊臣秀頼親子を徳川の睨みの届く遠国に追いやりたいと思っている家康。
そして、清正らの戦を引き起こさないようにとの願いもむなしく、大阪の役(冬の陣、夏の陣)で豊臣一族の終焉を見るまでが描かれている本編、上下巻ながら読み応え十分の内容に満足。
実にどの一遍を取り上げてもそうであるが、何度でも、何度でも読みたくなる池波小説との至福の時を過ごしている毎日。これが、当方の第二の人生なのかも知れない。 (夫)
(夫)
(下記のバナーへのクリックをお願いします。ご協力、ありがとうございます)
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
その徳川幕藩体制も綻びはじめて崩壊の一途をたどり、世は明治維新へと大きく時代が動いた。つまり、戦国時代から明治維新までの長い日本の歴史のうねりが書き綴られている池波小説群、どの一遍を取り上げてもその時代のうねりを感じ取ることができる。

歴史に埋没した名のある人たち、さらにそれを支えた名もなき人々の息遣いまでもが、ヒシヒシと感じとれる。池波小説を解説されている佐藤隆介氏によると、戦後の政治と教育の歪みによって、今の若者は日本の歴史から遠ざかり過ぎている。

400年以上前の戦国時代も、徳川幕府時代も、明治維新のあった近代日本もすべてが今ここに至る時代へと繋がっており、日本の歴史を知ることは日本人として大事なことである。そのためにも歴史の事実をベースに描かれている一連の池波時代小説は、日本の歴史を紐解くための一つの手段であり、何よりも文章が優れており、読みごたえがあるので寝る間も惜しまれると記されている。
さて、池波小説群の中でも、忍びの者を通して戦国武将が描かれている一連の小説がある。武田信玄を描いた「夜の戦士」では甲賀忍び丸子笹之助が主人公、上杉謙信を描いた「蝶の戦記」では甲賀杉谷忍び於蝶が主人公、信長死後から豊臣秀吉を描いた「忍びの風」は、甲賀忍び井笠半四郎と於蝶が主人公。
さらに秀吉の死後、石田三成や真田昌幸・幸村親子を描いた「忍者丹波大介」では、甲賀を裏切った丹波大介が主人公、また、「忍びの女」では、福島正則が克明に描かれており、女忍び小たまが主人公である。
そして、今回の「火の国の城」では、関ケ原の戦いから5年後、丹波大介が生きていたという設定から、大阪の役までが描かれている。既に福島正則が描かれた「忍びの女」の対極に加藤清正を描いた小説が、この「火の国の城」であり、池波忍者小説の完結編ともいわれている。
そのため、主人公は丹波大介であるが、その大介を支える甲賀杉谷忍びの於蝶、島の道半なども登場。その時の大介は、30代前半で於蝶は60代後半くらいの年齢となっている。一連の忍びの小説群を読むとよくわかる。

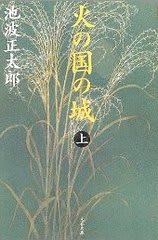

また、この大介は「夜の戦士」(甲賀忍び丸子笹之助)を読み終えると、笹之助の子供とも受け止められるところがあり、「夜の戦士」と「忍者丹波大介」の双方を読むことをお勧めしたい。
ところで、朝鮮にわたり勇猛果敢に戦をし、清正の虎退治として豪傑振りで名はせた加藤主計頭清正(かとうかずえのかみきよまさ)は、築城の名手として描かれている。そのため、家康から名古屋城築城、江戸城修復などを命ぜられている。
豊臣恩顧の武将である清正の財力をそぐことも目的であった家康。次々と難題を吹きかけるも飄々としてやり遂げる清正は、猪突猛進の福島正則とは対照的に頭の切れるしたたかな面もある武将である。また、家康にうまく取り入って、天下無双の熊本城を築城するから、いやはや大したものである。
その清正と浅野幸長が、関ケ原以後徳川と豊臣の戦をさせないためにも、秀頼君を何とか家康上洛のおりに対面させようと懸命に策を練る。ここらあたりの駆け引きなども克明に描かれており、実に面白い内容となっている。

対面した秀頼が余りにも立派に成長している様子に瞠目する家康、それに付き従う清正と幸長にも不安を覚える家康はついに決断をくだす。すなわち清正を亡き者にしようと・・・。
長年清正のお膳を任されていた料理人の梅春、実はこの人物は甲賀山中忍びであったことが、小説の後段で判明するから・・・えらいこととなる。あと、5年加藤主計頭清正が生かされていたなら、時代も大きく変わっていたと思うと残念な結末である。
この小説には、真田忍びの奥村弥五兵衛や向井佐助が登場、また甲賀五十三家の筆頭ともいえる山中俊房なども登場。これらの人物は、池波忍者小説には必ず登場する。
甲賀を裏切って伊那忍びとなった主人公の丹波大介、それに甲賀杉谷忍びのお婆の於蝶や老忍者・島の道半が大介を助ける。徳川方に組している山中俊房が抱える甲賀山中忍びや伊賀忍びと大介たちの死闘も詳細に描かれており、次々とページをめくらざるを得ない面白さがある。

関ケ原の戦が終わってもなお、自分の目の黒いうちに豊臣一族を滅亡させるか、豊臣秀頼親子を徳川の睨みの届く遠国に追いやりたいと思っている家康。
そして、清正らの戦を引き起こさないようにとの願いもむなしく、大阪の役(冬の陣、夏の陣)で豊臣一族の終焉を見るまでが描かれている本編、上下巻ながら読み応え十分の内容に満足。
実にどの一遍を取り上げてもそうであるが、何度でも、何度でも読みたくなる池波小説との至福の時を過ごしている毎日。これが、当方の第二の人生なのかも知れない。
 (夫)
(夫)(下記のバナーへのクリックをお願いします。ご協力、ありがとうございます)
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ