以前、盗塁の種類で説明したギャンブルスタートを、今回深堀します。
ギャンブルスタート=悪いプレーと思われ(私だけ?)がちですが、時と場合によっては用いてもいいのでは?と思う作戦です。
まず、ギャンブルスタートってなんぞや?から。
ギャンブルスタートとは、読んで字の如く、ピッチャーや野手の(投球・送球)動作でスタートを切るのでなく、ある程度のタイミングで走塁スタート(盗塁)をする事です。言わば見切り発車です。
よって一歩間違えば、ハイリスクしかないと思われがちなプレーです。
しかし、これば成功すればワンベースだけでなく、ツーベース以上が狙え、尚且つ相手ベンチに与えるプレッシャーは計り知れないです。
では、どのような状況で行われるのでしょうか?色々な状況があり、一概に言えないのですが、大きく分類すると
①左ピッチャーの1塁牽制時。
②ランナー3,1塁での、1塁ランナー盗塁時の3塁ランナー
③ランナー3塁で、バットに当たった瞬間の3塁ランナー
細かく分けたらきりがないですが、だいたいこの状況ではないでしょうか?
ギャンブルスタートをチームとしてやると決めた場合は、しっかりとした練習が必要です。
では、その状況での注意点を
①の場合には、やはりピッチャーの牽制の速さ(バリエーション)がキーになります。
よく、左ピッチャーでの盗塁は難しいと言われます。その理由は足をあげた際に、どちら(牽制か?ホームか?)か判らないからです。
ゆっくり足をあげ、牽制するかと思いきやホームに投げたり逆のパターンもあり、ギリギリまでスタートが切れない事が原因です。
ですので、そのようなピッチャーにお勧めなのが「右足が上がった(動いた)瞬間にスタートを切る」です。
これは、ピッチャーの1塁牽制が遅い場合です。クイックを行うピッチャーには不向きです。
だから、暫く牽制の癖を見て「大丈夫」と判断した場合にベンチからギャンブルスタートの指示があります。
近年は左ピッチャーもこの事を判っているので、あまり活用する事はないですね。
②の場合ですが、ギャンブルというよりダブルスチールの方が強いでしょうか。
要は、1塁ランナーが走って、キャッチャーが2塁に送球すると同時に、3塁ランナーはホームに突っ込みます。
その場合にも、予めこの相手チーム連携(特にセカンドの動き)をしっかり観察しておくことです。
セカンド・ピッチャーがカットプレーをしたり、するとチャンスが一気に0になります。
これも、だいたい学童野球であれば、3,1塁は必然的に3,2塁になるので、あまり実用性が無いですね。
最後に③です。これはここ最近プロ野球でも良く使われる作戦です。
スクイズのバンドでなくスイングするパターンです。
とにかくバッターはバットに当て、尚且つバウンドさせればOKです。
この場合にも2種類あり、完全に投げたらGOのパターンと、バットに当たればGOのパターンです。
前者は非常にリスキーですが、バットに当たればほぼ1点です。後者でも大丈夫ですが。
学童野球でも、この3塁ランナーパターンのエンドランをちらほら見かけます。
最初は「サイン間違い?」と思いましたが、実は3塁のエンドランです。
これはさすがに三振の多いバッターには不向きですね。
以上の3パターンが主たるギャンブルスタートだと思います。
軟式ボールであれば、バウンドが高く跳ねやすいので、ゴロスピードがどうしても遅くなるため、このギャンブルスタートは軟式野球では特に有効です。
打者心理的にもスクイズよりは緊張感が無いので楽に打席に立つことができ、成功確率はこちらの方が高いのでは無いかと、個人的には思います。
ギャンブルスタートはあくまで+αの作戦です。
しっかり基礎ができた時点でのステップアップの作戦です。
よって基礎練習を何度も行う事が一番ですね。




















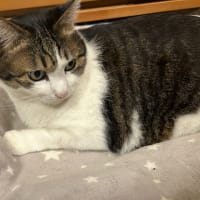
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます