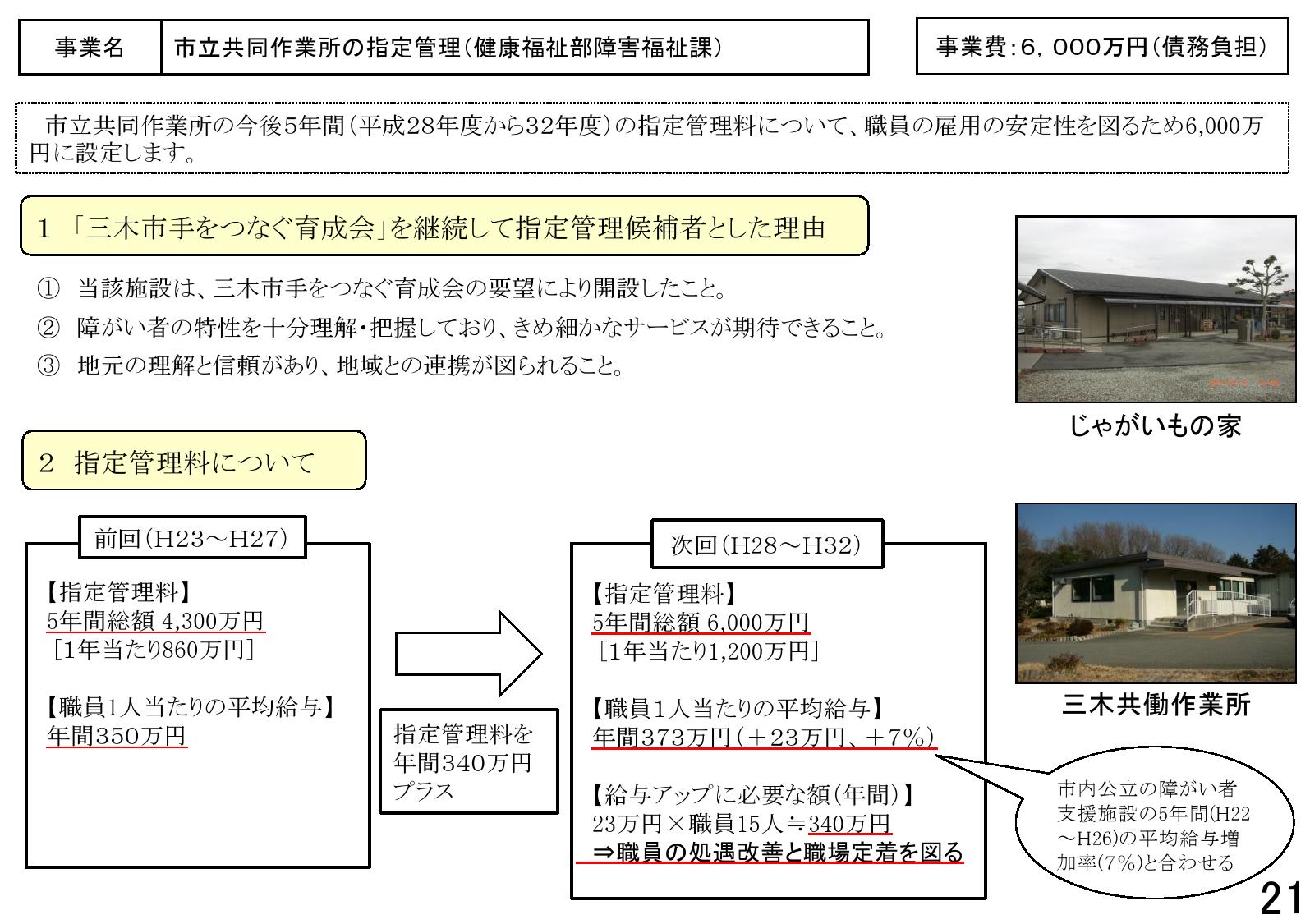市長等の給与条例の一部を改正する条例に対して反対の討論を行いました。
この間の理事の飲酒運転の問題と事業者同席に関する問題点を一定まとめられたのではないかと思っています。
昨日は、寝ずにこの原稿を書きました。
第67号議案、市長等の給与条例の一部を改正する条例に対して反対の討論を行います。
この条例は理事兼企画管理部長が酒気帯び運転をし、現行犯逮捕されたことをうけて、市長の道義的に責任を取るために給与月額の20%を3か月行うというものです。
反対の理由として3点挙げさせていただきます。
1点目は処分の根拠が明確でないことです。11/24の議員総会で配布された「市長等の給与減額について」の資料では、道義的責任を取るため市長は給与月額の20%を3か月、副市長は10%の3か月、教育長が10%の3か月の自主的返納する内容となっています。
ここでいう、市長の道義的責任とは何なのか。
教育長は副市長と同様の給与債権を自主的返納する理由について、特別職であり、その場に居たことの道義的責任があることを議員総会で言われました。
しかし、市長と副市長はその場に居たこの道義的責任についての言及はありませんでした。大西議員が「職員にお詫びを言うべきではないか」という質問に対して、「社会通念上の行為を行っただけで職員に謝罪する気持ちはない」と答弁をされています。
12月1日、本会議1日目の議案説明でも「三木市の最高責任者として、理事の任命権者としての責任」しか認めておられませんでした。
それが、12月9日の本会議の初田議員の「任命権者として潔く辞任すべきとの声をどう考えるのか」という質問に対し市長は「呼びかけた責任がある」と答弁しました。
また、12月14日の総務環境常任委員会の大眉議員の質問で副市長の口からですが、その場に居たことの責任もあることを認められました。
このことからも、提案された時とこの度の議会の中で責任の内容が変わっていることを確認したいと思います。
2点目は三木市職員倫理条例施行規則のいう利害関係者が同席していた問題が解決されていないことです。
12月8日に市幹部職員と民間の方との飲食について記者発表資料が出ています。
本来、建設業者の社長が三木市職員倫理条例施行規則のいう利害関係者にあたり、職員が利害関係者の同席する飲食の場に行けば規則違反となります。
しかし、今回2次会に参加した職員は市長・副市長が利害関係者の同席を誰にも伝えなかったので知らなかった。
一緒に飲んだり歌ったりしたにもかかわらず、市長副市長が誘った人たちであったことも知らないまま2時間半の飲食が終わったというのです。
一般市民の感覚では部長会の有志の会と言え2次会に外部の民間人を同席させることが異常ではないでしょうか。
更に、同席することを他の部長に一切伝えていなかったことは非常識と言わざる得ません。
しかし、このことにより、今回部長が三木市職員倫理条例施行規則違反をせずに済んだと認識されているようです。
仮に、市長・副市長どちらかが部長らの誰かに民間人を同席することを事前に話したりしていたら、三木市職員倫理条例施行規則違反になっていたわけです。
副市長が自治会長を勧誘し、市長がそれを追認したわけですから当然市長・副市長の責任も免れなかったでしょう。
今回、市民の疑念を払拭するために、職員倫理審査会を開催されますが、この審査会で抵触すると答申されれば市長副市長の責任も問われることになります。
この答申が出ない中で給与の減額処分を決めるべきではないと考えます。
最後3点目に、市長等の倫理基準に違反するとの疑念は払拭されたとは言えない状況にあるということです。
12/8の記者発表資料では本会議の議員の質問に答える中で疑惑の解明をすると言われていました。
本会議の質問の通告は4日に締め切られており全ての議員が質問する機会を与えられたわけではありません。
しかも岸本議員には通告外の質問が含まれていると指摘し、議員の質問に制限を加えました。
疑惑を解明しようという誠意も感じられませんでした。
更に、12/11の議員総会は今定例会の一部の議員の質疑と一般質問で十分な説明を行なっているという理由で欠席届けが出されました。
広報みき1月号にて市民に説明すると言われていますが、議員にも再度説明をし、残る疑念を解消した上で市長・副市長の処分は行うべきと考えます。
この間の議論の中で、国家公務員の倫理規約と比べて三木市の倫理規約が厳しいことをしきりに言われています。
しかし、国家公務員の倫理規約の改正施行日は平成17年4月1日です。
今の三木市の職員倫理条例及び施行規則は平成18年9月29日。
三木市職員の懲戒処分に関する指針と懲戒処分基準が平成18年11月6日に施行となっています。
薮本市長が三木市長として就任して1年目の大なたを振るった年であります。
市長自ら決められた規則と基準をそれよりも前に改正のあった国家公務員の倫理規約と比べて厳しすぎると今更いうのは、市長の倫理観が低下している表れではないかと思うのはわたしだけでしょうか。
また、本来三木市職員倫理条例と三木市長等倫理条例を施行するにあたって、審査委員を決めてなかったことについて落ち度があったのではないかと感じます。
今回の一連の問題は、最悪のシナリオは、市長・副市長をはじめ殆どの部長が責任問題に発展するというものです。
目の前の市政の課題を解決するにあたって、大きな打撃となるでしょう。
しかし、今この問題を不問にしたり、先延ばしにすることは、三木市にとって近い将来それ以上の打撃となるのではないでしょうか。
私たち議員1人1人が目を背けたくなるような現実に対してどれだけ誠実に対応するのかが問われているのではないでしょうか。
市の幹部をはじめとした職員の皆さん。
これまで三木市の将来のために働いてきた皆さんがこの先も誇りを持って働くためにも真実を明らかにすることから目をそらしてはいけないと思うのです。
どうか、第67号議案、市長等の給与条例の一部を改正する条例は議員、職員、そして市民が真実を究明した後に判断する必要があるために反対することを求めて討論を終わります。