
こんな面子での対談集が出版されたら、何を置いても読まねばならぬ、と発売直後に購入したのですが、他に読みかけの本が何冊かあったので、年明けから読み始めました。

三島、安部、大江の三人対談なんてあったの知らなかった。
その他にも、三島-大江、安部-大江と、とても興味深い組み合わせですよ。
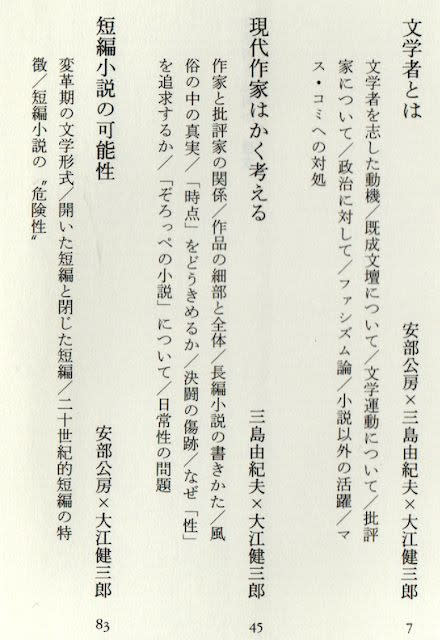
文学者とは 安部公房x三島由紀夫x大江健三郎
(群像1958年11月に掲載)
三島由紀夫はこのとき33歳。『金閣寺』を書き上げた2年後で、文芸誌を始め一般紙まで数多くの作品を発表し、まさに絶頂期と呼んでもいいのではないかという時期。
安部公房は34歳。芥川賞を受賞したのは8年前で、その後不条理文学を発表し、前年には『けものたちは故郷をめざす』を発表。しかし、『砂の女(1962年)』や『他人の顔(1964年)』と代表作とされる長編を発表する前の時期で、作家としては上り調子の時期といったところでしょうか。
大江健三郎は23歳。大学在学中で、『飼育』で芥川賞を受賞した年です。『死者の驕り』や『見る目に跳べ』など初期の尖がった作品を書いていた頃です。『セヴンティーン(1961年)』はまだ書いてない頃。
という時期なので、大江健三郎には先輩二人を前にして、やや遠慮がちなところも見られます。三島と安部はうまく大江をフォローしている感じ。
中では『ファシズム論』が面白かった。大江が三島の小説をファシストな感じと言い、それを三島が茶化して答える、安部がその態度をたしなめる、といった感じ。この3人の中では、安部がもっともファシズムに敏感なことがわかります。
最後の『マス・コミへの対応』で三島が、テレビ塔を焼ききって倒したいと軽口を叩くところで、編集者が対談の終わりを告げます。傍観者は、いいとこで止めるな!もっとやれー!という気分で終わりました。
現代作家はかく考える 三島由紀夫x大江健三郎
(群像1964年1月に掲載)
三島由紀夫は39歳。『豊饒の海-春の雪』を書き始める前年です。ほとんどの有名な小説、戯曲、評論はそれまでに発表した後で、円熟期というか戦後民主主義の中での孤立感をいちばん感じていた時期かもいれません。『英霊の聲(1966年)』を書く2年前、自衛隊入隊の2年前、楯の会結成の4年前の時期です。
大江健三郎は29歳。前年に生まれた長男光氏が障害を持って生まれ、『個人的な体験』を発表。3年後には『万延元年のフットボール』を発表し国際的に評価が高まります。作家としては上り調子ながら転換期を迎えていた時期といったところでしょうか。
全体的に、大江が三島に突っかかるところが見え隠れします。この二人はきっと馬が合わないのでしょう(^^)。バチバチの議論を交わしています。
『作品の細部と全体』の議論は、なかなか白熱した雰囲気で面白かった。
『「時点」をどう決めるか』の対談は興味深かったです。小説の「時間(時代)」について、三島も大江も否定的な考えを示しています。「短い時間に集約できることが小説家としていい技術ではないでしょうか(大江)」といった具合に。しかし、世界的ベストセラーとなったマルケスの『百年の孤独』は、長い時間を舞台にした小説です。『百年の孤独』が初刊されたのは1967年、大江はこれに影響をうけて『同時代ゲーム』を書いています。その前の『万延元年のフットボール』もしかり。対して、三島のマルケス評価は未知ですが、大江はこの対談当時からは、「時間」と小説の関連性への評価が変化したのでないでしょうか。
短篇小説の可能性 安部公房x大江健三郎
(世界1965年11月に掲載)
安部公房は41歳。『砂の女(1062年)』、『他人の顔(1964年)』と代表作と言われる作品を世に出し、映画化もされ、絶頂期と呼べる時期かと思います。大江健三郎は30歳で、三島との対談の一年後、自ら「乗り越え点であった」と語る『万延元年のフットボール』を発表した後で全盛期への入口でしょうか。
三島x大江の対談のようなバチバチ感はなく、理知的に文学について語り合っています。豊富な作品例を出しつつ語っているので、そららの作品の知識を持って読まないと意味が理解しにくい箇所も多くみられます。
この二人は議論が噛み合っているように思えます。"開いた短編と閉じた短篇"の議論は面白かった。しかし、後半にいくと話が難解、特に安部の話は難解で何度読んでも理解しがたいところもあります。"短篇小説の危険性"などは特にそう。

二十世紀の文学 安部公房x三島由紀夫
(文藝1966年2月に掲載)
この対談は、読んだことがありました。
三島由紀夫対談集『源泉の感情』に収録されています。

三島由紀夫は41歳、自衛隊に体験入隊したのがこの歳で、後の"楯の会"結成へとつながります。安部公房は43歳、『榎本武揚』を書き上げた翌年になります。両人とも作家としての地位を不動にしていた時期で、大御所同士の対談という趣きです。
この二人は和気藹々とした感じ。話し方からくつろいでいる印象を受けます。ときおりユーモアも交えながら対談は進みますが、三島の話は、平易な説明でわかりやすいところと超難解なところが両極端。
対談の最後は三島の有名なセリフ「俺には無意識というものがない」という話になり、安部は「そんなはずはない」と無意識存在論で、決着がつかずに終わりますが、お互いに”らしさ"が存分にでていた対談だと思います。
対談 安部公房x大江健三郎
(朝日新聞夕刊1990年12月17-19日に掲載)
安部公房は66歳、大江健三郎は55歳。三島の死から20年後の対談です。
最初の方で三島の話が出ます。大江の「いま思うと、三島さんと安部さんは一番の対立項でしたね」の問いに、
安部「確かにそう。でも三島君って変わり者だった。思想と人格が、完全に分離していた。思想は気に入らなかったけど、人格は好きだったな」
大江「あなたのことも好きでしたね。晩年の三島由紀夫は僕は好きじゃなかった」
といったやりとりがあります。
新聞掲載の対談のせいか、1965年の対談とは違い、わかりやすい話が多いです。この対談からは、大江が安部に一目も二目も置いていることが伝わってきます。
興味深かったのは、小説においてその執筆中に書き手の意識を越えることがあるか、ということです。先日いった三島100歳の対談のなかで、「三島(に限らず小説家は)、最後のシーンまで設計して書く。対して画家は、頭を無にして描いているうちに新しいものが生まれる(ゾーンに入るという感じ?)。三島はそういう体験をしたことがなかったのだろう」という話がでました。つまり、美術は無意識により芸術が生まれることがあるが文学はそうではない、と私は解釈しました。
しかし、安部は、そう考えてはいないことが、この対談からわかります。
安部「僕はこれからますます方向のない小説を書きたい。書くものの意味が事前には分かっていないものを」
大江「書く作業の中に、書き手の意識を超えるものはあるんでしょうか」
安部「ありますね。作品自体に存在する力があれば、意味なんて放棄していい」
ここらへんが安部のアバンギャルドなところというか、右脳で読ませる作家というか、非常に面白かった。
と、安部公房、三島由紀夫、大江健三郎と戦後を代表する三人の作家ですが、それぞれの思想の違いというか個性が、対談のあちこにみられて非常に面白い本でした・
三島は対談ではユーモアやお茶目なところを端々に出しますが、小説の中ではそれが出てこない。大江健三郎はその反対で、小説ではけっこう真面目にふざける、ようなところを感じます。しかし対談では真面目そのもの。もっともそれは三島や安部が年上だったせいなのかもしれませんが。
何度読み返しても飽きない一冊です。座右の書にしよう(^^)

対談者のプロファイル。
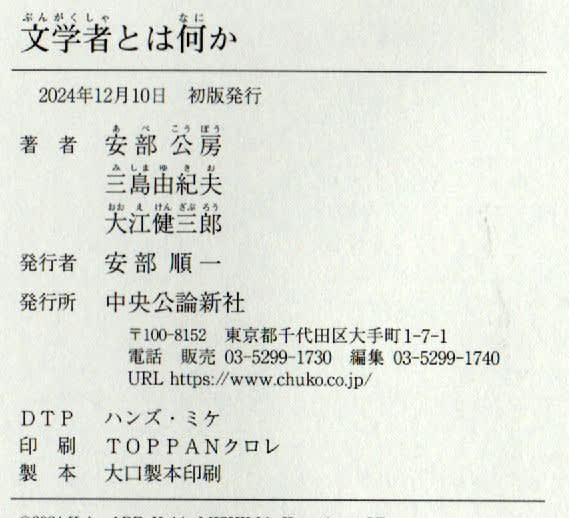
書誌事項。
p.s. 考えてみれば、将棋界の歴史が変わるか否かという重大極まりない案件が、若手新人一人の手に委ねられていたのだから、棚木四段の心労も察するに余りあるな。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます