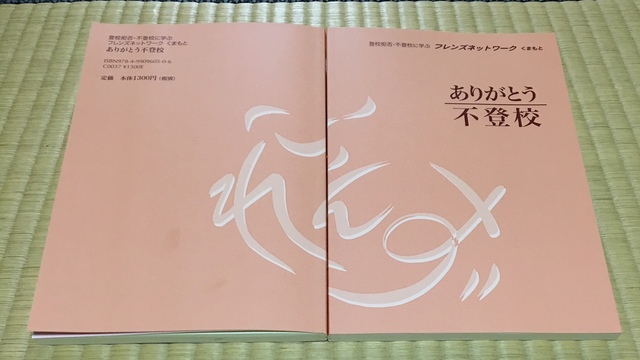参 考 会誌ACADEMIA No.172から
心理臨床から見た登校拒否 ―登校拒否は自立への生みの苦しみー つづき
立命館大学名誉教授 高垣忠一郎
2.「高速道路」の様相を強める子どもたちの生活
筆者自身は登校拒否が急増し始めた1970年代半ば頃から、登校拒否の子どもやその親と、カウンセリング面接や「親の会」活動を通じて付き合ってきました。また教師の教育研究集会のなかで、この問題に悩む教師の取り組みの苦労を共同研究者として目のあたりにしてきました。そこから浮き上がってきた子どもたちの生活のイメージは、まさに「高速道路」でした。そのイメージの背景には、すでにみた「閉じられた競争」「生き残り競争」の様相を強める社会と学校の状況と、その学校を中心とした生活に子どもたちが囲い込まれていく状況があることはいうまでもありません。
「高速道路」の最大の特徴は自分のペースで走れないことです。前後左右車が密集して走っており、その車の流れに乗って走らなければなりません。緊張してストレスが溜まります。しかしだからといってスピードを緩めることはできません。そうするとドライブインに入って、一服し、体勢を立て直す必要があります。筆者には登校拒否の子どもがそれと全く重なるイメージで見えてきました。「高速道路」を走るような毎日の生活のなかで、「もうこれ以上同じペースで走っていると、自分が自分でなくなってしまう」と感じるところまで追い込まれる子どもがたくさん出てきたのです。
その子どもたちが「自分をとりもどす」ために一服し、体勢を立て直そうとする試みが登校拒否なのだと見ることができました。彼らが登校の意図を持ちながら腹痛や頭痛、発熱などの身体症状を呈し、登校不能に陥るのは「高速道路」化した生活に対する彼らの追い込まれた心や身体の示す「拒否反応」であると、理解できました。ですから、筆者はこの論稿でも「不登校」ではなく「登校拒否」という言葉を使っているのです。
そしてこのような見方や理解を、個々の面接の場面や「親の会」の集まり、あるいは教育研究集会で折りに触れ語ってきましたし、書いてもきました。むろんこのような理解は大雑把で概略的な理解であり、個々の登校拒否の「ケース」を臨床心理学的にきめ細かく理解するには十分ではないことは重々承知しています。にもかかわらず、そうした理解を語り、書いてきたのは、その理解が「登校拒否」の多発と社会的な背景との結びつきを理解するうえではわかりやすく、かつ欠くことができないものだと確信してきたからです。
そしてまた、こうした理解が少なくとも二つの意味で重要な意義をもつと考えていたからです。まず第1に、こうした理解が、今日の社会や学校のあり方に目を開き、広い視野のもとに自分たちの抱える問題をとらえなおす視点をもたらし、ひいてはそのような社会システムを改善していく行動や運動につながっていくことを可能にするからです。
第2に、そのような視野が「世の中についていけない自分がダメだから、学校に行けなくなる」とか「自分が親としてダメだから、子どもが登校拒否になってしまう」という見方に立って、もっぱら自分を責める「自責感」や「負い目」(それにとらわれ続ける限り、子どもも親も元気になれない。そうした「自責」の念や「負い目」から自分を守ることに精一杯の心理状態にとどまり続ける)から子どもや親を解放する支えになるからです。
筆者自身はこうした意義を追求し、実現していくことを無視した心理臨床実践は、重箱の隅をつつくような「請負稼業」的な実践へと自らを閉ざしていくことにつながる危険性をもつと考えています。