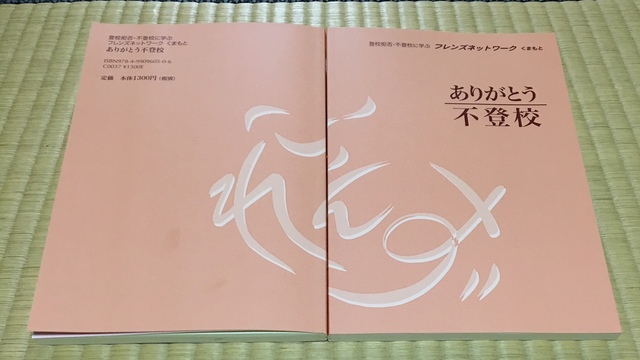講演内容
「いいんだよ!」 と言えなくても
―「ダメだなぁ」と思ってしまう、あなたのために ―
講師 / 齋藤眞人 立花高等学校 校長
今日は、フレンズさんが提案されたこの演題に合わせて「よーし、頑張ろう!」と全部新しく書き直して来ました。でも、肩に力が入ってたら、ろくな事ありません。肩の力を抜いていきます。
省略
■実践例
¦対価を支払う 省略
¦チーム担任制導入
担任と合う、合わないということがあるし、力のある教員に限ってこの教室はおれの城だと頑張ったりするので、チーム担任制を導入しました。3人一組で2クラスを担当し、週ごとに一人ずつ入れ替わって、4週目に最初のクラスに戻ってくる。これが大当たりで、他校にも広がっていくんじゃないかと楽しみです。
¦フリースクール設置 省略
¦「ママズカフェ」就労支援施設A型 省略
■問題提起
学校や社会は、もうちょっと柔らかくてもいいんじゃない?
▼特別扱い?
うちは今、針時計とデジタル時計、両方を設置しています。最初は図形が苦手な学習障がいの有る生徒への配慮でした。その子は時間を守れないのではなくて、分からなかったのです。問題は、その子が学習障がいだということではなく、“無理解の中で義務教育を終えていること”です。
ある小学生のお母さんが「うちの子にデジタル時計を持たせたい」と学校にお願いしたら「この子だけ特別扱いはできません」と断られたそうです。だけど、メガネをしていて「あんた卑怯、外せ」とは言われませんよね。メガネは市民権を得ている。
又、本校ではケータイを禁止したことはないです。黒板の文字を書き写すのが苦手な子も、カシャッと撮れば一瞬です。とても便利。
でも、ケータイで問題が起きるからと禁止すると、問題が水面下に沈むだけです。
▼素直で従順でないとダメ?
社会を安定して保持するためには集団性の維持が前提だとして、日本の教育は“素直で従順な人間を育てること”に重きを置いてきた気がすします。僕もそうでした。
例えば全校集会、「静かにしなさい!」「ちゃんとしなさい!」と飛び交う怒号。一糸乱れぬ見事な集団。目的はそこですか?内容を理解しようと意欲を持って参加することではないですか?
あまりにも揃えようとして指示するから、自律ではなく他律になってしまって、自分で考えることが出来ていない。だから、社会に出て投票率が低い。同調教育は限界が来ていると、私は思います。
一定の範囲内に入れない子どもたちの居心地が悪くなっている。裏返してみると、同じであることを実践している子どもたちをもっと賞賛していいのに、それを当たり前にすり替えられ、何かが突出していないと認めてもらえない社会になっている。
▼自由は我がまま?
大人は、自由を我がままだと曲解している。自分の自由が尊重されるから、他者の自由も尊重できるはず。指導に従う従順な子だけが賞賛されてしまうのは“社会側の悪気のない最悪文化”。
従順でなければ教育を受ける権利はないんでしょうか?子どもは未成熟であることが許される。それが彼らの特権です。
▼問題の本質は?
昨年10月に文部科学省が発表した「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」というのがあって、問題行動と不登校を一緒くたにしているのはどうかと思いますが、「不登校のきっかけ」として次の数字を発表しました。
先生がきっかけ27.5% (昨年10月・生徒対象)
先生がきっかけ 0.9% (昨年11月・教員対象)
つまり教員は自分たちが不登校にさせている意識がないんです。(30倍以上の)この意識の乖離(かいり)が、問題の本質だと思います。
一定数の子どもが学校に行かない選択をするのは自然です。「学校に行くのが当たり前」という考えから脱却していきましょう。大人の仕事は可能性を示すこと。「克服」に拘らない柔らかさを!
▼平等は公平?
多くの大人が平等と公平を取り違えている。
例えば塀の向こうの野球の試合を観るために、背の高い子、中くらいの子、低い子それぞれに、大人は、同じ高さの台を平等に1個ずつ与えがち。でも1番低い子は、台1個では塀の上まで届かない。1番高い子は台がなくても見える。こんな場合どうしますか?見える子の台を見えない子に譲れば、3人とも公平に野球観戦できますよね。
◆バラバラではいけない?
ここに昭和2年の、ある教室の授業風景を撮った写真があります。オルガンを弾いている子たち、カルタ遊びをしている子たち、赤ん坊の世話をしている子たち、友だちの髪を結ってる子たち、バリカンで髪を刈っている子たち、それから机で静かに勉強している子たち、皆バラバラ。だけどこの先生は悲壮感なく穏やかに見守っている。これこそ本校創設者、安部清美先生27才の時の授業風景です。鳥肌が立ちます。全国から2800人見学に来て、「愛の教育」と呼ばれていたそうです。
この写真を見て、当時の生徒さんが、
「いいクラスでした。みんな思いやりがあって」と、懐かしがっていらっしゃいました。
▼不登校は不幸?
30日以上休んだら不登校。では 29日ではどうなのか?200日休んでいても自分らしく生きている子もいれば、1日も休まず学校へ行っていても、心がすっかり折れている子もいます。
学校に行かなかったら不幸になるというのは、大人の思い込みです。
²迷惑をかけてはいけない?
他人に迷惑をかけてはいけないと言いますけど、本当にそうですか?私は「助けて欲しい時は、誰かにすがりなさい」と言います。誰にも迷惑をかけないように一人で生きろ、とは言えない。むしろ、互いに支え合って生きていることを、伝えたい。
“元気と迷惑は貸し借りできる”のです。いつからですかね、大人が立派にならなくちゃいけないと思い込んでいるのは。「出来て当たり前」と思っていたら、いろんなことを見逃すと思います。自分自身の頑張りにも気づいてください!