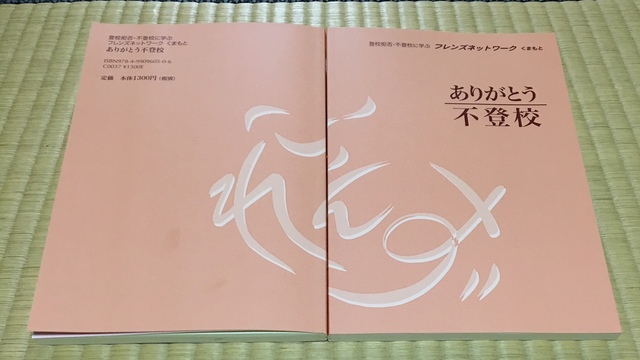親の会報告より
2 特徴を理解して
E祖母:うちの孫は、発達障がいがあります。ADHDと自閉スペクトラム症です。小学校で片付けが下手で教科書をしまう事が出来ませんでした。担任は孫の出来ない事ばかりを箇条書きにして、母親に渡してました。親も何となく気付いてはいたようでした。
将棋が好きで得意として、将棋でバランスが保ててる感じでしたが、それをクラスメートに「自分の方が上手い」などと責められ、学校に行けなくなりました。
絵も風景画は遠近感がつかめず、描けません。幾何学模様は得意です。担任が、孫が描いた風景画を「こんなのは駄目だ」と皆の前で破った事もあり、辛い思いをしました。
進行: 酷い先生ですね。
E祖母:6年生に上がる前に校長に、担任を変えてほしい、持ち上がりにしないでほしいと話をしました。小児科に相談したら、発達の専門の先生がいらしたのでそこで初めて検査をして、発達障がいが分かりました。
うちの孫の場合は黒板が写せない、同世代の子と遊べない、話をすぐには理解できないという特徴がありました。
どんな事が苦手か分かればそれに対応できるし、どうすればやり易いか考える事が出来て、子どもも理解していきますよね。「発達障がいだよ」で済ませるのではなく、こんなところが苦手とか、こんな事が得意だと話ができると思います。
D : 親や学校の先生とか、周りの大人がその子の特徴を理解するための検査、ということですよね。
B母: うちの息子も、自分はこんなところがあるからっていう話ができます。発達障がいという言葉は使わなかったです。特徴が分かった方が周りもやり易くなるという事を、お医者さんがよく話してくれました。
進行: 検査はどうフォローするのかが、一番大事ですよね。本人がどんな状態かしっかり見て、相談されながら決めていかれたらいいのかなと思います。