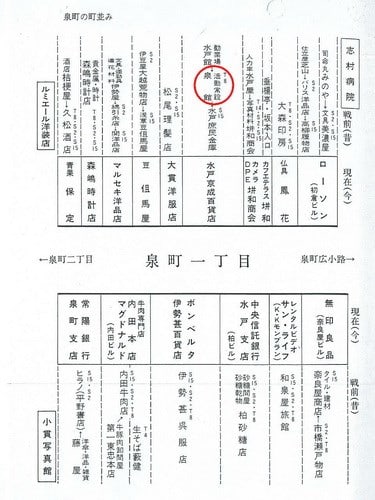驚き半兵衛
水戸の町はずれに半兵衛というあわて者がいて、あるあまりに暑い夏の暗い夜に丸裸で外に出たところ、夜警の同心に気づかれて追いかけられ、酒門村の知人の家に逃げ込んで、小さな女の子の白い着物を着て再び逃げて、清巌寺に至ったそうです。坊さんが戸を開けると、暗い中、半兵衛が足のない白い幽霊に見えて、坊さんは本堂に逃げて念仏を唱えたそうですが、その幽霊が追いかけて来るので、鐘楼の鐘をならしたそうです。村の人々が集まってきたそうですが、幽霊は半兵衛とわかり大笑いになったそうです。それであわて者のことを、「驚き半兵衛、夜半の念仏」というようになったそうです。写真は清巌寺山門です。
熊の恩返し
むかし宿屋の主人と、おかみさん、きみ子という娘がいたそうです。主人が山で熊を撃ったそうですが、子熊がいたため家に連れ帰って育てて山に返したそうです。きみ子が病気になり、薬に熊の生き肝を食べればと主人が山に入ったそうですが、心配して後から行ったおかみさんを撃ってしまったそうです。後妻を迎えたそうですが、後妻はきみ子の両手の指を切り落として家を追い出したそうです。行くところがなく、山に入ったきみ子のもとに、毎日食べ物が置かれ、それは助けた熊が運んでくれたものだったそうです。その後、里へ戻ったきみ子は親切な人びとに囲まれて、結婚をして子供も持ったそうです。井戸で水を汲んでいて、指がないので井戸に子供を落としてしまったそうです。きみ子が井戸のつるべにぶら下がって子供を助け出そうとすると、指が生えて、子供を助けることができたそうです。

下馬橋
旧湊街道の東大野と圷大野との境にある用水路にかけられた橋だそうです。香取稲荷神社の神前にあり、この神社の神力によって、殿様はこの橋から極楽橋の間は駕籠を降りて歩かなければならなかったので、下馬橋という名前がついたそうです。
晡時臥山の蛇
晡時臥山(くれふしやま)に兄(努賀毗古(ぬかびこ))と妹(努賀毗咩(ぬかびめ))の二人が住んでいたそうです。ある時、妹の寝室に男が通ってきて、妹は身ごもり、小さな蛇を産んだそうです。妹と兄はは蛇は神の子であろうと考えて、さかずきにいれて祭壇に安置したそうですが、一晩でさかずき一杯になり、次に瓮(ひらか)にとりかえましたが、これもすぐにいっぱいに成長して、これを繰り返したそうですが、器が間に合わなくなり、これ以上は養えないので父のもとへ行くようにいったそうです。子は泣き悲しみ、それなら童(わらわ)を付けてくれといったそうですが、いないからと断ると、兄を殺して天に昇ろうとしたそうです。妹はびっくりして瓮を投げつけると昇天できなくなって晡時臥の峰にとどまったそうです。その子孫はやしろを建てて、今も祭礼を行っているそうです。晡時臥山は、朝房山のことだそうです。

かじや窪の恋
昔、字(あざ)鍛冶屋に美しい娘がいたそうです。娘が毎晩家を出るので、母が、娘の懐に糸をつけたところ、行く先は鏡智院とわかったそうです。娘は鏡智院の坊さんと恋仲だったのだそうですが、そのことが知れてしまったので、二人は斧沼(よきぬま)への身投げをよそおって京都へゆき、織物の修行に励んだそうです。叔父が二人を探して京へゆき、帰るように説得したそうですが、二人は帰ることをこばんで、十三仏を織り込んだ西陣織を土産にくれたそうで、それが今でも宝憧院に保存されているそうです。
水戸の伝説(4)