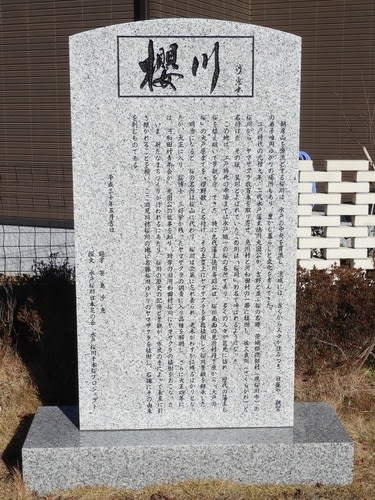水神社 手挟み(たばさみ 北見町36°22'37.2"N 140°28'46.6"E)
ここには、水神社と稲荷神社が並んでいます。写真は、水神社の手挟みに彫られた波と千鳥です。稲荷神社も波と千鳥の手挟みです。「波に千鳥」ということわざがあって、梅に鶯などと同様、組み合わせの良いもののたとえだそうです。「波千鳥」という、波と千鳥を組み合わせた縁起の良い伝統的模様もあるそうです。そうした縁起の良さや、防火の水があることから彫られたのでしょうか。

染付波涛千鳥文蓋付碗(そめつけはとうちどりもんふたつきわん 二の丸展示館 三の丸2-6-8)
二の丸発掘調査で出土した、江戸時代肥前産の蓋付碗だそうです。これは、あまり強く様式化していない、絵画的雰囲気を残した図柄のようです。

別雷皇太神手水舎懸魚(べつらいこうたいじんちょうずやげぎょ 元山町1-1-57)
これも波と千鳥の意匠のようです。神社建築のさまざまなところで、波と千鳥の意匠は使われているようです。

偕楽園紅千鳥(常盤町1-3-3)
3月から4月上旬にかけて咲く、遅咲きで一重の紅色性品種だそうです。オシベも紅色で、花付きがよいそうです。写真は平成31年2月のものです。

錦糸南天(水戸市植物公園 小吹町504)
江戸時代に発達した園芸品種のナンテンだそうです。大千鳥と表示されています。千鳥という品種は江戸時代にすでにあったそうです。細い枝が巻いているのを水と見たのでしょうか。水戸錦糸南天同好会の植栽で、写真は平成31年1月です。