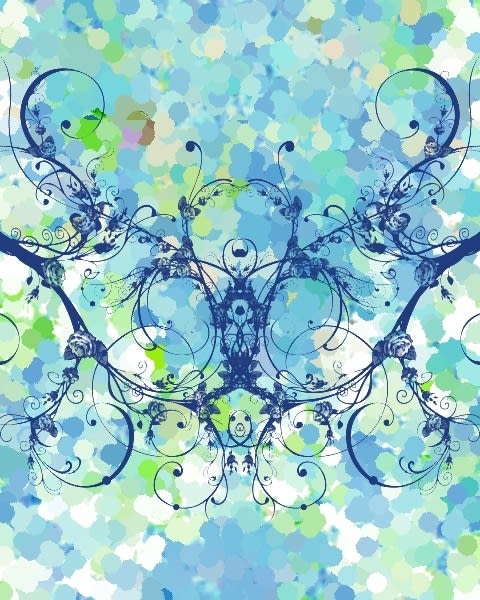素材は、
mabotofu様からお借りしました。
「FLESBLOH&OD」の二次小説です。
作者様・出版社様とは一切関係ありません。
ディズニー映画「ノートルダムの鐘」風のパラレルですが、一部キャラ設定や時代設定が違っていたりしますが、それでもいいよという方のみお読みください。
海斗が両性具有設定です、苦手な方はご注意ください。
遠くで、狼の声が聞こえた。
「さぁ、急ぎませんと・・」
「わかっているわ。」
数人のロマ達は、森を抜け、川を渡りパリへと向かった。
だが、彼らは船頭に騙されていた。
「約束した金は払った筈だ!」
「あの金の五倍くらい払っていないと、話にならない。」
「そんな・・」
彼らの間に流れる険悪な空気を敏感に感じ取ったのか、ロマ女の腕に抱かれていた赤子が激しく泣き出した。
「泣かないで。」
「おやおやこれは、随分と賑やかだと思ったら・・」
蹄の音と馬の嘶き声が聞こえた後、一人の男が川岸に現れた。
「ウォルシンガム判事・・」
「この者達を牢へ。」
ロマの男達が鎖で繋がれているのを見たロマ女が赤ん坊を抱いたままその場から逃げようとした時、一人の兵士が目ざとく彼女を見つけた。
「あの女、何かを持っているぞ!」
「盗人だ、捕まえろ!」
ロマ女は、脱兎の如くその場から逃げ出した。
「誰か、助けて!」
彼女は、必死に大聖堂の扉を叩いたが、中から返事はなかった。
「待て!」
「やめて、離して!」
ロマ女と揉み合いになったウォルシンガム判事は、ロマ女を誤って突き飛ばしてしまった。
石畳の階段に頭を強く打ち付けたロマ女は、その場で死んだ。
ウォルシンガム判事は、ロマ女が腕に抱いていたものを取り上げた。
それは、灰青色の瞳をした赤ん坊だった。
だが、その右目には醜い火傷痕があった。
「何と醜い!」
彼は赤ん坊を井戸の中へと投げ入れようとした。
しかし、司教がウォルシンガム判事の蛮行を止めた。
「この子を、お前が育てなさい。」
こうしてウォルシンガムは、赤ん坊を“ナイジェル”と名付け、育てる事になった。
同じ頃、ある貴族の屋敷の前に、一人の赤子が捨てられていた。
その赤子には、男女両方の証があった。
「奥様、大変です!」
「まぁ、可愛い子ね。」
貴族に引き取られた赤子は「カイト」と名付けられ、愛情深く育てられた。
十年後、パリは道化の王を祝う祭りが開かれていた。
「お嬢様、余り遠くに行ってはいけませんよ!」
「わかっているわ!」
海斗はそう叫ぶなり、乳母の手を振り切り、広場に向かって走り出した。
その途中で、海斗は一人の少年とぶつかった。
「ごめんなさい、大丈夫?」
「うん、大丈夫。君の方こそ、怪我は無い?」
そう言った少年は、灰青色の瞳で海斗を見た。
「あなた・・」
「何をしている、早く来い!」
「すいません!」
少年は海斗に一礼した後、雑踏の中へと消えていった。
「カイト様、こちらにいらっしゃったのですね!」
「ごめんなさい。」
「奥様があちらでお待ちですよ、参りましょう。」
海斗は乳母と共に、広場の中央にある貴賓席へと向かった。
そこには、自分とぶつかった少年の姿があった。
「あら、ウォルシンガム判事、あなたも来ていたのね?」
「奥様、お久し振りでございます。そちらの可愛いお嬢さんは?」
「わたくしの一人娘で、カイトですわ。カイト、ウォルシンガム判事にご挨拶なさい。」
「はじめまして、カイトと申します。」
「美しいお嬢さんですね。ナイジェル、こちらに来なさい。」
「はい・・」
ウォルシンガム判事の背中に隠れていた少年は、海斗を見た途端、顔を赤くして俯いてしまった。
「まぁ、恥ずかしがり屋さんなのね。」
「申し訳ございません。」
「いえ、いいのよ。ナイジェル君、カイトと仲良くしてね。」
「はい・・」
はじめはぎこちなかったナイジェルと海斗だったが、次第に打ち解けていった。
「ねぇ、ナイジェルはどうして、右目に眼帯をしているの?」
「俺には、火傷痕があるんだ。」
ナイジェルはそう言うと、右目を覆っていた眼帯を外した。
そこには、醜い火傷痕が広がっていた。
「痛そうね・・」
「ううん、痛くないんだ。ただ、この火傷痕を見て皆が怖がるから、眼帯をつけているんだ。君は、怖がらないね?」
「わたしは、あなたの瞳の色が好きよ。」
海斗はそう言うと、ナイジェルに微笑んだ。
その瞬間、ナイジェルの胸に天使が放った恋の矢が刺さった。
「どうした、ナイジェル?顔が赤いぞ?」
「いいえ、何でもありません・・」
ナイジェルはウォルシンガム判事と共に屋敷に帰宅すると、自室に入り溜息を吐いた。
「あら、まだ起きていらっしゃるのですか?」
「ええ、少し眠れなくて・・」
海斗はそう言うと、ハンカチに何かを刺繍していた。
「それは?」
「ナイジェルにあげるの。」
「きっと喜んで下さいますわ。」
「そうね!」
翌日、海斗はナイジェルにハンカチを贈った。
「ありがとう、大切にする。」
「喜んでくれて良かった!」
道化祭りで出会って以来、海斗とナイジェルは良く二人だけで遊ぶようになっていた。
「ねぇナイジェル、将来・・大人になったらわたしと結婚してくれる?」
「あぁ、勿論さ、約束だ!」
しかし、幸せは長く続かなかった。
海斗の養父母が流行病で亡くなり、彼女は孤児院に引き取られる事になった。
「カイト、これ・・」
別れ際、ナイジェルが海斗に贈った物は、中央にペリドットが嵌め込まれたロザリオだった。
「ありがとう、ナイジェル!」
海斗は、孤児院で生活を始めたが、そこは暴力に満ちた場所だった。
海斗達は早朝から深夜までこき使われ、粗末な食事で命を繋いでいた。
(お父様、お母様・・)
夜寝る前、海斗は亡き養父母の事を想い、泣いた。
ナイジェルも、養父の虐待に耐える日々を送っていた。
「可哀想に、鞭で打たれたんだね。」
「大丈夫だ・・」
白いハトのジャニスは、ナイジェルを慰めるかのように、彼の肩にそっと乗った。
「どうして、あの人は俺を殴るんだろう?」
「世の中には、人や動物を虐めて喜ぶ奴が居るのさ。」
「そうか・・」
ナイジェルは、粗末な寝台に横になると、目を閉じて眠った。
(カイトに会いたい・・)
目を閉じて浮かぶのは、海斗の笑顔だった。
また彼女に会いたい。
海斗といつか再会する日を夢見ながら、ナイジェルは孤独な日々を送っていた。
そして海斗もまた、ナイジェルと再会する日を夢見ていた。
それから、二人が出会って十年の歳月が経った。
「ナイジェル、もたもたするな!」
「はい・・」
雪が舞う中、道化の祭りはいつものように、賑やかに行われた。
―あれは・・
―ウォルシンガム判事の・・
―綺麗な方ね・・
―右目の眼帯がセクシーだわ・・
女達から熱い視線を送られている事など気づかずに、ナイジェルは祭りを眺めていた。
そんな中、一人の少女が自分の方へと向かって歩いて来る事に気づいた。
彼女は、炎のような美しい赤毛をしていた。
「カイト・・カイトなのか?」
「ナイジェル、ナイジェルなの!?」
突然の再会に、ナイジェルと海斗は驚き、その後共に喜んだ。
「ナイジェル、元気そうで良かった!」
「カイトも、元気そうで良かった。」
海斗はそう言うと、ナイジェルが抱いているハトに気づいた。
「その子は?」
「ジャニス、俺の唯一の友だ。こいつにも、祭りを見せてやりたくてな。」
「そう・・」
「ナイジェル、何をしている、早く来い!」
「カイト、また後で会おう。」
「ええ。」
道化の祭りの後、ナイジェルはノートルダムの鐘楼でジャニスを看取った。
友を喪い、悲しみに打ちひしがれているナイジェルの元に、一匹のネズミがやって来た。
「お前は・・」
そのネズミの白黒模様を見たナイジェルは、そのネズミが数日前ナイジェルが水溜まりから助けたネズミだという事に気づいた。
「済まない、お前にやれる物はこれしかなくてな。」
ナイジェルはそう言うと、ひとかけらのパンを差し出した。
ネズミは嬉しそうに鳴き、パンを両手に持って、壁に開いた穴の中へと消えていった。
「カイト、どうしたの?」
「いいえ、何でもありません。」
「そう・・」
海斗はバルコニーから自室へと戻ると、寝台に横たわった。
彼女が今居るのは、二番目の養父母の家だった。
最初に海斗を育ててくれた養父母は海斗に莫大な遺産を遺してくれたが、その遺産は養父母の親族に奪われてしまった。
孤児院で辛い生活を送った後、二番目の養父母が海斗を生き地獄から救ってくれた。
「今日はお祭りだったわね。」
「ええ。そこで、昔の友達に会いました。」
「まぁ、それは良かったわね。」
二番目の養母・クララは、そう言って海斗の髪を撫でた。
「明日の舞踏会の為に、早く寝なさい。」
「お休みなさい、お義母様。」
(ナイジェルと、また会えるかな?)
海斗はそんな事を思いながら、眠りに就いた。
ウォルシンガム判事は、朝を告げる鐘の音で目を覚ました。
「おはようございます、旦那様。」
「朝食の後、出掛ける。馬車の支度を。」
「はい。」
同じ頃、ナイジェルは鐘楼から外へと抜け出し、誰も居ないパリの街を歩いた。
いつも鐘楼の上から見下ろしていた街は、雑然としていて、狭い世界に生きていたナイジェルの目には鮮やかに映った。
暫く街を歩いて、ノートルダム大聖堂へとナイジェルが戻ろうとした時、一匹のネズミが彼の前を横切った。
それは、あの時の白黒模様のネズミだった。
「よぉ、また会ったな。」
ナイジェルはそう言ってネズミを見ると、ネズミは嬉しそうに鳴いた。
「どうした?食い物が欲しいのか?残念だが・・」
「ナイジェル。」
背後から声がしてナイジェルが振り向くと、そこには海斗の姿があった。
「カイト・・」
「この子は、あなたのお友達なの?」
「あぁ。」
ナイジェルはネズミを肩に乗せると、ネズミは嬉しそうに鳴いた。
「こんにちは、ネズミさん。パンをどうぞ。」
海斗はネズミにパンのカケラを渡すと、ネズミはそれを受け取ってナイジェルの肩の上で食べ始めた。
「また、ここで会えるか?」
「ええ。」
海斗と噴水の前で別れたナイジェルは、それから毎朝噴水の前で会うようになった。
二人は、十年間―自分達が離れ離れになっていた間の事を話した。
「じゃぁね、ナイジェル。」
「あぁ。」
海斗はナイジェルと別れ、自宅へと向かっていると、突然彼女の前に数人の男達がやって来た。
「お嬢ちゃん、俺達と遊ばない?」
「通して下さい。」
「へへ、恥ずかしがるなよぉ~!」
男がそう言って酒臭い息を吐きかけた後、海斗の腰に手を回そうとした。
だがその前に、一本の矢が男の足元に刺さった。
「おや、失礼。大きな猪が居たから、今日の夕飯にしようと思ったんだが・・」
「てめぇ、誰が猪だ!」
「そのお嬢さんから手を離しな。」
「ひぃっ!」
酒臭い男は突然現れた謎の男に剣を突きつけられ、情けない悲鳴を上げて逃げていった。
「大丈夫か?」
「は、はい・・」
美しい金髪をなびかせた男は、蒼い瞳で海斗を見つめた。
「パリには最近、変な奴が流れて来る。若い娘の一人歩きはそういった輩に狙われるから、気を付けた方が良い。」
「あの、これを・・」
「礼は要らん、またな。」
真紅のマントの裾を翻しながら、謎の男は海斗の前から去っていった。
(素敵な人だったな・・)
「カイト、紹介するわね。こちらはジェフリー=ロックフォード様、お父様のご友人よ。」
「初めまして、カイトです。」
「美しい赤毛ですね。」
「ありがとう・・」
滅多に褒められたことが無い赤毛をジェフリーから褒められ、海斗はそう言った後、恥ずかしくて俯いた。
「ねぇあなた、あの二人、すぐに仲良くなったわね。
「あぁ。それよりもクララ、“例の件”はどうなっている?」
「それは、わかりませんわ。」
「そうか・・」
クララの夫・ユリウスは、そう言うと溜息を吐いた。
海斗は、自室で夜眠る前の祈りを捧げていた。
(ナイジェル、どうしているのかしら?)
月光を受け、ロザリオの中央に嵌め込まれたペリドットが美しく輝いた。
「クソッ、やられた・・」
怒りに震えながら、ビセンテ=デ=サンティリャーナは愛馬で賊を追っていた。
その途中、ビセンテは一人の少女とぶつかりそうになった。
「すまない、怪我は無かったか?」
「はい・・」
ビセンテは、少女と目が合った瞬間、彼女に一目惚れした。
(彼女は、わたしの守護天使なのかもしれない・・)