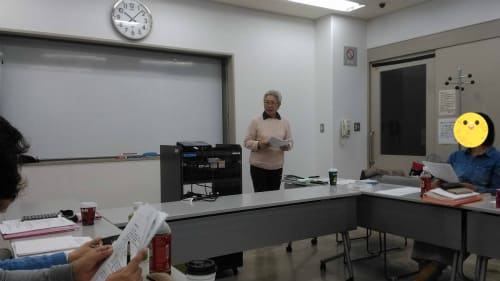
みんなきっと心配していただろうな~ アリガト♪
発表の間何度もあたたかいビームを感じてました。アリガト♪
当事者より落ち着きのなかったチャーリーママさん。アリガトゴザイマシタ♪
自分の記録として残しておこうと思います。
チャーリードッグスクールインストラクターコース全10課題の提出が終わると最後に1時間の発表です。
今回お題がなかったので、自分と犬とのルーツ、自分がChoco.と暮らし始めてから今までやってきたことと、
私の犬との暮らし方に大きな影響を与えたCDSの犬学について話そうと思って準備を始めました。
準備のためにブログをはじめ、今まで参加した座学のハンドアウトや自分のノートを読み返しました。
それはそれは膨大で、このテーマを選んだ自分を半ばあきれながらもそのテーマから離れられずにいました。
なぜなら、これがもはや自分の中の基本のきになってしまっているからでした。
Choco.と暮らす前にすでに飼い主がいない、新しい飼い主を探している犬たちと出会っていました。
保護団体のボランティアをしていたからですが、きっかけは単に犬に触りたかったから…だと思います。
そこにいたのは北関東の野良犬の子どもたちで、県内では里親を見つけることが難しいということで
わざわざ都会の家庭に迎えてもらうための里親会でした。
それがだんだんブリーダー崩壊や飼育放棄などの理由を持った純血の小型洋犬が増えてきました。
そんな事実に理不尽な思いをずっと持っていましたが、我が家は犬や猫の飼育は禁止されていたので、
預かりさんもできなければ、そういう子たちの里親にもなれません。
救ってあげたいのに、できない葛藤の中にあって、里親会からフェイドアウトしてしまいました。
そんなときに、Choco.出現だったのです。(保護団体経由でなければ、家の子にするチャンスでしたから!)
Choco.も飼育放棄犬でしたから自分の中ではホッとした思いがありました。
でも・・・犬との暮らしは楽しいだけではありませんでした。
ビーグルは、森の中を仲間とともに獲物を追いかけて行って吠えて知らせるために
森の中でも声が通るように大きな声を持っているわけです。
それが、隣近所がひしめき合っている住宅では吠える声が問題とされます。
それをいけないといわれても、いけないがなにかわからないわけで、それをいくらトレーニングで
なんとかしようとしても、本能に埋めこまれているものはなかなか思うようになりません。
家で無駄吠え・・・はありませんでしたが、外ではいろいろなものに吠えました。
Choco.はビーグルが入っているから吠えやすいのは致し方ないこと・・・と
わかってあげられるようになったのはCDSの座学で学ぶようになってからでした。
私もそうでしたけど、飼い主さんの多くはそういう風には教わりませんし、
トレーナーもそういう指摘はしません。
単にヒト社会の中ではそれでは困るからと、罰を使って封じ込めようとしたり
違う行動ではぐらかしてやりすごそうとする方法をとることをすすめます。
理由はどうであれ吠えないことだけを目的にトレーニングします。
その結果副作用が出てしまってますます困窮する飼い主さんを作ってしまうのが
多くの巷のトレーニング方法です。
そういう方法をとらずに犬を知り、犬の心を、感情を尊重しつつ
ヒト仕様の罰を使わず解決しようと考えて学んでいるのがここにいる私たちです。
そうなんです。しつけじゃなくて、暮らし方なんです。
犬がやることは間違っているからそれを正さなければ・・・
ヒト社会のルールを教え込もうとか…ではなくて
ヒトと犬が安心して暮らせる暮らし方をお互いを思いやりながら探していこう♪
私はそんな気持ちでいます。
そういうときに一番大切なのは、好子のシャワーを惜しみなく降り注ぐことです。
だからこれからもずっと「名前を呼んでおやつ」を極めていきたいと思います。
ゴールに到達することを求めてはいません。
過程を大事にしたいんです。
始まりや途中がつらくても、乗り切れる力がついてくる・・・
自分だけではとうていできそうもないものでも周りから助けてもらいつつ学ぶって
本人、本犬にとってこんなに幸せなことはありません。
それが散トレですよね。
わたしは何に向かっているんだろうか・・・と考えることがあります。
やっぱり、飼い主さんがなんとか踏ん張れるように支えたい・・・
結果的に、センターにくる子を減らしたい・・・
これからもそれらを目指して学びも活動も続けようと思っています。

このまなざしに応えなければ・・・
この一年、散トレや部活で一緒に歩いたみなさんとわんこさん、
座学で泣き笑いしながら学びあった皆さん、
ヨコハマ座学でわたしの発表をあたたかい目と耳で聞いてくださったみなさん、ありがとうございました。
発表までの課題についていつも的確で心がほんわりとする講評をくださった
チャーリーママさん、あ、皆さんのように夏目先生とこれからは呼ばせていただきます。
ありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いします。











