

・筑波大学名誉教授 ・元 日本サッカー協会理・元 筑波大学蹴球部監督
い返せば、まだまだ対応の仕方があるように思えます。
しかし このような恐怖に似た心配は、今の若い人々にとっては初体
験です。きっと自分の判断が適切かどうか 不安に思えてしまうので
はないでしょうか。戦争に関わる実体験は、必ずしも人生の関所と
は思っていません。 しかし それに代わるものが必要な気がします。
手前みそになりますが、体育・スポーツの必要性重要性が その辺に
あるような気がします。
●人間はいろいろな面で大変特殊な動物だと思います。
その一つにその動物が種を残せる状態(子孫を残せる状態 即ち生殖
活動が可能になる時期)になる事が、その動物の完成期と考えると、
この状態になるまでの期間が他の動物と比較して 人間は大変長いと
いうことです。
例えば犬などは、誕生から2年もすると交尾をして 子犬を生みます。
これが植物になるともっと短時間です。 私たちの主食である米など
は、種子籾を苗代に早春蒔きますと、初秋には稲穂が実り 収穫する
ことができます。
生殖活動までいかなくても、私たちの身近な動物を見ていると その違
いは明白です。例えば馬の誕生を見ていると、仔馬が誕生した数分後
には、細い華奢な四脚をフラフラさせながらも自分の脚で立ち、周囲
を跳びはねるまでになります。また野鳥の卵が孵ってひな鳥が生まれ
ると、数週間後には親鳥から離れ、巣立っていきます。
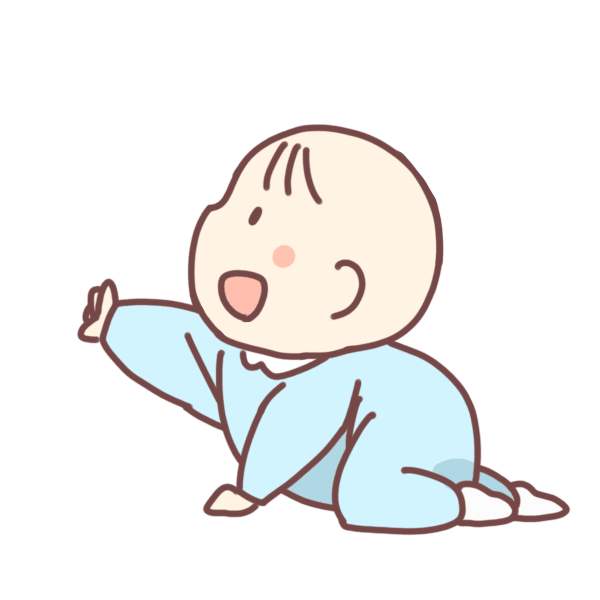
●これに比べ人間は誕生してから四這 、そして2本の脚で立ってヨチ
ヨチ歩き、そして自由に動き回れるようになるまでに2~4年はかか
ります。
そして自由自在に動き回れるようになりながらも、その後、小学校、
中学校、高等学校と両親の保護のもとに成長し、大学を卒業してやっ
と身体的にも精神的にも自立して、社会に巣立っていきます。
この間約22年、何の生産的な行為もせず、ただひたすら実社会へ出
て自活(自立)するための準備をするといっても過言ではないでしょう。
それではその期間の彼らの生きる糧や、ほしいものを手に入れるお金
はどうしているかといえば、親からの援助であり、仕送りです。
特に高校生期、大学生期は 冒頭記した人間の完成期(種が残せる状態)
にさしかかりながらも、未だ自分で自分の生活の糧を得ない状態に居
るという事です。
これは現在の日本の社会構造が、そのようになっているから可能な事
であって 、フィリピンの田舎に行けば小学生の頃から一家を支えるた
めに懸命に働いている 子供は数えきれないほど居ます。 インドネシア
マレーシア、イラン、ブラジルなどでも同じような光景を見ることが
できます。
●このようなことを思いながら、サッカーというスポーツを眺めると
き、サッカーは他の動物の成長ではなく、人間の成長によく似ている
ように思えます。
それはボールを扱うという技術を習得するためには、非常に長い時間
がかかること、技術の習得とは攻撃の手段を獲得するということです。
攻撃は明るく、楽しく、希望に満ちた世界です。

●幼稚園、小学校、中学校位までは、この世界の人間としての側面を
伸ばし、人生の楽しさ、明るさ、希望、夢を育む時期です。
この時代は実に自由で活発で束縛や規制をできる限り受けない自由な
発想、何の先入観も持たない創造性、奇抜なアイディアなどが生み出
されなければならない時期だと思います。
この時期に変な束縛をして、いらぬ先入観を入れられては 自由奔放な
攻撃のアイディアは生まれて来ません。
しかしこの時期を過ぎて、一人前の人間となりつつある高校生(厳密
には トップの競技者育成では、小学生高学年あたりから徐々に)にな
ったなら、自分の生活の糧といっても過言でないBALL(サッカーの
ゲームで唯一のもの)を自分で獲得する術と努力を身につけなければ
なりません。

それまでの“子どもの時期のサッカー”では、どこからかBALLが自分
たちのチームに転がって来ることを前提として 攻撃を考えても許さ
れる(親の保護で生活する)ものでした。
このBALLを獲得する行為、それよりも重要な自陣のGOALを守ると
いう行為、即ち守備、これは大人のサッカーの必要絶対条件なのです。
●高校生のサッカーが、子どもから大人のサッカーに変わる転換期で
あるならば、こ の守備に対する考え方をこの時期に徹底させることが
不可欠です。この守備という障害を突き付けられたとき、攻撃はそれ
を乗り越えるためのアイディアと術を工夫し、練習し獲得していくも
のです。高いパフォーマンスを示すチームには、高い守備能力があり
ます。

その高い守備能力を乗り越えようとする攻撃の工夫とたゆまぬ努力が
サッカーの競技力向上をもたらすのです。すなわち、この攻撃能力の
向上が次に守備者に対し、大きな課題となって守備能力の向上へとプ
レイヤーを駆り立てるのです。
このような環境ができたチームが他のチームと競い合った時、 勝利と
いう自分たちの努力の証を得ることができるのだと信じています。
しかし、ただ単に高い守備能力と表現しましたが、この能力の獲得は
そう短期間に簡単にできるものではありません。
トレーニング、栄養、休養、そして知的学習、まさしく自分の生活を
律してはじめて獲得できるものです。これはまさに私たちの実生活に
おける労働の側面に該当するものだと思います。
●すなわち労働は、自分の都合や気分や身勝手で行うものでなく束縛
や規制や約束事の中で 責任と信頼に裏付けられた大人の世界の事なの
です。
あまりにマイナス的要素を口にしたくありませんが、現在のJリーガー
の中にも、これに気づいていない何人もの身体とプライドだけが大人の
プレイヤーを見るとき、日本のサッカーはまだまだ進歩の途上にあると
の再確認をせずにはいられません。

●成熟人の日々は、我慢に我慢して働いて(労働)得たお金を使って、
自分(自分たち家族)が待ちに待った週末に楽しい、好きなことを、
おもいっきりする(攻撃=人生の華)。言い換えればその好きな攻撃
がしたいがため 私たちは日々労働をしているといっても過言ではない
のではないでしょうか(完)

「松本光弘 筑波大学名誉教授のご紹介」
●まずは、新しく執筆陣に加わった松本先生をご紹介したい。
40年前のある日、英国ロンドンシティ ハイドパークに
にある世界のサッカーの総本拠 THE FA 英国サッカー協会
のクロッカー事務総長が取り持つご縁でお付き合いが始まり、
今日に至る。まさに奇縁である。
当方は戦中ッ子のため スポーツとは無縁で育ち 口と頭だけで
終生、生き永らえててきたが、その間けじめけじめで、いつも
快く仕事をサポートしていただき、それをほぼ酒で濁してきた
趣がある。
日本サッカーの黎明期を、川渕三郎会長とともに切り拓き 卓抜
な指導者として活躍された結果、今の隆盛な日本サッカー界が
ある。どちらにしても頭が上がるはずがない。
これからは、社会貢献の国際交流サイトで、余後のお付き合い
が始まる。 (Yama)


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます