
■■■■■■■■■■連鎖する貧困■■■■■■■■■■
⬛️⬛️「日本経済の現況」
⚫️3年来のコロナが収束して、やっと柳眉を開きつつあるところだ.
しかし国内需要が低迷するなか、原材料や 食料価格の高騰や円安の
為替要因も加わり、日本経済はインフレ傾向にある。
理由はウクライナ戦争による一時的な資源高騰もある。しかし賃上げ
は、少し動き出したものの一般賃金は殆ど上がっていない。
本来日銀が目指した金融緩和による2%の物価上昇による[インフレ」
によ,国内の需要や賃金の上昇を伴う「良いインフレ」のはずだ。

⚫️先日, 黒田日銀総裁が任期を終え、学者の植田新総裁が跡を継いだ。
安倍元総理と黒田総裁のコンビで探求した
・「2%というほど良い循環による賃金の上昇」
・「消費拡大による景気の上昇」
は、残念ながら目標には至らなかった。
この2人の10年に及ぶ努力は、コロナパンデミックやウクライナ戦
争など予期せぬ出来事に阻まれたが、デフレ脱却のために大きく貢献
した事に変わりはない。
その安倍総理は既に亡く,黒田総裁は去り,植田新総裁が再びこの実現を
目指す事になる。
⚫️最近の日経新聞や経済誌の専門家によると,日本の「デフレ脱却
と良いインフレ」は, 日銀の施策だけではとても実現が難しく,,政
府による減税(例えば消費減税)や,思いきった財政出動を伴うべきと
提言している。
専門家によると、消費税を5%減税すると、ーーー
・消費者の給与が5%上がり、
・消費者物価が5%下がり、
・実質的に消費を5%押し上げる
という。
ところが最近情報によると政府(財務省)は、少子化対策や国防予算の
拡大に伴い, その財源を消費税増税や社会保険料の増額に求めようと
しているという。
そんなことをすると, 経済が拡大するばかりか逆に経済が閉塞に向う
事は判っているはずなのに, なぜこのような事をするのか政府内の二
律背反的な動きに対して,非難の声が挙がっている。
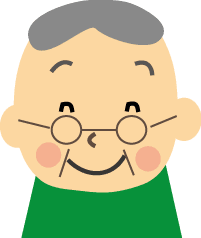
⬛️⬛️[高齢者の実像」
⚫️いま日本では、高齢者の「おひとりさま」が急増している。
・体調変化への対応遅れ.
・特殊詐欺被害やゴミ屋敷のの増加、
・空き家の増加
といったリスクを高める側面もあるだけに, 地方自治体は 3世代同居
を促したり, いろいろ知恵を絞る。
都道府県間の独居率の差は最大14ポイント。でも少子高齢化に歯止め
がかからない。

⚫️「日本の高齢者の実像」(データ)
・百歳以上の高齢者人口 65785人
・90歳以上の人口 206万人( 1.9%)
・80歳以上人口1074万人(8.5%)
・高齢者の就業者数 807万人
・90歳まで生きる人、男性は9人に1人、女性は4人に1人。
・65歳以上の就業者人口、770万人 (過去最高)
・日本の全世帯数5340万世帯(2.8%)
・日本在住外国人43.6%増、274万7137人(過去最高)


高齢者とお一人さまと痴呆症と介護問題は、それぞれ有機的に関連
する大きな社会的な問題であることがよく判る。
折角の「出会いの人生」が、いつしか孤独な「おひとり様世帯」
とは、なんとも残念な次第だが、人生の明暗を分かつために前向き
に対面する「生きる気概」を失ってはなるまい。
⬛️⬛️「高齢者と新聞」
⚫️いま新聞の存在が,あやうい。1997年5,400万部を記録した日本の
新聞総発行部数は, 25年後の2022年には3,000万部(44%)にまで減少
した。
当然,主要新聞の売上は大幅に落ち込こみ赤字基調のところが多い。
・地域の夕刊を廃止したり、
・週刊誌(週間朝日)を廃刊したり、
必死の経営努力をすれど底が見えないと言う。
その理由について媒体各社は,何処も同じこんな分析をしている。
「スマホやインターネットの普及で,新聞が読まれなくなった」と。
⚫️日本の新聞全国紙の発行部数」(2022年、日本ABC協会調査)
・読売新聞:6,677,823(-370,903)
・朝日新聞:3,993,803(-626,041)
・毎日新聞:1,871,693(-114,646)
・日経新聞:1,702,222(-151,434)
・産経新聞:1,008,642(-82,424
昔から日本の全国の家庭では、全国紙か地元地方紙,最低1紙が毎日
購読され,家庭における社会の情報元として, また子どもたちのため
の教育素材として大きな役割を果たしてきた。
⚫️東京や大阪の大手新聞社は, 度重なる都市再開発で本社ビルをオ
フィスビルに変容して経営改善に取り組む。
経営指標を見ると名目は新聞社だが,業容は不動産業というところが
多い。
戦後,新聞の後にお目見えしたテレビやラジオなどの放送媒体は,国民
の財産と言われる政府管轄の情報通信網を利用して, 多くの読者と密
接に接してきた。
そして情報と教育と生活は、国民生活の三位一体とも言われる基盤を
築いてきた。特に戦後昭和の経済振興期には, 消費経済拡大のための
戦略的な媒体として,極めて大きな経済効果を生み出てしてきた。
世界大戦の敗戦国の日本が, 戦後僅か30年にして,国民総生産(GDP)で
世界第2位に踊り出たと言う事は、まさに快挙としか言いようがない。
これに果たした新聞やテレビなど所謂マスコミの果たした役割は,計り
知れず大きい。
この様な情報は 少なくとも平素、新聞や経済誌を読んでいないとな
かなか理解がむつかしい。ところが私の知る限りでは,多くの日本の
高齢者は, アベノミックスや、それによる株価の上昇や、景気回復,
日銀の総裁交代も知らないし、余り関心を持ち合わせていない。
にも拘らず手元の物価が少しでも上がると, 声高に政府や組長を批判
するが、その何故を探ろうとはしない。
そんな生産性のない高齢者層が、日本の全人口の約3割をしめつつあ
る現実を無視する譯にはゆかない。
⚫️一方,デジタルの世界では,GAFAをはじめ「チャットGPT」の様に,
新しいビジネスのシーズを求めて, 虎視眈々と日本市場への進出を目
指すケースが後を絶たない。
新聞も読まない情報と隔絶した日本の高齢者の増大と,極めて高度な
情報化を目指す日本経済のデジタル化とは, 何かしら二律相反的な現
象に思えてならない. しかも先端的なデジタル国家を目指す日本最大
の苦悩ともいえる。
しかもこの高齢者が, ほぼ生産性がないにも関わらず,社会保障などの
政府支出では, 拡大一途の危惧が漂う。
しかも60代以上の高齢者の中には「情報源はスマホだけ」という
ケースも少なくない。しかもネット情報をいっさい目にしない高齢者
も多い。そして新聞もテレビ欄を見るくらいで, 中の記事を精読する
高齢者はごく少数派だという。
⬛️⬛️「未来の年表」
⚫️今から5年程前「未来の年表」河合雅司著と言う 日本の将来人口
を予測した本が出版され,大きな反響を呼んだ。

すでに5年を経過したが,全ての予測が的中し,著者が危惧した多くの
課題が現実の事となってきた。
・日本の出生数が100万人を切る。(実際は80万人を切つた)
・IT技術者が不足し始め、技術大国の地位が揺らぐ。(2019年)
・女性の2人に1人が、50歳以上に。(2020)
・3人に1人が65歳以上の「超高齢者大国」になる。(2024年)
・「高齢者の独り暮らし」が本格化する。(2022年)
・銀行や百貨店や老人ホームが.地方から姿を消す。(2030年)
⚫️一次殷賑を極めたテレビも,NHKの受信数が低下を続けている。
スマホからYouTubeなどで報道を聞くとしても, 若い人と違い縦横
にチャネルを駆使して所定の番組を見る事は,極めて難しい。
しかもいま、フェイクニュース(偽情報)が拡散している。
しかし不器用な高齢者と言えども, 他者と情報を共有できれば, 社会
共通の理解へと進みやすい。しかし
・高齢者の独り住まいが増え、
・独りよがりや、
・ちょっとした事で切れる暴走老人(逆ギレ現象)や、
・モンスタークレーマー
が異常に増加している。
そこには、そんな異端を生み出す日本の人口問題に起因する社会的
な異常が潜んでいると見ていい。

⬛️⬛️「百歳時代の到来」
⚫️日本のマスコミは「百歳時代到来」とはやすが, 私を含めその
年代の人達は,常に死期を予期しながら毎日を歩むか、運(死)を天に
預けて出たとこ勝負で生活するか, 2者択一の毎日である。
一番いいのは, 出たところ勝負の毎日を開き直って明るく歩む事であ
る。しかし自分の体調とか性格とかで, 割り切れない人も多いはずだ。
・当初はこの狙いでスタートしたものの,相談する相手もいなく,何時
しか自暴時期に走る暴走老人もいる。
・中には経年劣化が進み, 「痴呆症」になり施設に入る老人もいる。
このような事を想定すると,必ずしも百歳時代到来がおめでたいとは
考えにくい。

⚫️「晩節における死との対峙」(石原慎太郎)
先日,文芸春秋の特別寄稿「晩節における死との対峙」石原慎太郎著
を讀んだ。慎太郎氏はご存じ,戦後すぐ「太陽の季節」で大学在学中
に芥川賞を受賞した異才である。あの裕次郎の兄貴であり,後に政治
家に転身,大臣や東京都知事を歴任し昨年死去した。
存命なら今年91歳を数える。この寄稿では,米寿をむかえた際の迫
りくる「死」の予感を「人生最後の未知」と捉えて所感している。
「自分が人生のある極点に達したという事実は, これまでの人生の軌
跡をしきりに振り返らせるし,その感慨は齢の数に似合わず あっとい
うまのものだったなという, 呆気ないというよりもむしろ虚しい感慨
に他ならない」と言い、「最後の未知なる己の死を自ら造形した多く
の自殺者たちは, その遺書や周囲の推察が明かすように 多くは老衰に
敗れて死んでいった」と言い「死という決定的な未知への人間にとっ
て反逆のじつは自殺でしかありはしない。しかしそれにはある種の勇
気が必要とされても,所詮は, 屈服敗北としか思われない」と述べてい
る。死期を予測しての思いを綴った一文である。
⬛️⬛️「戦後昭和の偉業」
⚫️私は日本の敗戦後の戦後昭和と言うミラクルな日本経済の復活劇
(戦後15年の昭和40年頃)を身近に見てきた。見て来たというより
日本復活劇の劇中の一人として貴重な体験をしてきた。
大戦により大都会が焦土と化した日本は, 敗戦後7年目の昭和27年
(1952年)の講和条約の発効で, 国際経済社会に復活することになる。
要約すれば,何しろ無資源国の日本が, 敗戦という汚名を手に,無資本
で国際社会への仲間入りを果たしたというのが実状だ。
戦後, 外地の戦場から引き上げて職場復帰を果たした働き盛りの人達
に,戦後教育を受けて企業に就職した我々若者たちが加わり,試行錯誤
の中、一から仕事を創っていったと言っていい。
資本財もなく,全員で知恵を絞る事で,当時の貧しい日本の経済を牽引
した、戦後日本経済の先陣の一人, サントリー佐治 敬三社長(当時)の
一言「まず、やってみなはれ」を忘れる事は出来ない。
何もかもが不足するなか「まず行動する事で 方法を探れ」、すると
必ず手掛かりがつかめ、新しいアイデアが生まれると教えられた。
そして実際に新しい道が拓けた。これが戦後昭和の日本経済を 大き
く索引し世界にはばたかせる大きな動機とパワーになった事は, 間違
いない。
そして敗戦から23年目の昭和43年にGDP(国民総生産)世界第2位
を獲得した。これは、前の東京オリンピックから3年目の快挙だし
日本経済を全世界にアピールすることになった。そして2年後の前の
大阪万国博に全世界から6400万人の人々が集まる礎になったと言
っていい。
⚫️まず戦後昭和,先人の足跡を辿りたい。
・昭和20年(1945年)●敗戦による終戦
・昭和22年(1947年)団塊の世代の出生
・昭和27年(1952年)●講和条約発効、国際社会へ復帰、
・昭和28年(1953年)・朝鮮戦争休戦, 日本テレビ、民間初の放送開始、
・昭和30年(1955年)・自由民主党結成,
・昭和33年(1958年)・テレビ受信契約100万台突破
・昭和34年(1959年)●[貿易の自由化開始」皇太子(現天皇)結婚、
・昭和35年(1960年)●安保条約締結、
・昭和37年(1962年)●LT貿易開始、キューバ危機、
・昭和39年(1964年)●東京おリンピック(94ケ国参加)
●IMF8条国に移行 ●夢の新幹線開通 (東京―大阪間)
・昭和42年(1967年) ・非核3原則, 公害対策法制定
・昭和43年(1968年)●核拡散防止条約、
●GDP(国民総生産)世界第2位
・昭和44年(1969年)・ベトナム反戦運動
・昭和45年(1970年)●大阪万博(6421万人入場)世界に日本をアピール。
・昭和46年(1971年)・中国の国連加盟、
・昭和47年(1972年)●沖縄の本土復帰、
・昭和48年(1973年)●変動相場制(1ドル360円に移行) 第4次中東戦争、
・昭和50年(1975年)●第1回先進国首脳会議(日本参加)
・昭和54年(1979年) 第2次石油危機、ソ連,アフガ二スタンへ侵攻.
・昭和58年(1983年) 大韓航空機ソ連が撃墜、
・昭和60年(1985年)●G5プラザ合意、
・昭和61年(1986年)●男女雇用均等法施業、チェルノブイリ原子力大事故

⬛️⬛️「高齢者の自覚」
⚫️「高齢者の掟」
・深夜便のラジオを聴く。
・パソコンに挑戦し,なじむ。
・新聞や雑誌を読む。
・引きこもることなくどんどん外に出て人に出会う。
・バスや地下鉄に乗る。
・街を歩く。
・何かと人と出会うことで、何かが変わって来る。
⚫️「年寄りのタブー」
・転ぶな。
・風邪引くな。
・義理を欠け。
⚫️色々検証してきたが、日本経済の明日は,非常に心もとない。
日本経済は,安倍さん亡き後, 精彩を欠く。特に
・中国の台頭と、米中問題、
・コロナパンデミック3年のひきこもり、
・サプライチェンの崩壊、
・急速な高齢化、
これらは,10年以上に及ぶ日本経済の停滞を余儀なくした。戦後,無
から立ち上げ,僅か20数年にして 日本経済をGDP世界第2位に
押し上げた先人達の偉業を,いまこそ再現させる時ではないのか。
だからこそ、何もしない何も出来ない高齢者の駄弁は,慎むべし。
日々の情報に注目し,日本経済が完全に立ち直る事ができるよう,改め
て日本の現役世代に熱い視線と声援を送り続けようではないか。(山)


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます