『看護婦が見つめた人間が死ぬということ』 宮子あずさ著 を 読んだ。

宮子あずささんは、この本を書かれた1994年、経験8年目の看護婦さんだった。
内科病棟に勤務し、そこでは高齢者の入院が多いため、年間50人前後の方が亡くなっていた。
職業柄、人より多くの死をみとるうち、自分がいずれは死ぬことについても、受け入れられ、それを受け入れるための考え方を、身に付けられるような気がすると述べている。
「死は新しい世界への旅立ち」という考え方に至ったそうだ。
今、看護師さんと呼ぶべきところだが、当時は看護婦さんという呼称で、私の年齢の者にとっても、「看護婦さん」という包容力をイメージさせてくれる呼び名のほうが温かさが感じられ、本にしたがって、ここでは、看護婦さんとあえて書かせていただいている。
内科病棟の看護婦さんたちの間では、仕事の休憩中などに、時々『自分が死ぬなら何の病気がいいか』『絶対避けたい病気は何か』といったことが話題に上るのだそうだ。
それによれば、死ぬならこれ、と出てくる病名は、一気に決着のつく脳幹部の出血、なのだという。
「ぽっくり願望」は、看護婦さんのあいだにも、根強いものがあると。
反対に、これだけは避けたい病気としてあがるのが、肺がんと膵臓がんなのだそうだ。
肺がんは、モルヒネで痛みは取れても、肺に息が入っていかない息苦しさは、いかんともしがたい。
膵臓がんは、その痛みが強烈な場合が多いという。
胃がん、肺がん、大腸がんなどでは、その臓器そのものが痛む場合よりも、周囲の神経に浸潤したり、骨に転移した部分が痛む、ということが多く、臓器そのものの痛みとしては、膵臓がんが何より痛そうな印象がある、と書かれている。
一方、高齢になればなるほど病気にはなりやすくなる。
だから、死因が老衰という、厳密に加齢による衰弱だけで死んでいく例はほとんどないのだそうだ。
病院に運び込まれて意識がない一番悪い状態でもうろうとしていた間のことは、患者さんは忘れていることが多いという。
その状態から意識が戻ったある患者さんは、”一度死んだ”体験から、
「死ぬ瞬間って、別に痛くも何ともない。
たいへんなのは、そこに行くまでの苦しみだ。
その苦しみだって本当に短い時間で、それほど
大したことじゃなかった。」
と、話していたのだそうだ。
私は、幼いころ小児喘息でよく床についていた。
大人になってからも、20代に長いこと病んでいて数年間働けなかった時期もあったし、病気やけがで手術を2回して痛みに堪えて、治療の成果でまた普通の生活に戻れるようになったことを経験している。
小さいころから、病気は治すもの、元気になってまた日常にもどるもの、と思ってきたので、死にたいとか、このまま死んでしまったら楽だろうか、とかそういう考えが頭をもたげることはなかった。
病気が苦になって、「俺は死ぬんだぁ!」と叫んだ人を身近に聞いているが、私は、そうならないような気がしているのだ。
60年も生きていると、身内の死に何度かであうが、死は生きていたときの苦しみから解放されて別の世界へ行く、と思える。
その意味では、宮子さんの「死は新しい世界への旅立ち」に共感できる。












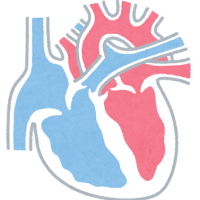

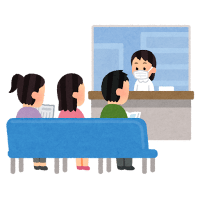













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます