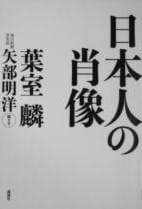調べてみると、2016年7月に文庫本として出版されているので、この表紙をまず引用した。
 私が読んだのは、この表紙の単行本である。
私が読んだのは、この表紙の単行本である。
本書は、雑誌『DENiM』掲載の「関西学」というコラムに執筆されたエッセイを中心に、他誌初出のエッセイ2つを含め、1995年8月に小学館・ DENiM books の1冊として出版されたものである。これは読後に奥書を読んで知ったこと。
この本を読む気になったのは、友人とのやりとりの中で、著者が江戸時代の学者富永仲基の主著である『出定後語』について触れていると知ったことによる。単純に著者がどういうことを書いているのかという関心からだった。本書が何を取り扱っているかも知らずに手に取った次第。
読後印象の結論を先に言えば、主として関東の人々が発言する、あるいはイメージを抱く「関西人は・・・・・」というステレオタイプに対して、一種もの申すというスタンスで反論を書き連ねているという感じのエッセイである。だが、ここにてんこもりに書き連ねられたものは、結構逆説的でアイロニカルな発言と観点に満ちている。
著者は言う。「私は、いわゆる大阪論、京都論の常套をこわすことを、めざしている。世間にころがっているゴミのような関西論を茶化したい。こんな気持ちで、書きつづけているのである」(p88)と。
四半世紀近い前に書かれたエッセイなので、話材に使われている事例などははやなつかしいなあ・・・・と思い出す類いのことが多くある。しかし、ここで論じられているのは、おもに関東から見た関西論、関西人論への問題提起であり、また関西に在住する著者が地元の近畿をどうみて、どうとらえているかの所見でもある。近畿つまりかつて政権の中枢となった「畿内」をそこに住む人間が自らを「関西」と呼ぶことにも、アイロニカルな視点で著者は論じているから、おもしろい。そう言われればそうだな・・・・と思うところが、あちらこちらに出てくる。
書かれて二十有余年もたつが、問題指摘の点や論点は今も変わらず厳然と続いているように思う。関西論、関西人論がそんなに急変するわけがない。連綿と同じような色眼鏡、ステレオタイプな見方は継続されているように思う。
私が本書を読むきっかけになった事に関しては、第1章「関西弁の真実」に収録された「関西弁は議論に向かないという知識人」というタイトルのエッセイに出てくる。著者は富本仲基という大坂の商家育ち、ナニワのアキンド、コテコテの大阪弁、バリバリの関西弁の人物が、18世紀に今日風に言えば知識社会学とも言える仏教研究書を出版していて、関西弁がその中に出てくるという事例に取り上げただけだった。私はこの書の内容に触れているのかと想像していたのだが、それは肩すかしだった。だが、「関西弁は議論に向かない」というステレオタイプに対する反論事例として例示しているのはおもしろいと思った。著者は言う。「関西弁でも、抽象的な思考はできる」「思想的営為を積み重ねることは、できる」と。そらそうや、あたりまえやないか・・・・と同意する。
第1章に収録の「オーマン港をなんと読む?」というエッセイがこっけいである。放送禁止用語からみの裏話、著者の体験談といえようか。また、「マスコミのつくる関西弁」は皮肉たっぷりである。
ステレオタイプの関西論、関西人論について論じた初出のコラム欄が「関西学」だという。『関西人の正体』というタイトルづけもまた逆説的でおもしろい。ステレオタイプな思い込み、偏見的見方に反論し、関西をいわばミソもクソも一緒くたにして一つの見方で論じることに反論しているはずなのに、「関西人の正体」がひとつである様なイメージを与えかねないタイトルのネーミングになっている。さらに、ここでは反論の事例や話材は主に大阪と京都の事例である。近畿地方を関西というなら、その他の県はほとんど出て来ない。著者が関西論、関西人論で反論しているのも、ある意味では地域限定と言えるかもしれない。京都人の一読者としては、限定された範囲内の地域で生活してきているので、わりとすんなり、このエッセイをおもしろ、おかしく、時にナルホドとうなづきつつ読み終えた。
せっかくなので、単行本と文庫本の表紙関連で少しご紹介しておく。
単行本の表紙のイラストは、第2章「大阪の正体」に収録の「”大阪のパワー”と人がいうとき」に直接関連する。大阪の町並みが大阪ミナミの町並に直結し、そのイメージがこの人形に直結していくという事例として出てくる。このステレオタイプな見方を俎上にあげる。一方、「江戸こそ食いだおれの街」というエッセイの最後あたりにも、この人形の出番が来る。
文庫本の舞妓さんの左のオバチャン。「大阪の女はケバい」というエッセイに関連する。だが、著者は関東のマスコミが、大阪のハデな女の映像をステレオタイプに切り出させているに過ぎない、大阪以上に東京の方がハデな人が集まるスポットは多いと論じる。これはマスコミが作り出すステレオタイプの問題点を指摘している。「テレビは、宿命的に紋切型しかうつさないメディアなのである」(p81)と論じている。
この章に「”風俗発祥の地・大阪”というぬれぎぬ」というエッセイがある。昔なつかしい言葉をここで目にした。「ノーパン喫茶」という語句。なんとこの発祥地は大阪ではなく、京都だったというのを初めて知った。この点に関し自信があると著者はいう。また、「ホルモン焼き誕生秘話」は「ホルモン」の解釈に蘊蓄が傾けられていておもしろい。
文庫本の僧侶(坊主)のイラスト。これは第3章「京都の正体」に収録の「ぼんさんがへをこいた」というエッセイに関連する。「坊主」という言葉の使われ方を論じるとともに、京都における僧侶の多さに触れ、また「ぼんさん」が坊主にからむのか、丁稚制度の丁稚にからむのかを論じていて興味深い。
「京都の景観なんて、どうでもいい」というエッセイはまさに反語的な見出しだが、京都の現状を的確にとらえていると思う。景観保護問題の規制についてのいびつな運用を皮肉たっぷりに論じている。京都の伝統的な景観美の頽落をくい止められないのは京都の経済力の有無との二律背反だと論じている。
「京の町家」というエッセイでは、町屋の景観が破壊されていく必然性を解き明かしている。税制、都市行政が一般の町屋存続を不可能にしている側面を指摘する。そして、他府県で京都村をこしらえてはという声を事例に取り上げる。「きっと、そんなところでは、舞妓や芸妓が、アルバイト学生の仕事になるんやろな」と記す。舞妓さんのイラストはこのエッセイに直接関連しているように思う。ホントの舞妓ではなく、似非舞妓の発生という展開への連想に。イラストの着物に般若の絵が書かれているのは、仮面の連想かも・・・・。本物の舞妓さんならそんな図柄の着物を着るはずがない。そう言えば、最近は借衣裳の舞妓姿の京都歩きはあまりみかけない。一方で見るからに借り物の着物姿京都名所観光組がやたら目につくようになってきた。似非舞妓姿の影が相対的に薄まっただけなのかも・・・・しれないが。似非舞妓姿はブームが下火になったのかな?
僧侶のイラストの右側に阪神ファンの人物イラストが描かれている。これは第4章「関西全体への大誤解」の中に収録されている「阪神ファンでないひとの運命」に関連しているのだろう。本文は「私は、阪神ファンである」の書き出しから始まるエッセイである。阪神ファンの悲喜劇をおもしろおかしくまとめている。野球に関心のない私には、ファンの心境はわからないが。だがこのエッセイのアイロニカルなおもしろみは楽しめた。
最後に、エッセイに出てくる著者の所見のいくつかをご紹介しておこう。思考素材になる。
*もちろん、バイタリティを強調するのは、東京からくる論客だけではない。地元のジャーナリズムも、しばしば同じことを力説する。大阪の底力を、うたいあげる。
ちなみに、底力がうんぬんされるのは、没落地帯の特性である。 p55
*ケバい女が多いからそうなるのではない。彼女たちの集まれるスポットが限られているから、集積度が高くなる。狭いエリアにやってくるから、群がるという印象になる。 p82
*文化の中心地では、ユニークさだけが、クローズ・アップされることはない。標準的な思考、制度的な理念も、じゅうぶんに浮上する。
中心地には、文化の諸相があるれている。ひとつの相だけが目につくというようなことはない。
だが、辺境地は違う。そこには、文化の全局面をうきたたせるだけの力がない。浮上してくるのは、一部のものだけである。・・・・
辺境地が中央にたいして独自性がほこれるのもこの点だ。そこには、中央にはないユニークな部分でしか、自己の存在をアピールすることができないのである。中央に対峙できるのは、ここだけなのだ。 p102
*一方は、東京化の波を関西へ押しつけてきた。そして、もう一方は、その東京化に抵抗しつづける者を、もちあげる。たがいのめざす方向は、まったく逆であるように、見えかねない。だが、この両者、じっさいは共犯関係にあるのではないか。 p186
*政治の力が東へうつる。経済の中心も移動する。文化も右へならへとなる。
この傾向は、どうあがいてもとめられまい。首都・東京都の格差は、これ以後もひろがる一方であろう。京・大阪は没落を運命として甘受するほかあるまい。 p210
この本、ところどころに喜多桐スズメさんの4コマ漫画が併載されている。本文のエッセイと呼応していておもしろい。
ご一読ありがとうございます。

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
 私が読んだのは、この表紙の単行本である。
私が読んだのは、この表紙の単行本である。本書は、雑誌『DENiM』掲載の「関西学」というコラムに執筆されたエッセイを中心に、他誌初出のエッセイ2つを含め、1995年8月に小学館・ DENiM books の1冊として出版されたものである。これは読後に奥書を読んで知ったこと。
この本を読む気になったのは、友人とのやりとりの中で、著者が江戸時代の学者富永仲基の主著である『出定後語』について触れていると知ったことによる。単純に著者がどういうことを書いているのかという関心からだった。本書が何を取り扱っているかも知らずに手に取った次第。
読後印象の結論を先に言えば、主として関東の人々が発言する、あるいはイメージを抱く「関西人は・・・・・」というステレオタイプに対して、一種もの申すというスタンスで反論を書き連ねているという感じのエッセイである。だが、ここにてんこもりに書き連ねられたものは、結構逆説的でアイロニカルな発言と観点に満ちている。
著者は言う。「私は、いわゆる大阪論、京都論の常套をこわすことを、めざしている。世間にころがっているゴミのような関西論を茶化したい。こんな気持ちで、書きつづけているのである」(p88)と。
四半世紀近い前に書かれたエッセイなので、話材に使われている事例などははやなつかしいなあ・・・・と思い出す類いのことが多くある。しかし、ここで論じられているのは、おもに関東から見た関西論、関西人論への問題提起であり、また関西に在住する著者が地元の近畿をどうみて、どうとらえているかの所見でもある。近畿つまりかつて政権の中枢となった「畿内」をそこに住む人間が自らを「関西」と呼ぶことにも、アイロニカルな視点で著者は論じているから、おもしろい。そう言われればそうだな・・・・と思うところが、あちらこちらに出てくる。
書かれて二十有余年もたつが、問題指摘の点や論点は今も変わらず厳然と続いているように思う。関西論、関西人論がそんなに急変するわけがない。連綿と同じような色眼鏡、ステレオタイプな見方は継続されているように思う。
私が本書を読むきっかけになった事に関しては、第1章「関西弁の真実」に収録された「関西弁は議論に向かないという知識人」というタイトルのエッセイに出てくる。著者は富本仲基という大坂の商家育ち、ナニワのアキンド、コテコテの大阪弁、バリバリの関西弁の人物が、18世紀に今日風に言えば知識社会学とも言える仏教研究書を出版していて、関西弁がその中に出てくるという事例に取り上げただけだった。私はこの書の内容に触れているのかと想像していたのだが、それは肩すかしだった。だが、「関西弁は議論に向かない」というステレオタイプに対する反論事例として例示しているのはおもしろいと思った。著者は言う。「関西弁でも、抽象的な思考はできる」「思想的営為を積み重ねることは、できる」と。そらそうや、あたりまえやないか・・・・と同意する。
第1章に収録の「オーマン港をなんと読む?」というエッセイがこっけいである。放送禁止用語からみの裏話、著者の体験談といえようか。また、「マスコミのつくる関西弁」は皮肉たっぷりである。
ステレオタイプの関西論、関西人論について論じた初出のコラム欄が「関西学」だという。『関西人の正体』というタイトルづけもまた逆説的でおもしろい。ステレオタイプな思い込み、偏見的見方に反論し、関西をいわばミソもクソも一緒くたにして一つの見方で論じることに反論しているはずなのに、「関西人の正体」がひとつである様なイメージを与えかねないタイトルのネーミングになっている。さらに、ここでは反論の事例や話材は主に大阪と京都の事例である。近畿地方を関西というなら、その他の県はほとんど出て来ない。著者が関西論、関西人論で反論しているのも、ある意味では地域限定と言えるかもしれない。京都人の一読者としては、限定された範囲内の地域で生活してきているので、わりとすんなり、このエッセイをおもしろ、おかしく、時にナルホドとうなづきつつ読み終えた。
せっかくなので、単行本と文庫本の表紙関連で少しご紹介しておく。
単行本の表紙のイラストは、第2章「大阪の正体」に収録の「”大阪のパワー”と人がいうとき」に直接関連する。大阪の町並みが大阪ミナミの町並に直結し、そのイメージがこの人形に直結していくという事例として出てくる。このステレオタイプな見方を俎上にあげる。一方、「江戸こそ食いだおれの街」というエッセイの最後あたりにも、この人形の出番が来る。
文庫本の舞妓さんの左のオバチャン。「大阪の女はケバい」というエッセイに関連する。だが、著者は関東のマスコミが、大阪のハデな女の映像をステレオタイプに切り出させているに過ぎない、大阪以上に東京の方がハデな人が集まるスポットは多いと論じる。これはマスコミが作り出すステレオタイプの問題点を指摘している。「テレビは、宿命的に紋切型しかうつさないメディアなのである」(p81)と論じている。
この章に「”風俗発祥の地・大阪”というぬれぎぬ」というエッセイがある。昔なつかしい言葉をここで目にした。「ノーパン喫茶」という語句。なんとこの発祥地は大阪ではなく、京都だったというのを初めて知った。この点に関し自信があると著者はいう。また、「ホルモン焼き誕生秘話」は「ホルモン」の解釈に蘊蓄が傾けられていておもしろい。
文庫本の僧侶(坊主)のイラスト。これは第3章「京都の正体」に収録の「ぼんさんがへをこいた」というエッセイに関連する。「坊主」という言葉の使われ方を論じるとともに、京都における僧侶の多さに触れ、また「ぼんさん」が坊主にからむのか、丁稚制度の丁稚にからむのかを論じていて興味深い。
「京都の景観なんて、どうでもいい」というエッセイはまさに反語的な見出しだが、京都の現状を的確にとらえていると思う。景観保護問題の規制についてのいびつな運用を皮肉たっぷりに論じている。京都の伝統的な景観美の頽落をくい止められないのは京都の経済力の有無との二律背反だと論じている。
「京の町家」というエッセイでは、町屋の景観が破壊されていく必然性を解き明かしている。税制、都市行政が一般の町屋存続を不可能にしている側面を指摘する。そして、他府県で京都村をこしらえてはという声を事例に取り上げる。「きっと、そんなところでは、舞妓や芸妓が、アルバイト学生の仕事になるんやろな」と記す。舞妓さんのイラストはこのエッセイに直接関連しているように思う。ホントの舞妓ではなく、似非舞妓の発生という展開への連想に。イラストの着物に般若の絵が書かれているのは、仮面の連想かも・・・・。本物の舞妓さんならそんな図柄の着物を着るはずがない。そう言えば、最近は借衣裳の舞妓姿の京都歩きはあまりみかけない。一方で見るからに借り物の着物姿京都名所観光組がやたら目につくようになってきた。似非舞妓姿の影が相対的に薄まっただけなのかも・・・・しれないが。似非舞妓姿はブームが下火になったのかな?
僧侶のイラストの右側に阪神ファンの人物イラストが描かれている。これは第4章「関西全体への大誤解」の中に収録されている「阪神ファンでないひとの運命」に関連しているのだろう。本文は「私は、阪神ファンである」の書き出しから始まるエッセイである。阪神ファンの悲喜劇をおもしろおかしくまとめている。野球に関心のない私には、ファンの心境はわからないが。だがこのエッセイのアイロニカルなおもしろみは楽しめた。
最後に、エッセイに出てくる著者の所見のいくつかをご紹介しておこう。思考素材になる。
*もちろん、バイタリティを強調するのは、東京からくる論客だけではない。地元のジャーナリズムも、しばしば同じことを力説する。大阪の底力を、うたいあげる。
ちなみに、底力がうんぬんされるのは、没落地帯の特性である。 p55
*ケバい女が多いからそうなるのではない。彼女たちの集まれるスポットが限られているから、集積度が高くなる。狭いエリアにやってくるから、群がるという印象になる。 p82
*文化の中心地では、ユニークさだけが、クローズ・アップされることはない。標準的な思考、制度的な理念も、じゅうぶんに浮上する。
中心地には、文化の諸相があるれている。ひとつの相だけが目につくというようなことはない。
だが、辺境地は違う。そこには、文化の全局面をうきたたせるだけの力がない。浮上してくるのは、一部のものだけである。・・・・
辺境地が中央にたいして独自性がほこれるのもこの点だ。そこには、中央にはないユニークな部分でしか、自己の存在をアピールすることができないのである。中央に対峙できるのは、ここだけなのだ。 p102
*一方は、東京化の波を関西へ押しつけてきた。そして、もう一方は、その東京化に抵抗しつづける者を、もちあげる。たがいのめざす方向は、まったく逆であるように、見えかねない。だが、この両者、じっさいは共犯関係にあるのではないか。 p186
*政治の力が東へうつる。経済の中心も移動する。文化も右へならへとなる。
この傾向は、どうあがいてもとめられまい。首都・東京都の格差は、これ以後もひろがる一方であろう。京・大阪は没落を運命として甘受するほかあるまい。 p210
この本、ところどころに喜多桐スズメさんの4コマ漫画が併載されている。本文のエッセイと呼応していておもしろい。
ご一読ありがとうございます。

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。