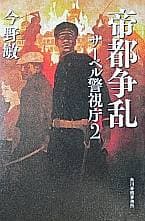立花登シリーズ第2弾。短編5本の連作集になっている。各短編は読み切りであるが、この5編の連なりには通底していく流れが引きつづき2つある。1つは勿論、町医小牧玄庵家の玄関わきの部屋に居候する立花登と叔父玄庵、叔母、娘のおちえとの人間関係である。もう1つは登にとって柔術の友、新谷弥助が第1作の短編連作途中から不可解な行動を取り始めたことに関連する。弥助は道場に行くと言って家を出た後、道場に出ることもなく深川の地回りたちと行動を共にするようになったのだ。この2つの流れが所々に織り込まれながら、個々の短編のストーリーが進んで行く。
この第2弾には、「老賊」「幻の女」「押し込み」「化粧する女」「処刑の日」が収められている。1980(昭和55)年に「小説現代」に連載され、1983年11月に文庫化されている。
登と小牧家との人間関係は、「化粧する女」に登の思いとして次のように描き込まれるようになる。「叔父夫妻は、とっくの昔におちえの婿に据えて、老後は左うちわと決めてしまったらしく、近ごろは言葉のはしばしに平気でそういうことを匂わせる」(p174)。「あれだけ叔母の尻にしかれている叔父が、ずいぶん反対もされたろうに、よくも自分を江戸に呼んでくれたものだと思う気持。たしかに口やかましいが、いやな顔ひとつせずに汚れ物を洗い、縫い物をしてくれる叔母、そういえばこの間は月の小遣いを一分ふやしてくれたしなどと思ったり、おちえも以前とくらべれば、少しは行状も改まったようではないかと見直したり、要するにそういう日常の感慨の底に、少しずつあきらめの気持がたまって来て、ある日は不意に、叔父の家の婿におさまったからといって、学問が出来ないわけでもあるまいと思ったりする。」(p174-175)そして、登が家に戻り、井戸端で行水を始めると、「登兄さん、背中流しましょうか?」とおちえが行動する場面が織り込まれていく。さらに、「処刑の日」の末尾には、「『ほうびはこれだぞ』登はおおちえの身体をすっぽり抱えると軽く口を吸った。きゃっと叫んで逃げるかと思ったら、おちえは動かなかった。眼を閉じてじっとしている。・・・・」(p255) という展開になっていく。
そして、この後、第3弾に続いていくことになる。
さて、各短編について、簡単にご紹介しておきたい。
<老賊>
ストーリーは鴨井道場で登がおとうと弟子に稽古をつける場面からさりげなく始まる。登と師範代の奥野との間で、新谷弥助の家を登が二度訪れたが留守だったこと。道場に姿を表さないこと。奥野が知り合いを訪ねた帰りに深川の櫓下、遊郭の近くで地回りのならず者と弥助がいたのを見かけたこと。その折、奥野を見ると弥助が顔をそむけ知らぬふりをしたことなどが語られる。その結果、登は奥野から弥助の様子をさぐってくれと依頼をうける。これがこの第2弾の底流の一つになっていく。
さて、この短編は東の二間牢の60を過ぎた捨蔵と名乗る囚人の話である。無宿者で盗みの罪はすらすらと白状したが、それ以外は口を閉ざしているという。登は彼の症状を考慮し、溜に行くかと捨蔵に尋ねる。捨蔵は助からない命なら、死ぬ前に娘と孫の顔を見たい。探してほしいと登に頼み込んだ。
浅草・阿部川町の弥五平長屋を皮切りに登は捨蔵の娘おちかを探し始める。弥五平長屋に住む女たちから、半年ほど前に40ぐらいの男がおちかの行方をさがしてここに来ていたという事を登は知る。一方、牢名主の長右衛門から、登は捨蔵が無宿牢への入牢の時、5両のツル(金)をぽんと出した。つまり、ただ者ではない。その後、新入りで牢をすぐに出て行っ男が捨蔵と話し込んでいた事実。長右衛門はその男が守宮の助だと思い出したということを聞く。登はおちか探しのために岡っ引きの藤助に協力を頼むことに・・・・・。おちかに会い話を聞いた登は、その後あることに気づく。危機一髪でのどんでん返し、そこにおもしろい視点が潜んでいる。著者は登に「捨て身の隅返し」と言わせている。
<幻の女>
<老賊>の末尾で、新谷弥助に関わることが少し語られ、この短編の冒頭も登が弥助の家を訪れる場面から始まる。弥助に関わる通底ストーリーがまず進展していく。
腕のいい蒔絵師巳之吉が口論の末に男二人を刺し、その足で自首して出た。争いの因は賭場でのもつれという。巳之吉は遠島の刑を言い渡されていて、あとひと月ほどで流人船が来る予定だった。巳之吉の病状を診た折、登は巳之吉から一度はさがし、所帯をもとうと思ったというおこまという娘の話を聞いた。登は巳之吉がおこまの最後の消息を聞いたという長屋を訪ねてみる。そこから話が始まって行く。そして、登は意外な事実にたどり着いていく。流人船に乗るために裏門から出て行く巳之吉に登は知り得た事実を告げなかった。巳之吉は己の胸中に「幻の女」を抱いたまま島送りとなる。
事実を知るより幸せか・・・・。告げない選択に、登の人情観が込められている。
<押し込み>
末を約束した男の裏切りに傷つきその男を刺したおしんは、特別の吟味の後牢を出されて、今は両国橋南河岸にある水茶屋しのぶで再び元気に働いている。道場からの帰りにおしんの様子を見がてら立ち寄った登は、店の中で三人組に目をとめた。その三人組-源次・金平・保次郎-は押し込みの計画を相談していたのだ。源次が奉公していた三吉屋という大きな足袋屋の娘、おしづの境遇に対する同情心を発端とした三者三様の思惑がらみで押し込み計画を彼等は練っていたのである。
朝の見回りのとき、大牢の牢格子から手を振り声を掛けてきた囚人金平に登は頼まれる。源次と保次郎に「じゃまが入った、やめろ」と伝えてほしいと。登は勿論、拒否する。だが、金平は「人の命がかかっている」という。さらに、夜の見回りの折に、金平は登に同じ店をむささびの七の一味が狙っているのだと一歩踏み込んで頼み込んだ。
瓢箪から駒のストーリー展開になっていく。馬鹿な男たちを助けるために、登が起ち上がる。2ヵ月ぶりに道場に現れた新谷弥助に手伝わせて・・・・。
表には出すことができない登と弥助の武勇伝にもなる。
<化粧する女>
房五郎は押し借りの罪で吟味を受け、敲きの上江戸払いと決まり、仕置きを待つ身である。その房五郎を奉行所吟味方与力高瀬甚左衛門が定法を逸した牢問にかけている。お奉行はしばらく高瀬のやることを黙認せよと裁断しているという。奉行の黙認を取り付けられるだけの何かがあるのだ。高瀬は房五郎がケチな押し借りではなく、百両の大金が絡んだ悪事に荷担しているとみて執拗に白状させようとしていた。
当初房五郎に不審を感じていた登は高瀬のやりすぎの牢問に憤りを感じる。そして房五郎をつかまえた岡っ引きが百助と知り、百助の話を聞きに出かけたことから、房五郎の女房おつぎに会ってみようという気になった。それは登が真相に近づいていくはじまりとなる。
色と欲のなせる業の一典型が描き出されて行く。登にはおぞましい記憶が残ることに・・・・。
<処刑の日>
登の住む福井町の隣町平右衛門町で筆墨と紙を商う大津屋の主人助右衛門が入牢していた。梅雨の頃に、妾のおつまを刺し殺したという罪である。助右衛門は吟味の席では終始無罪を言い立てた。しまいには、手当ての金のもつれで妾を殺したと白状し、口書きに爪印をとられていた。助右衛門が血のしたたる庖丁を持って立ち尽くす姿を何人もが目撃していたのだった。今、助右衛門は死罪の言い渡しを待つ囚人である。養女のおゆきは16歳で、既に婿が決まっている大津屋の跡取りだった。だが、助右衛門が死罪になれば、大津屋がどうなるかはわからない。
助右衛門を知る登は、彼が殺したとは到底信じられない。登は独自に調べ始める。
一方、併行して、登は新谷弥助の行状を直蔵に協力してもらい探っていた。弥助の兄多一郎や師匠の鴨井左仲に事情を知られる前に、弥助を深川の悪所から引き離す必要があった。どうも市之助というあくどい金貸しがからんでいるようだった。
二つのストーリーがパラレルに進行していく。
おちえが思わぬ場面を目撃していた。三日前におちえが仲よしのみきと一緒に東両国の軽業を見に出かけた帰路、柳橋の川口のところにある船宿三吉屋から大津屋のおかみと手代の新七が前後して出てくるのを見たという。登に告げておちえは気持がすっきりしたと言う。登は、このことを誰にも言うなと口止めする。登は助右衛門のこととの関係で調べる一つの突破口を得ることができた。登は叔父から大津屋の事情を聞き出すことから初めていく。新七は大津屋の子飼いではなかったが、商いの腕が確かなところが見込まれて、おゆきの婿に決められていたことがわかる。
登の疑念を解明するための行動に対して、死罪の言い渡しが何時あるか・・・・・切迫するタイムリミットとの競走が始まる。
併せて、深川の悪所から弥助を引き離すために、登は師範代の奥野の協力を得て一計を案じる。
異質の二つの話が進展していくことが、この短編に奥行を持たせている。また、上記の「ごほうび」の理由がこれでおわかりになるだろう。
立花登の事件解明ストーリーとそのプロセスでの人情味の発露にますます惹かれていく第2弾である。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『春秋の檻 獄医立花登手控え1』 講談社文庫
この第2弾には、「老賊」「幻の女」「押し込み」「化粧する女」「処刑の日」が収められている。1980(昭和55)年に「小説現代」に連載され、1983年11月に文庫化されている。
登と小牧家との人間関係は、「化粧する女」に登の思いとして次のように描き込まれるようになる。「叔父夫妻は、とっくの昔におちえの婿に据えて、老後は左うちわと決めてしまったらしく、近ごろは言葉のはしばしに平気でそういうことを匂わせる」(p174)。「あれだけ叔母の尻にしかれている叔父が、ずいぶん反対もされたろうに、よくも自分を江戸に呼んでくれたものだと思う気持。たしかに口やかましいが、いやな顔ひとつせずに汚れ物を洗い、縫い物をしてくれる叔母、そういえばこの間は月の小遣いを一分ふやしてくれたしなどと思ったり、おちえも以前とくらべれば、少しは行状も改まったようではないかと見直したり、要するにそういう日常の感慨の底に、少しずつあきらめの気持がたまって来て、ある日は不意に、叔父の家の婿におさまったからといって、学問が出来ないわけでもあるまいと思ったりする。」(p174-175)そして、登が家に戻り、井戸端で行水を始めると、「登兄さん、背中流しましょうか?」とおちえが行動する場面が織り込まれていく。さらに、「処刑の日」の末尾には、「『ほうびはこれだぞ』登はおおちえの身体をすっぽり抱えると軽く口を吸った。きゃっと叫んで逃げるかと思ったら、おちえは動かなかった。眼を閉じてじっとしている。・・・・」(p255) という展開になっていく。
そして、この後、第3弾に続いていくことになる。
さて、各短編について、簡単にご紹介しておきたい。
<老賊>
ストーリーは鴨井道場で登がおとうと弟子に稽古をつける場面からさりげなく始まる。登と師範代の奥野との間で、新谷弥助の家を登が二度訪れたが留守だったこと。道場に姿を表さないこと。奥野が知り合いを訪ねた帰りに深川の櫓下、遊郭の近くで地回りのならず者と弥助がいたのを見かけたこと。その折、奥野を見ると弥助が顔をそむけ知らぬふりをしたことなどが語られる。その結果、登は奥野から弥助の様子をさぐってくれと依頼をうける。これがこの第2弾の底流の一つになっていく。
さて、この短編は東の二間牢の60を過ぎた捨蔵と名乗る囚人の話である。無宿者で盗みの罪はすらすらと白状したが、それ以外は口を閉ざしているという。登は彼の症状を考慮し、溜に行くかと捨蔵に尋ねる。捨蔵は助からない命なら、死ぬ前に娘と孫の顔を見たい。探してほしいと登に頼み込んだ。
浅草・阿部川町の弥五平長屋を皮切りに登は捨蔵の娘おちかを探し始める。弥五平長屋に住む女たちから、半年ほど前に40ぐらいの男がおちかの行方をさがしてここに来ていたという事を登は知る。一方、牢名主の長右衛門から、登は捨蔵が無宿牢への入牢の時、5両のツル(金)をぽんと出した。つまり、ただ者ではない。その後、新入りで牢をすぐに出て行っ男が捨蔵と話し込んでいた事実。長右衛門はその男が守宮の助だと思い出したということを聞く。登はおちか探しのために岡っ引きの藤助に協力を頼むことに・・・・・。おちかに会い話を聞いた登は、その後あることに気づく。危機一髪でのどんでん返し、そこにおもしろい視点が潜んでいる。著者は登に「捨て身の隅返し」と言わせている。
<幻の女>
<老賊>の末尾で、新谷弥助に関わることが少し語られ、この短編の冒頭も登が弥助の家を訪れる場面から始まる。弥助に関わる通底ストーリーがまず進展していく。
腕のいい蒔絵師巳之吉が口論の末に男二人を刺し、その足で自首して出た。争いの因は賭場でのもつれという。巳之吉は遠島の刑を言い渡されていて、あとひと月ほどで流人船が来る予定だった。巳之吉の病状を診た折、登は巳之吉から一度はさがし、所帯をもとうと思ったというおこまという娘の話を聞いた。登は巳之吉がおこまの最後の消息を聞いたという長屋を訪ねてみる。そこから話が始まって行く。そして、登は意外な事実にたどり着いていく。流人船に乗るために裏門から出て行く巳之吉に登は知り得た事実を告げなかった。巳之吉は己の胸中に「幻の女」を抱いたまま島送りとなる。
事実を知るより幸せか・・・・。告げない選択に、登の人情観が込められている。
<押し込み>
末を約束した男の裏切りに傷つきその男を刺したおしんは、特別の吟味の後牢を出されて、今は両国橋南河岸にある水茶屋しのぶで再び元気に働いている。道場からの帰りにおしんの様子を見がてら立ち寄った登は、店の中で三人組に目をとめた。その三人組-源次・金平・保次郎-は押し込みの計画を相談していたのだ。源次が奉公していた三吉屋という大きな足袋屋の娘、おしづの境遇に対する同情心を発端とした三者三様の思惑がらみで押し込み計画を彼等は練っていたのである。
朝の見回りのとき、大牢の牢格子から手を振り声を掛けてきた囚人金平に登は頼まれる。源次と保次郎に「じゃまが入った、やめろ」と伝えてほしいと。登は勿論、拒否する。だが、金平は「人の命がかかっている」という。さらに、夜の見回りの折に、金平は登に同じ店をむささびの七の一味が狙っているのだと一歩踏み込んで頼み込んだ。
瓢箪から駒のストーリー展開になっていく。馬鹿な男たちを助けるために、登が起ち上がる。2ヵ月ぶりに道場に現れた新谷弥助に手伝わせて・・・・。
表には出すことができない登と弥助の武勇伝にもなる。
<化粧する女>
房五郎は押し借りの罪で吟味を受け、敲きの上江戸払いと決まり、仕置きを待つ身である。その房五郎を奉行所吟味方与力高瀬甚左衛門が定法を逸した牢問にかけている。お奉行はしばらく高瀬のやることを黙認せよと裁断しているという。奉行の黙認を取り付けられるだけの何かがあるのだ。高瀬は房五郎がケチな押し借りではなく、百両の大金が絡んだ悪事に荷担しているとみて執拗に白状させようとしていた。
当初房五郎に不審を感じていた登は高瀬のやりすぎの牢問に憤りを感じる。そして房五郎をつかまえた岡っ引きが百助と知り、百助の話を聞きに出かけたことから、房五郎の女房おつぎに会ってみようという気になった。それは登が真相に近づいていくはじまりとなる。
色と欲のなせる業の一典型が描き出されて行く。登にはおぞましい記憶が残ることに・・・・。
<処刑の日>
登の住む福井町の隣町平右衛門町で筆墨と紙を商う大津屋の主人助右衛門が入牢していた。梅雨の頃に、妾のおつまを刺し殺したという罪である。助右衛門は吟味の席では終始無罪を言い立てた。しまいには、手当ての金のもつれで妾を殺したと白状し、口書きに爪印をとられていた。助右衛門が血のしたたる庖丁を持って立ち尽くす姿を何人もが目撃していたのだった。今、助右衛門は死罪の言い渡しを待つ囚人である。養女のおゆきは16歳で、既に婿が決まっている大津屋の跡取りだった。だが、助右衛門が死罪になれば、大津屋がどうなるかはわからない。
助右衛門を知る登は、彼が殺したとは到底信じられない。登は独自に調べ始める。
一方、併行して、登は新谷弥助の行状を直蔵に協力してもらい探っていた。弥助の兄多一郎や師匠の鴨井左仲に事情を知られる前に、弥助を深川の悪所から引き離す必要があった。どうも市之助というあくどい金貸しがからんでいるようだった。
二つのストーリーがパラレルに進行していく。
おちえが思わぬ場面を目撃していた。三日前におちえが仲よしのみきと一緒に東両国の軽業を見に出かけた帰路、柳橋の川口のところにある船宿三吉屋から大津屋のおかみと手代の新七が前後して出てくるのを見たという。登に告げておちえは気持がすっきりしたと言う。登は、このことを誰にも言うなと口止めする。登は助右衛門のこととの関係で調べる一つの突破口を得ることができた。登は叔父から大津屋の事情を聞き出すことから初めていく。新七は大津屋の子飼いではなかったが、商いの腕が確かなところが見込まれて、おゆきの婿に決められていたことがわかる。
登の疑念を解明するための行動に対して、死罪の言い渡しが何時あるか・・・・・切迫するタイムリミットとの競走が始まる。
併せて、深川の悪所から弥助を引き離すために、登は師範代の奥野の協力を得て一計を案じる。
異質の二つの話が進展していくことが、この短編に奥行を持たせている。また、上記の「ごほうび」の理由がこれでおわかりになるだろう。
立花登の事件解明ストーリーとそのプロセスでの人情味の発露にますます惹かれていく第2弾である。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『春秋の檻 獄医立花登手控え1』 講談社文庫